| �P�M�Z�̉Y�����Y |
|||||||||||||||
| �̂������ƁB �ؑ]��ɂ��Y�����Y���������ƁB ���Y�͏㏼�̐Q�o�m���ɏZ��ŁA������ɍ������ẮA�ނ莅������Ă����ƁB ����Ƃ��̂��ƁA���Y�������̂悤�ɒނ�����Ă�����A�㗬�̑�ɂ����Ȃ�S�C�����o�ĂȁA�����Ƃ����Ԃ��Ȃ� ���Y�͐��Ɉ��܂�Ă��܂����Ƃ��B ���ꂩ��ǂ̂��ꂦ�����������A�ӂƋC�����Ă݂���A���Y�͍��܂łɌ������Ƃ��˂��悤�Ȃ��ꂢ�ȍ��~�� �Q������Ă���ƁB �������Ă��ł́A����܂����ꂢ�ȏ��̐l���A�S�z�����ɑ��Y�������Ƃ̂�������ł���ł˂����B ���Y�͂��܂��ĂƂыN����ƁA�u�����͂ǂ�����v���Ă����˂��ƁB ���������炻�̏��̐l�́A�ɂ�������āu�����͗��{�ł������܂��B���͉��P�ł��B�v���āA���������ƁB �͂��A������Ă��Ƃ��ꂪ�b�ɕ������{���ƁA���Y�͂܂��܂����܂��Ă��܂����Ƃ��B ���ꂩ�牽�����������ɁA���Y�͂������肱���̕�炵���C�ɓ����Ă����ƁB ���P���܂͂��ꂢ�����A�������܂�����͐H���邵�ŁA���Y�͂��ꂱ�����̂悤�Ȗ������߂����Ă������Ƃ��B ����ǂ��ȁA���̋C����������ς���Ă��ĂȁA���܂ł������ɂ������Ă���킯�ɂ͂����˂��� �����v���悤�ɂȂ����B ����ł���Ƃ����P���܂ɂ킯��b�����Ƃ��낪�A�u�c�O�ł����d������܂���B�ł͂ǂ�����������������������B �ł������Ăӂ����J���Ă͂Ȃ�܂����B�J�����ɂ���A�����܂��A���̂܂܂̎p�ł���ł���ł��傤�B�v �ƁA���P���܂́A�����Ȃ���ɂ������ɋʎ蔠�Y�ɓn���Ȃ��炱���������������B �������đ��Y�́A�v���Ԃ�ɐQ�o�m���ɂ��ǂ��ė����B �Ƃ��낪�ǂ������킯���A������̎R���͂����Ƃ��l�q�͕ς��Ȃ��̂ɁA�N�ЂƂ�m�����l�����˂��B ��l�ڂ����̑��Y�́A����ł��܂��A�O�̂悤�Ɋ�ɍ������Ēނ莅������ĕ�炵�n�߂��ƁB ����ǂ����炭���邤���ɁA���Y�͉��P���܂��������Ă��܂�Ȃ��Ȃ��ĂȂ��A �ʂꂬ��ɂ�������ʎ蔠�̂��Ƃ��v���o���ƁA�J����Ȃ��Č���ꂽ���Ƃ��Y��āA ���A�ӂ����J���Ă��܂����Ƃ��B �ƁA���̂Ƃ���A�����甒�����������̂ڂ��ĕs�v�c��s�v�c�A���Y�݂͂�݂邤���� ���������܂̂������܂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����킯���B �J���Ă͂����Ȃ��ƌ����Ă����̂ɂ�������Ȃ�����������A�Ƃ��Ƃ����Y�͂��������A���P���܂Ƃ� ���������܂��ɂȂ��Ă��܂����B������͎����ƁB |
 |
||||||||||||||
| �Y�����Y�̓`�������� �Q�|�P�Q�o�̏� |
|||||||||||||||
| �@�Q�o�̏��͖ؑ]���i�̂����ōł��i���̒n�ƌ����Ă���B �@�ؑ]�삪�A���݂̋���ŋ��߂�ꂽ���ŁA��Ǝ��A����ɐ��̒��a���������B�������̗�Ԃ̑�����]�ނ��Ƃ��ł��A�ʉ݂̍ێԏ����ē����Ă���B �@�Q�o�̏��֍s���ɂ͏㏼�w����o�X�ŏ\�����A�Q�o�̏������ō~��ď�������ƗՐ쎛�Ƃ�����������B���̋������猩���낷�Q�o�̏��̕��i�������B�����̖͐����V�c�����z���ɂȂ����B���c���q�a����������ɂȂ������Ƃ�����Ƃ���A���̗Ր쎛�̂����������S���������ʂ��Ă���A���H���z���ĐQ�o�̏��ɍ~���B �@�傫�Ȋ�Ɗ�Ƃ̊Ԃɍ��Ɨƍ��킹���悤�Ȑ�������ł���B��ɂ̓r���E�u��A�^�^�~��A�R�V�J�P��A�V�V��A�}�i�C�^�ⓙ�X�Ɩ��������Ă��āA�Ȃ��Ȃ������ł���B �@���̐Q�o�̏��́A�́X�A�Y�����Y�����{����A���ė]���𑗂����Ƃ���Ƃ����`��������A�����̉Y�����ɂ͉Y���̒ނ�Ƃ�����B �@�Q�o�̏�����܁Z�Z���[�g�����̉����𗠐Q�o�Ƃ����B�Â����ŕ����Ē��Ȃ��Â��Ƃ���ł���B�Q�o�̏����痠�Q�o�܂ł̈�т͓V�R�A�����ŁA�ؑ\���L�̒������������Ă���B �@�㏼����̃o�X���~�肽�Q�o�̏������ɂ͐̂���̒��X������B�����̎������͂Ȃ��Ȃ����܂��ƕ]���ł���B �@�܂��㏼�t�߂̖����n�Ƃ��Ėؑ]�̎V������B�o�X�ŏ\�ܕ��ʂ����A�������ؑ]���i�̂ЂƂB �@�@�@�@�@�@�����͂��▽������ނ����Â� �Ɣm�Ԃ���Ƃ���B�ؑ]��̐[�����A�ނ����������݂̊ݕǁA�ؑ]�H�̓�������ʉe�����̂��B |
|||||||||||||||
| �Q�|�Q�Q�o�̏��̉Y�����Y | |||||||||||||||
| �@���{��Ŏ��̌o�̂��Y��V��ł����Y�����Y�́A������{�̖������A�}�ɉƂɋA�肽���Ȃ����B �@�����ŁA�����ɂ��Ƃ܂�����\���o��ƁA�����͑��蕨�Ƃ��āA�ٍ��V�̑����Ɩ���_���ꊪ�A����ɋʎ蔠�����ꂽ�B �@���Y���ƂA���Ă݂�ƁA�̋��͈�ς��Ă��āA��̒m��Ȃ��l����B �@���Y�͂�����������āA�̋������Ƃɏ������V�̗��ɏo���B �@�����āA�ؑ]�H�́u�Q�o�̏��v�ɗ��āA���Y�͂�������������C�ɓ������B �@�����A�D���Ȓނ���y���ޑ��Y�ł��������A������A���l�ɐ̘b���������łɋʎ蔠���J���Ă݂����B �@����ƁA�����率�̉����킫�o�āA���Y�݂͂�܂ɎO�S�̉��ɂȂ����B���Y�́u�p���̒r�v�Ɏ����������A���߂Ė{���̎����ɋC�t��������o�߂��B �@���Y�͗��{���玝���A�����ٍ��V�����̏�ɂ����ƁA�܂��ǂ��ւƂ��Ȃ����������čs�����B �@���ꂩ��A���Y�������o�܂������̟����u�Q�o�̏��v�Ƃ����A�ٍ��V���K���J���Ď��Ƃ����̂��Q�o�R�Ր쎛�Ƃ����Ă���B ���O���N�ԍ�ʂ̈�҉͉z�O�삪���̐Q�o�̏��ɏZ�݂����B�O��͐Q�o�̏��Œނ莅������A���Ƃ��Đl�X�ɗ^���A�S�Έȏ�̒�����ۂ������߁A�l�X�͂��̎O����Y�����Y�Ƃ����������Ƃ����Ă���B |
 |
||||||||||||||
| �R�Q�o�i�w�ȁ@�̖��𒆐S�Ƃ������́j | |||||||||||||||
| �M�Z�̍��ؑ]�̌S�ɁA�Q�o�̏��Ƃ�������������B�����́A���̍s�҂��A���炭�C�Ƃ����ꂽ�ꏊ�ł��邪�A���̌�ǂ�����Ƃ��m�ꂸ�A��l�̘V�l������ė��ďZ�݂����B���̂̒m��ʘV�l�ŐQ�o�̏��̖̍����܂���ɂ��āA���炵�Ă������A��Ԃ�̖�������Ă��āA�O�x��Ԃ����̂ŁA�O�Ԃ�̉��ƌĂ�Ă����B �@���̒�A���V�c�́A���̗R���������ɂȂ�A���̉����̖�����߂邽�߂ɁA���g���������B���g���Q�o�̏��ɒ����ƁA��l�̒j�����āA�Q�o�̏��̗R�������A���̖�������ƁA��ꂱ�����Ԃ�̉��Ɩ�����ď����������B�₪�āA��ɓ���ƁA�O�Ԃ�̉��͉̕��������A�_�ʎ��݂̏p�������āA���g�����ǂ납���A���̌��g�ɗ^���ď������B |
|||||||||||||||
| �S�|�P�Q�o�̏��̎�1 | |||||||||||||||
| ���̘b���͂킩��˂����A���������Ԃ�̂̂��Ƃɂ͈Ⴂ�˂��B �ؑ]��̂قƂ�Q�o�߂̗��ɂ́A�N�Ɉ�x�����낵���������肪���������Ă͂Ȃ����B ���N�H�Ƃ��Ȃ�ƌ��܂��āA�Ⴂ���̂���Ƃɔ��H�̖�Ƃ�ł��ĂȁA���ꂪ����������Ō�A ����Q�o�̏��̎�ɂ������ɂ�Ȃ�����B �����Ȃ���A�͂��A���̂�������Ă��̂��܂��������낵���B �����a�����s������A���Έꗱ����Ȃ�������A���̎҂�����݂�ȁA�т��т���炵�Ă��������ȁB ����Ȃ���N�̂��Ƃ��ƁB �܂��H���߂����Ă���ƁA�ꌬ�̉Ƃ̉����ɔ��H�̖�������B ���̉Ƃɂ͂����ƂA����Ɉ�l�̎Ⴂ�����������ȁA�O�l�Ƃ�����������ƂȂ�ƁA ���ꂱ����������ɒQ���߂������ȁB ���傤�ǂ��̍��A����̗��Ɉ�l�̍s�҂��܂��Z��ł������B �Ȃ�ł��������߂����ďC�s�ɏC�s���Ƃ��ŁA���̔O�͂͑�ςȂ��������Ă������B �����Ƃ͂����������̍s�҂��܂�K�ˁA[��������������������]���Ă���߂��ɗ��ƁB ���������ƍs�҂��܂́A���炭�Ւd�Ɍ������Ă��F�肵�Ă����A���������������̂��A ����Ȃ��Ƃ��������ƁB [�����̊ԂɁA�͂�ݒ����ꓪ�߂��Ă���̂���B��������Ύ�߂�łڂ��邩�������]�ƂȁB �����Ƃ͋}���ʼnƂɂ��ǂ�A�g�x�x���ƂƂ̂���ƎR�ւƌ��������B �������Ă������̎R�������̎R�Ɛh��������������ĂȁA���̂������Ƃ��Ƃ������ڂ̒��� �ꓪ�̂͂�ݒ����������Ƃ��B ���������s�҂��܂̂Ƃ���ւ����Ă����ƁA�s�҂��܂͒��̕��q�����o�����B �������đ����Ē������Â�̍j�ƁA����܂������ސj�������ɗp�ӂ����ĂȁA���������ŕ��q�����A �Q�o�̏��ւƏo�����Ă����������ȁB ������ɂ́A��ގ��̉\�����đ��l�����������玟�ւƏW�܂��ė����B �s�҂��܂͍����������ē��Â�Ɍ����q�ւƓ������ƁB ������Ă��Ƃǂ�����A���������ĕ��̐����S�H�[���ĉ����Ďn�߂ĂȁA �}�ɍj�����̂����������łǂ�ǂֈ������܂�n�߂��������B [����A�����������A�j������]�s�҂��܂̐��ɁA���l�����͖����ōj�ɂ����݂����B ���̒ꂩ��́A��̉�����������ς�炸�������͂ōj�������ς��Ă���B ���̂��������o�Ă����A������͗��݂Ă��ɂ܂�����ɂȂ��ł݂�Ȃ��ꂱ���������S�n�����˂��B ��ł������ōj�ɂ����݂��A�����ӂ�����Ƃ��B ���āA���ꂩ��ǂ̂��ꂦ���������A�S�Ȃ��������[���j���������ޗ͂���܂������Ǝv���ƁA ���������܂��Ă����ƁB [���ꍡ����A�����グ��]�s�҂��܂̍��}�ŁA���l�����͂���������Ƃ��ꂹ���ɍj��������悹���B �������Ă���Ƃ̂��ƂłЂ��グ�����Č�����A�Ȃ�Ă����Ƃ��B �������낵���قǂł������ł�������R�����ł˂����B �݂�Ȃ��ꂱ���A�ڂ�ʂƂяo��قǂ��܂��Ă��܂����B [���������̎傾�����̂���]���ĂȁA���X�ɂ��������Ă��ߑ������Ƃ��B ���ꂩ����Ă�����́A���H�̖�����Ƃ��Ȃ��Ȃ����B �������ĐQ�o�߂̗��ɂ́A���[���ƕ��a�Ȗ�����ꂪ���������Č������Ƃ��B(�M�Z�̘̐b���) |
|||||||||||||||
| �S�|�Q�˂��߂̏��̎�2 | |||||||||||||||
| �@�u�Q�o�̏��v�ɏZ�ގ�́A���~���߂��鍠�ɂȂ�ƁA���N���̖���l��l�g�䋟�ɂ����o���ƁA���̖��̉Ƃɔ��H�̖�𗧂Ă��B �@���H�̖�������Ƃ����Г�ŁA���������������������o���Ă����B �@�����A�Q�o�̏��̎�ɔw���Ė��������グ�Ȃ��ƁA�c���͎��炸�A���l�͋Q���Ď��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��B �@���N�́A�ǂ��̉Ƃɖ�����A�������т��т����Ă������A�V�v�w�̉Ƃ̉����ɔ��H�̖�˂��������Ă����B �@�V�v�w�ɂ́A���������܂ꂽ�������āA�O�l���ǂ���炵�Ă����B �@����ǁA���H�̖���ĂA����܂ł̍K�����A���ꂩ��̍K�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���ɂ́A���̏H�ɂ����ɗ���Ƃ�����҂������̂��B �@�V�v�w�́A�߂��݂ɂ���d������ɂ��Ȃ��������A�Ō�̗��݂��������M���Ă�����Ԃ̍s�҂ɂ����Ă݂��B �@�s�҂́A�V�v�w�̗��݂��āA�������܂��F��ɓ���A�₪�Đ_����̂��Ƃ��������B����ɂ��ƁA�u�����Ԃ̂����ɒ��̕��̎q�������Ă���悤�Ɂv�Ƃ������Ƃ������B �@���͏t�Ɏq���Y�ނ����ŁA���̉Ă̎����A���Ɏq�������ȂǁA�ǂ��ɂ����Ȃ��B����ł��A�V�v�w�͋������悤�ɂȂ��ĎR�����蒖��T�����B �@�����āA�肢�͓V�ɒʂ������A�܂������v�������Ȃ��⌊�ŁA�Q�Ă�������������邱�Ƃ��ł����B�V�v�w�́A���̒����s�҂̏��Ɏ����Ă����ƁA�s�҂͒�����������A���̖��ŕ��̎q���ۗg���ɂ����B �@�s�҂́A���l�����ߓ���̐�ɕ��̎q��t�����̟��[���������ꂽ�B���̂����A�����育�����������āA���܂킸�������������グ��ƁA���Â�̐�ɂ́A�Ȃ�ƘZ�ځi��[�g���j������R�������A���ڂ����点�������Ă����B �@���܂ŁA���l���ꂵ�߂��Q�o�̏��̎�Ƃ́A���̑�R�����������̂��B �@���ꂩ��A���~���߂��Ă����H�̖���������Ƃ��Ȃ��A���ɕs���͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����B |
|||||||||||||||
| 4-3�Q�o�̏��̎�3 | |||||||||||||||
| �Q�o�̑��ɂ͖��N�A������ꌬ�̉Ƃɗ��B �@���̓��ɂ́A���̉Ƃɂ��閺�������ɂ��Ƃ��ĐQ�o�̏��̎�ɂ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@�����č��N�͘V�v�w�̔����������̉Ƃɖ�������̂ł��B�V�v�w�͋������������ɂ��Ƃ��ďo�����Ƃɂ����B���������̎��A�E�C�����l�̒j���Q�o�̏���ʂ肩�������B�����Ă��̘b���A�Q�o�̏��̎��ގ����邱�Ƃɂ����B���̑���ɒj�����ɓ���A��̏��֍s�����B����ƐQ�o�̏��̎�Ƃ����̂́A�u�傫�Ȃ���ȁv�������B�j�͂������т��Ƃ�Ȃ��悤�ɂƖ������B |
 |
||||||||||||||
| �T�|�P�Y���`��1 | |||||||||||||||
| �ٍ��V�̑����A�A���{��ɍĂі߂��ė����閜��_���ꊪ�A�����ċʎ蔠���g���Č̋��ɋA���Ă����Y�����Y�B�����������͒N��l�Ƃ��Ēm��҂̖������m�̐��ԁB���������Y�͔�s�̏p�A�����̖�@�Ȃǂ��L���ꂽ���@�_����ǂ݁A���ɂ܂����ď����̗��ɏo�܂��B �����Ă��܂��܋C�ɓ����ďZ�ݒ������̂��Q�o�̏��B�����ő��Y�͖Y��Ă����ʎ蔠�����o���A�O�S�̉��ɘV�����̂ł����B���̌㉥�͐l�X�ɗ��Ȃǂ������Ă��܂������A�V�c�N�Ԃɂǂ����֗�������A����ɂ͈�ٍ̂̕��V�����c����Ă��邾���ł����B |
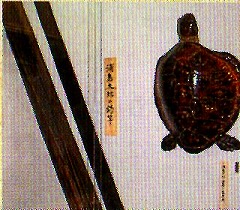 |
||||||||||||||
| �T�|�Q�Y�����Y�̓`�� | |||||||||||||||
| ����ȎR�̒��ɁA�Y�����Y�̓`��������Ȃ�āA������Ƃ����������Ƃł��邪�A�Y�����Y�����{�֍s�����Ƃ����b�́A��͂�C�݂̂��ƂŁA���̋��s�̓V�����ł���B���̊C�݂ŋT�������Ă��A���̋T�ɂ���āA���{�֍s�����̂ł��邪���{�ł̘b��A���{����A���ė���܂ł́A���Ƃ��b�ɂ���ʂ�ł���B�Ƃ��낪�A���Ă݂�ƁA�e�A�Z��͂������A�e���אl�N��l�Ƃ��Ēm���Ă���l�͂Ȃ��A�䂪�Ƃ������̂ŁA�����ɏZ�ނ��Ƃ��o�����A�̂̂��Ƃʼn������ǂ��ʂ����Ƃ��Ȃ��A���̎R�̒��ɂ��܂悢����ŗ����B ���̖ؑ]�H�̕��i�ɗ҂����Ƃ���Ȃ����߂��Ȃ���A�D���Ȓނ��������A���͑��l�ɒ��������{�̘b�������肵�ĕ�炵�ċ������Ƃ���A������̂��ƁA�t�b�Ǝv�������悤�ɁA�y�Y�ɂ�����Ă����ʎ蔠���J���Č�����A���ɎO�S�̂���������ɂȂ��Ă��܂��A�r�b�N�����ĊႪ���߂��B ������܂����Ƃ����̂ł�����Q�o�Ƃ����B �Ƃ���ŁA�����ł����ς�������킢�l���Ǝv���Ă������l�́A���̗L�l�ɋ����ċߊ��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�����ɏZ�ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�A���̍s���������Ă��܂����̂ł���B ���̐Ղ�����Ɨ��{����������Ă����ٍ��V�̑������i���������̂ŁA��������K�ɔ[�ߎ������ĂĂ��̕����Ƃނ�����Ƃ����B����S�N�O�̂��Ƃł���B���̐Q�o�R�Ր쎛�����̎n�܂�ł���B |
 �ٍ����i������N�Č��j |
||||||||||||||
| �U�Q�o�m���ٓ̕V���� | |||||||||||||||
| �ނ����O��̍��|��S�Y���Ƃ����Ƃ���ɁA���]�Ȃɂ����Ƃ����̎傪�Z��ł��܂����B���̐l�ɑ��Y�Ƃ�Ԏq�������܂����B�Y���̗̎�̎q���ł��̂ł݂ȉY�����Y�ƌĂт܂����B������A�C��Œނ�����Ă������Y�́A��C�̑傫�ȋT��ނ肠���܂����B�����̂��̂��T���E�����Ƃ��܂������A���Y���悭�悭�݂�ƁA���ʂ̋T�Ƃ������ČܐF�̎�������ǂ�A�b���ɔ��T�̕��������܂��B�E���̂���߂����āA�T���C�֕����Ă��܂����B �@�l�ւ��ǂ������Y���ƂɋA�낤�Ƃ���ƁA���т̂��������l�̔���������������Ă��Ă��Ȃ����Ƃ����B���Y�͖����݂Ă���悤�ȋC�����ł��Ă䂭�ƁA�₪�Ďl�ܒ�����̂Ƃ���ɁA�ꂩ�܂��̗��h�Ȍ�a������܂����B���Y�������Ă����͂ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ȕ��̂��Z�܂��ł����Ɛq�˂܂��Ə����́A����ꂱ���퐢�̍��̗��{��ł���Ɠ����āA��̒��ֈē����܂����B �@���{�ɂ́A�������A�吨�̉Ɨ������ƁA���Y�̗���̂�҂��Ă��܂����B��킽���͂����̑剤�ł���B���O���P�������Ă��ꂽ���炪����������A�������V��ł����悤�ɣ�ƔO�̂����������A�����A�R�C�̒��������ĂȂ��Ă���܂��� �@�����̂��̂��Y��ėV��ł������Y�́A������{�̐����ق̂��ɕ������Ă���̂��A�Y��Ă����̋����v���o���� |
|||||||||||||||
| �V�V�c��n�̘Z�n�� | |||||||||||||||
| �Z�n���͏㏼�ň�ԌÂ��n�����܂ʼn���U�N�V���i�P�U�V�W�N�j�Ɍ�������܂����B�����҂̎��������ʂɒ����Ă��܂��B �E����� �@�@
|
|||||||||||||||
| �W�����_�� | |||||||||||||||
| �{�a�͍]�˒����̑�\�I�ȎГa���z�ŏ㏼���ł͈�ԌÂ��_�Ђł��B �ĔN�㌎��{�ɂ͖����̍��O�͂̐_�c�����Ƃ����l������`����ꂽ�|���炢�ƌĂ�鎂�q��������A�ɂ���ď㉉����܂��B �����̏����͂��ׂĎ��q��������{�ɂ͏\���̉��ڂ�����܂��B |
|||||||||||||||
| �X�ؑ]�X�ѓS���ƋS���S�� | |||||||||||||||
| �S���S���͑吳��N�ɓ����̒������㏼�w����؍ނ��ݎԗA�����邽�߂ɉ˂����܂����B�S����\�O�C�����[�g���g���X�\���Ŕ������S���̍|�ނ��g�p�����̉��͋������쏊���肪�������̂ł��B�v�͎O����\�v�B�����E�Z�t���܂ߏ��̏����Y�S���Ƃ����܂��B �S���̐����ŏ�����E������̋O���������ɉ�����͏��a�\�N�܌��̖ؑ]�X�ѓS���p���i�����Ō�̐X�ѓS���j�܂Ŋ��܂����B �Ő����̖ؑ]�X�ѓS���͖؍ނ����łȂ��l�╨���̗��ʂ��S���ؑ]�̑哮���ł����B���̌�̋S���S���͎ԓ����Ƃ��Ċ��p���꒷�N�ɂ킽���Ēn��̌�ʂ��x�������܂����B |
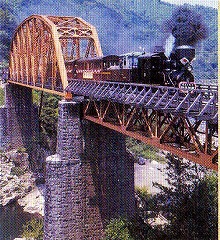 |
||||||||||||||
| �P�O���{���� | |||||||||||||||
| ���{�����͎��݂̉A�z�t�Œ����̉A�z���܍s���ɂ��V�̊ϑ���̍쐬�⎞�̑����⬒|�Ȃǂŋg�������Ă��܂����B ���͈��{�ۖ���͗�͂��������Ƃ��Ēm���锒�ρB ��q��������������ɐ��̂�m��ꂽ��� �u�������ΐq�˂��Ă݂�a��Ȃ�M���̐X�̂���݊��̗t�v �̉̂��r�݂���Ɉ��ށu�M���ȁv�̕���͗L���Ŗ��N�t�����{�_�Ђŕ�[�̕����������܂��B �����I���̒n�������ł���m����؋��͂���܂��V���Ɋւ��Ɠ��Ȑ����̉c�ݐ����̓Ɠ��̏�����ȂǕ�炵�̐����Ɍ����܂��B |
|||||||||||||||
| �P�P��{�_�� | |||||||||||||||
| �V�Ƒ�_�E�ɕ��O���i�����Ȃ��݂̂��Ɓj�E�ꓛ�j���i���������݂̂��Ɓj���Ր_���J���{�_�Ђł͖��N�����̒��{�̓y�j���E���j���ɗ�Ղ��J����܂��B �����̂��悻�O�Z�Z�˂����q�Ɏ�����A�ɂ���Ċe�˂̈����������s���A�����E�E�j���E�����Ȃǂ̎��q�_�y����[����܂��B �܂���{�_�Ђ͓ꕶ�l�̈�\���������ꂽ���Ƃł�����y���܂��B ���a�\��N�i�P�X�W�S�j���ŕ����q�a���Č��z�̍۔q�a�O��œꕶ���㑁���̉��^���y��ЂƐΊ킪��������܂����B�[���R���ň�\�����@����邱�Ƃ͔��ɋH�Ȃ��Ƃł��B |
|||||||||||||||
| �P�Q�А_�� | |||||||||||||||
| �Зl�Ɛe���܂��А_�Ђ͓V���N�ԁi�P�V�W�P�`�P�V�W�W�j���̍ޖؕ�s�E���X�쌹�����ؑ]�R��̈��S�Ƃ����ɓ����[����قɃP�K�⎖�̂�������������Č������ꂽ�Ɠ`�����܂��B �ЂƂ� ��ԑ匠���i�n���ؑ]�n���̎��_�j �M�c��_�{�i�����ؑ]�����߂Ă��������ˎ�̋��Z�n���É��ɂ���_�Ёj �V�Ƒ�_�i�ɐ��_�{��_��ؑ]��茣��j �O����_�i���C���O���h��{�ЂƂ���R�̐_�j ���V�{�i���t�E�D���̈��S����鐅�̐_�j ���w���܂��B �Ȃ��㏼�ޖؖ������J���Ă����А_�Ђł����������l�N�i�P�W�V�P�j�ޖؖ����̔p�~�����ɏ㏼���̒���z�K�_�Ђ̋����Ɉړ]����܂����B |
|||||||||||||||
| �P�R�|�P�������̂��P�l�̓`�� | |||||||||||||||
| �������̐l�̑O�ɒǂ��肩�瓦���邨�P�l�����ꂩ���܂��Ă����悤���肵�܂��������l�͌�������Ă����f��܂����B ����Ƃ��P�l�͏������o���Ă��������ƌ����܂��������l�͏������������グ�Ċ肢�͕����܂���ł����B �r���ɂ��ꂽ���P�l�͎R�H������������̂قƂ�ɐg���B�����ǂ���ɔ���������ɂ͑�ɐg�𓊂����̂ł����B �ȗ����̑�́u�B���v�ƌĂ�����K�͕P���J�������̂Ƃ���܂��B |
|||||||||||||||
| �P�R�|�Q ������� | |||||||||||||||
| �́A�킢�ɔs�ꂽ�����̗��l�̂��邨�P�l���ǎ肩�瓦���Ėؑ]�܂ł���Ă��܂����B�����ď㏼�ɂ����̐��e�ɐg���B���Ă��܂����B�Ƃ��낪�����ė���r���ɓ����܂𗎂Ƃ��ė��Ă��܂��܂����B�����ǎ肪�����āA���̑�ɂ��P�l�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��A�����肻���ɂȂ������P�l�́A������g�𓊂��܂����B���ꂩ�炱�̑�́u�������v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B �u�������v�Ƃ��������͂��������܂��B���R������́A���̑ꂪ�����ȎR�ɉB��Ă��āA��̔������p�͌����Ȃ��B�ꂪ�B��Ă���̂ŁA�u�������v�Ƃ����Ă���B |
|||||||||||||||
| �P�S�|�P����1 | |||||||||||||||
| �ؑ]�H�͂��ׂĎR�A�ׂ������R�ƒJ��D���悤�ɑ����Ă���B ���̓����ɂ��ڂ낪����ǂ����B �钆�ɐl���������ƁA���ڂ�͂����ƌ�납����ė��� �u���낤�A���낤�B�v �Ɣ߂����ɐ��������A�тނ������Ȏ���̂��A���Ԃ��낤�Ƃ���̂��B �����Ă��̐l�͐���������ꂽ�����ō����ʂ������A�������܂œ����̂Ăē����Ă��܂��̂������B ���ɑ��̏O���������̂́A�H�ו����^��ł��鉪�M�i���j�����Ȃ��Ȃ������Ƃ��B ����Ȃ�����A�����S�_�������A���邩��ɋ������Ȏ����ʂ肩�������B�����Ă��ڂ�̘b���� �u�Ȃ�A���Ԃ��낤�Ƃ��邨�������ƁB�܂�Ŏq�����܂�����ȁB�َ҂��ގ����Ă�낤�B�v �ƌ������B ���̏O�͑��тŁA��y�������A��ɂ��ĂȂ����B ��ɂȂ�ƁA���͂����ďo�����čs�����B ����肳���Ɛ������͎₵���A�₪�ĕ��̉��ɂ܂����Ă������� �u���낤�A���낤�B�v �Ɣ߂����ɌĂԐ������������B ���͂Ԃ�Ԃ��Ɛg�k�������āA�Ȃ����s�����ƁA���x�͂������� �u���낤�A���낤�B�v �Ɩтނ������Ȏ���̂��Ă��ꂩ�������B �u���������B�v ���͖ڂ��ނ��āA�������ɐ�����B����Ɗm���Ȏ育�����A �u�����[�B�v �Ɩ������̂������A�傫�ȃn���l�Y�~�̉��������A�������Ɨ����ė����B ���A�������́A�S�z������ďW�܂������̏O�ɁA �u��͂��͂��͂��A�܂�ł��킢���Ȃ���������B�꓁�̂��Ƃɐ�̂Ăė����킢�B�����̒����ɍs���Ă݂邪�悢�B����ɂ��Ă��A���܂łɂ���Ȃ��̂�ގ�����҂����Ȃ������Ƃ́B�v �ƁA��В���Řb�����B ���̒��A���l�Ǝ����s���Ă݂�ƁA���Ă���̂͂Ȃ�ƁA�傫�ȏ��̖̎}�ł������B ���͂��������Ɠ�������A���l�͂�������B ���ɗ����̂͗t���B�傫�ȓ�ؓn��̓S�C�������A���ł��A��˂̎R�̎�A�u�傤��݁v��ގ����ė����Ƃ����B�N�}�̖є�ɁA���������̂悤�ȑ��B �u����Ȃ�A�R�̎�����Ȃ��܂��Ɂv �ƁA���̂��イ�͂��̂����������B ��ɂȂ�ƁA�t�͗E��ŏo�����čs�����B ���߂��A����肳���̕��̉��ɂ܂����� �u���낤�A���낤�B�v �ƁA�߂����ɌĂԐ� �����|���ĉ䖝�ł��Ȃ��B�t�͐U��������܁A�������ȋC�z�Ɍ������� �u�_�{�[���v �ƁA�ꔭ�B���̎��͂₭�A�������ȉe���ڂ̑O�ɂƂт����A�тނ������Ȏ肪�������ƓS�C�����������B �t�͎d���Ȃ��A�R�����ʂ��A�߂����₽��Ɛ�����B �Ȃɂ��A����͉������A���Ă����Ă��P���������Ă���B�i���͖閾���߂��܂ő����A�t�͔������B �������߂��ɂȂ��āA�悭�悭����A�܂��̖݂��A�߂��Ⴍ����ɐ�|����Ă��邾���������B ���ɗ����͎̂R�����B����̘b���� �u�킵�͍������܂���āA�L�c�l�c�L���́A�͂��a���̂��Ȃ����Ƃ�B�킵�̔O�͂ł����Ƃ���Ƃ���ގ����Ă��悤�B�v �ƁA�o�����čs�����B ���̏O�́A���x�����O�x�ڂ̐����Ǝv�����B �R�����������オ���čs�����ƁA �u�u�͂����A�͂����A�فA�فA�فA�v �ƁA�ӂ��낤���Ȃ����B �u������A����A����A���A���A���v �ƁA�̗t���������B �����C���������Ďd�����Ȃ��B�R���͎����Ă����z���L���������Â��ɁA �u�����[�A�����[�A�Ԃ��A�Ԃ��A�Ԃ����B�v �Ɩ炵���B �ǂł����z���L�̉��ɁA�R�̏b���т����肵���B�R�̏������������Ɣ�ї������B�b�����́A�����A�����ƁA�R�������o��A���������́A������A������Ɩ݂ɓ˂����B �������A�̐S�̂���́A�p�������Ȃ������B�������������Ȃ������B �R���́A���������A������������A���֖߂�ƁA�[�ċz������������B�����đ��l�����ɁA �u�������v���B�킵�̔O�͂ŁA����͊��S�ɕ������߂�ꂽ�B�킵�̑O�Ɏp�������Ȃ������B�v �ƁA�����āA����̋�������������炤�Ƃ��̂܂ܗ��������Ă��܂����B �������A���̔ӂ���A��������͏o���B ���v�Ǝv���āA�H�ו����^�тɍs��������������A���M�͑���܂�A�ו��͒J�֗����Ă��܂����B �Ƃ���ŁA���̊X���������Ɨ��ꂽ�R�ɁA�����˔k������ǂ����B ��������ŁA����Ă�V�̔k���܂ɂ��������ł����B���։łɂ����������u���������܂ꂽ�B�v�ƒm�点���͂����̂��B �����܂́A�̂��䂷���đ��сA���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ�A�����ɖ��̗��ւƏo�����čs�����B �Ƃ��낪�A�����ɂ��������鍠�A�����Ƃ��Ղ�ƕ��Ă��܂����B �u�q�����������ꂽ���A�������Ȃ��B�v �����܂͏������������ɂ���̂��Ƃ���������Y��A�ǂ�ǂ�����čs�����B ���炭�s���ƁA �u���낤�A���낤�B�v �Ɣ߂����ɌĂԐ����A���ׂ��������ė����B ���̂��Ƃœ��������ς��̔k���܂ɂ́A���̐����A�e�ɊÂ����A�Ԏq�̐��ɕ��������B���̋������ɂ��v��ꂽ�B |
|||||||||||||||
| �тނ������Ȏ肪���ꂩ����ƁA�܂�ő��ł����Ԃ��悤�A��������Ƃ�������Ԃ��Ă��܂����B �������̂͂��낾�B�����Ƃ��Ă��Ⴄ�B�Q�Ăē����悤�Ƃ������Ă݂��B����ǂ�������Ƃ��Ԃ�ꂽ�����܂̍L���w���́A�ӂ���Ə_�炩�������B������ƒg���݂��`����ė����B �o���ǂ��s�� �O���傤���邳���� �ł̍ݏ��� �������� �悢�悢�悢�́@�悢�悢�悢�p �����k�l�̌����瑷�����₷�̐������ꂽ�B �_�����тɕ�܂ꂽ���낪�A�����Ɏv���ė����̂��B ���������������S���Ă��܂��āA����������A�����疰���Ă��܂����B �閾���߂��A�����߂��A������̒��ɁA��u�����A�������_�X�ƌ����ė����B �u���炟�A�Ƃ��Ⴂ�������܂������B�w���ɋ���̂͂��낾�����Ȃ����B�w������x�ڂ��o�܂��B�ق��̐l�ɂ߂���������A�Ђǂ��ڂɑ������B����������Ƃ��Ԃ��Ă��������悩�炷�B�v �閾���̌��ł悭�悭����A�q���ʂ�����C�A���傱��Ƃ���Ă���B |
 |
||||||||||||||
| �q���ʂ��́A���炭�����Ƃ����܂̔w���ɂ������܂��Ă������A�����Ƃ��ꂽ���̂��䖝���āA�҂傱��Ɣ�э~�肽�B �u����A�܂��A���܂��́A����i���̑O�j�t�ɐe�������ꂽ�����ʂ�����Ȃ����B�����A�����A����ۂǂ��ꂽ��������Ɂc�c�R�̂��Ƃ́A�R�̂���łȂ���킩���łȂ��[�B�v �q���ʂ��́A�����Ƃ����܂����Ă������₪�āA�����A�����Ɩ݂ɓ����čs�����B �u���炟���A�Ƃ���Ă�V�����A�������ŁA�C�����̂��������}���邱�Ƃ��ł����B����ő����A�����q�Ɉ����낤�B�����͂��A�͂��A�͂��B�v �閾���̖ؑ]�̎R�X�ɁA�����˔k����̖��邢�����������܂��Ă������B ���ꂩ��ؑ]�̓��ɁA����͏o�Ȃ��Ȃ����ƁB�i�㏼���㏼�j |
|||||||||||||||
| �P�S�|�Q����2 | |||||||||||||||
| �@�́A����ɂʂ���R���Ɂu����v���o���B �@����́A��ɂȂ�Ɠ���ʂ�l�̌�납��A�u����A����v�ƁA���̔߂����ɐ��������A�тނ������Ȏ���̂��A�l�̔w���ɂ��Ԃ��낤�Ƃ���B �@���������̐l�́A���������������œ����o���������ʂ����B �@�N�������킪���āA���̂������̎R����ʂ�l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �@�Ƃ��낪�A����ӁA�łɂ��ꂽ���̉Ƃ���A�q�������܂ꂽ�Ƃ����m�点���āA���k���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ����B�B �u�������ɁA���猩�Ă��v �@�铹���Ȃɂ����炷���A���k����Ă�Ă�ƎR��������A����̖��̍ݏ��ɏo�����čs�����B �@����ƁA�ォ��u����A����v�̐�������B �@����́A���ꂩ���ɂ������̋������ɕ��������B �@�u���肽�����A����v �@���k���������߂�ƁA���Ԃ����Ă�������̎���A�������ɂ�����Ƃ��ނƁA�w���ɂ҂����肭�������B �@�т����肵���̂́A���낾�����B �@���܂Łu����v�Ƃ�����ł͂������A�l�̔w���ɂ��Ԃ���̂́A���ꂪ���߂Ă̂��Ƃ������̂��B�Ȃ�Ƃ������o�����ƁA�㑫�ł��k����̔w�������ς��Ă݂����A�Ȃɂ�������������般���Ă���B���̂����ɁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ����k����̔w���ɁA�Ȃɂ�炤��Ƃ��Ă����̂��B �@�₪�āA��������疾�������Ė��̉Ƃ������Ă����B �@�����ł��k����A�w���̂�����Ђ傢�Ƃ��낵���B �@����Ώ������ނ��Ȃ������B �u�����A����ł���̂���������ɁA�������肨���Ă�����ɂȂ��v �@�ނ��Ȃ͖����ڂ��������Ă������A�₪�ē��̉��֏����čs�����B �@���ꂩ��A����͏o�Ȃ��Ȃ����ƁB |
|||||||||||||||
| �P�T�|�P�������R�Ɩ��n | |||||||||||||||
| �������R�ƌ���ꂽ�A�ؑ]�`���͕��ƂƐ키�O�A�ؑ]�J�̂Ƃ���ǂ���ɔn������A�ǂ��n����ĂẮA�����Ɨ����P�����Ă������B �`���͓��ɎR�ɂł���ɂł��A��ɋ����n�̌P���ɗ͂����Ă������B ����ȋ`������������A�����̏��n�́A���ɑ��̋����A�ǂ��n��I��ł����B ���ł���ԋC�ɓ���̔n�́A�l�Ԃ̌��t���킩��A�ǂ�Ȍ��������ł��A�炭�炭�z����Ƃ������n�ł������B �`�������̔n�ɂ܂�����A�傺���̉Ɨ���b��O���]���A�ؑ]�J���܂��Ƌ삯��邳�܂́A�܂��ƂɌ����������Ƃ����B ������A���̖��n�ɂ܂�����A�n�̌P���ɗ����`���́A�V�ɒʂ肩�������B �̂̎V�́A���肽������ɂ��������A�R���̓r�ꂽ���ɒӂ�A���Â�ŕ҂������A����͊댯�ȏ��������B �R�̉��ɂ͖ؑ]�삪�Ƃ��Ƃ��Ɨ���Ă���B �`���͔n�̏�ŋ���A���ӂ��Ɍ������B �u�F�̎҂ǂ�����A�킵�͂ЂƂ��̎V���A��C�ɔ��ł݂悤�Ǝv���B �Ɨ������́u����v�Ƌ����̐����グ���B�������N��l�Ƃ��ĂƂ߂�҂͂��Ȃ��B ����́A���S�C�ŁA�����o�������ֈ����Ȃ��`���̐��i��N�����悭�m���Ă������炾�B �`���͋����Ă���Ɨ������ӂ��Ɍ��n���ƁA�n�����������点���B�e�݂����邽�߂��B �`���͂��̒f�R�����\�O�ԂƖڂő������B |
|||||||||||||||
| �u���\�O�Ԕ�ׂ��v �J�b�J�b�J�b�J�b�A�n�͐����悭����o�����B�Ō�̊���ΉԂ��U�炵�ĂЂ��߂������A�Ђ��Ɣ�B�Ƃ��낪�ǂ��������Ƃ��A������Ԃقǂ̏��ŁA�ؑ]��ɂ܂��������܂ɗ����Ă��܂����B �n�͐쌴�̊�ɑ̂��ƂԂ���A����f���Ď��B��ɏ���Ă����`���͉^�悭�����菝�����ŏ��������B ���͂��̎V�A���\�܊Ԃ������̂��`�����ԈႦ�āw���\�O�ԂƂׁx�ƌ����Ă��܂����̂��B |
 |
||||||||||||||
| ���̂��Ƃ�m��ƁA�`���͑嗱�ȗ܂����ڂ��A �u�킵�����������B�E�E�E�E�E����ɂ��Ă��킵�̊Ԉ�������߂ł������Ɏ���Ď���ł��܂������܂��́A�Ȃ�Ƃ���䂢���̂��B���������B���������B�E�E�E�E�E�x �ƒj�����ɋ������B �����Ă���܂��Ă��C�̍ς܂ʋ`���́A���n�������Ɏv���A���ŗ��h�Ȋω��l����点�A�߂��̋u�ɂ��������āA���n���˂�ɒ������B ���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A�����グ���`���́A���Ƃ̑�R�����X�Ƒł��j��A�����̏o��悤�Ȑ����ŋ��s�ɍU�߂̂ڂ�V��������Ă��܂����B �l�X�͂��̂�ŁA�����̂悢�`���̂��Ƃ����R�ƌĂB �������`���̓��ӂȎ����͂��������͑����Ȃ������B���������̋`�o�̌R�ɔs��A���Â����Ƃ������ŁA�D�c�ɔn���͂܂�A�����Ȃ��Ȃ������������Ƃ��Ă��܂����B ���������Ă���l�N�A�`���O�\��̂��Ƃł���B �u���̎V�ŖS�������A���n�ɏ���Ă���������A�D�c�ɂȂ����Ƃ��Ȃ����������̂��B����Ȉ���Ȏ��ɕ��͂��Ȃ��������̂��B�v �u���Ƃ��A��ɕ����Ă��A�����Ɩؑ]�܂œ����������Ă��ꂽ���̂��v �ƁA�c�O�������Ƃ����B �������`�����c�������̌B�|�̊ω��l�́A�ؑ]�n�̎��_�ƂȂ�A���Q��ɗ���l�łɂ�������Ƃ����B�i�㏼���V�j |
|||||||||||||||
| �P�T�|�Q�`���Ɩ��n | |||||||||||||||
| �@�ؑ]�`���̈��n�́A�r�̏�v�ȋ����n�ŁA���̏�l�̌��t������Ƃ����A�����ւ����n�������B �@ ������̂��ƁA���̖��n�ɂ܂�����ؑ]��̐�ǂɂ������������`���́A���������Ί݂Ƃ̕���ڑ����A�u���\�O�ԂƂׁv�Ɩ��߂����B �@���n�͍������ȂȂ��A�S��̏������炪�����Ƌr�ɗ͂����߁A�Ȃ�̂��߂炢���Ȃ��J�Ԃ��ƂB �@���A�ǂ��������Ƃ��A�Ί݂܂œ�Ԃ��c���ؑ]��ɗ����Ă��܂����B �@�`���́A�^�悭�����������A���͂��̒J�Ԏ��\�܊ԂƂ���A�`�����ڑ��̌��A���n�͖�����ꂽ�܂��\�O���Ƃі��𗎂Ƃ��Ă��܂����̂��B �@�`���͐[�����n�����݁A���̊ω���������Ђ����ĂĖ��n�̗���Ȃ����߂��B �@���ꂩ��A�܂��Ȃ��`���͕��������A���ɍU�ߏオ�舮���R�ؑ]�`���Ƃ�����悤�ɂȂ����B �@���A��������̊ԁA���������̋`�o�̌R�ɔs��A���Ã����̏��c�̒��n���͂܂荞�ݓ����Ȃ��Ȃ����Ƃ���֗����Ƃ�ł��Ė��O�̐펀�B �@�����`���������ؑ]�̐l�����́A���̖��n�ɏ���Ă�����A����Ȃ��Ƃɂ��Ȃ�Ȃ������낤�ɂƁA�傢�Ɏc�O�������Ƃ����B �@�ؑ]�ł́A����̊ێR�ω��A���ؑ]�̓c�̏�ω��A�{���̊�o�ω�����ɂ��̏㏼�̌B�|�ω����l��n���ω��ƌĂ�ł���B |
|||||||||||||||
| 16���n�̂͂Ȃ� | |||||||||||||||
| �ؑ]�̖����u�����͂��v�͐̂͂ӂ��̂�ŋ����Ȃ��ł������Ƃ����B �@������A���́u�����͂��v�𖼔n���ʂ����B���̔n�͂ƂĂ��肱���Ȕn�Ŏ�l���u��Ԕ�ׁv�ƌ����ƁA�ꐡ�̂��邢���Ȃ���Ԕ�сA���ꂪ�ǂ�Ȃɒ��������ł��҂�����Ɛ��m�ɔ�B �@�u�����͂��v�ɂ����������A��l���ؑ\���������ׂƌ������B�n�͎�l�̌������ʂ肿���Ɣ�̂����A��l������������ď��Ȃ����������߂ɁA�ؑ]��ɗ����Ď���ł��܂����B���킢�����Ɏv�������l�B�́A���̔n�ׂ̈ɂ��n�����܂��������J�����B���ꂩ��́u�����͂��v��ʂ�n�͖ؑ]��ɗ����Ă������Ď��ʂ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B �@���̂��n�����܂̂������ŁA�ǂ�ȑ傫�ȉו��ƈꏏ�ɗ����Ă��n�����͏��������Ƃ�����B |
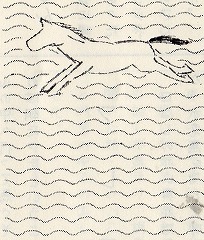 |
||||||||||||||
| �P7�n�������q | |||||||||||||||
| �@�]�ˎ���A�ؑ]�X���ɂ����ւς��Ȕn���������B �@���ʁA�n���Ɣn�̊W�́A�n������l�Ŕn�͏]�A�n���g���Ă���ԕ��ɂ���B �@�����Ƃ����A�n�������E�����n���������B������n�́A�n���̂����Ȃ�Ɏg���邵���Ȃ������B �@�Ƃ��낪�A�����q�Ɣn�̏ꍇ�A�܂�����������B �@�n����l�ő����q���]�B �@�܂�A���x�G�͂����A�n�̉��Ɏ����������Ă����̂��B �@������A�ו���n�̔w�ɂ���Ƃ����A �u�e���A���܂˂����^�т��B����ڂ����Ă�����Ȃ�����B�v �Ƃ���܂�A�O���̔n�ɓ��ׂ̉����ς܂Ȃ������B �@�����āA�댯�ȎR���ɂ���������ƁA�n�̎��������A �u�e���A�C�����Ă���������B�킵���J�ɗ�������A�����Ԃ��Ă�����Ȃ����v �ƁA�܂�Ŏ�l���C�Â����悤�ɘb���������B �@�n�����������Ɖבʂ��킯�Ď������w�����A�̂ǂ����킭�ƁA�܂��n�ɐ������܂����B �@������A���X�ŋx���A�����q�͂���݂��O�������B �@�����āA�O���̔n�Ɉ�ÂH�ׂ����Ȃ���A �u�����e���A����Ō��C�����Ă���������v �ƁA�����͈���H�ׂȂ������B ��������ė��l���������B �u���������A���O�����ǂ������e���Ȃ��v �@�����q�͏��ē������B �u�����������܂��Ă���܂��B�킵��n�̂������ŕ�炵�Ă���ҁA�n���e���ł̂��Ăǂ����܂��B �@������ė��l�́A�[���S��ł��ꂽ�Ƃ����B |
|||||||||||||||
| �P8�P���̂��� | |||||||||||||||
| �ނ�������悤�ȐV�̖ؑ]�H���A�l�ڂ�������Ă��鑫���}�����Ă���������P�N���������B �P�́A���s���G�̒ǂ����A�����ė����̂��B���̕ւ�ɕ����A��������l�̒�A��N���ؑ]�̎R���ɉB��Ă���Ƃ����B����������ЂƂ̂����ɁA����ƐQ�o�m���ӂ�܂ł��ǂ蒅�����̂��B �ǂ���̋߂����Ƃ�m�����P�́A��������ؑ]��ɂ���������������̂ڂ����B�����ē��̕����ɂ������A����ʂɐ����閃�������B �q�Ȃ�ƋC�����悭�L�т������낤�B���̒��Ȃ�p�����������Ƃ��ł��悤�B�łȂ��Ƃ����̔�ꂽ�̂��ꎞ�����ł��x�߂邱�Ƃ��ł��悤�B�r �P�͔��œ������l�ɗ��B �u�������A���̖����̋���݂��ĉ������B�ЂƋx�݂ł���悢�̂ł�����B�v ���l�́A���̔������痧���ƁA���т��Ă���l�q�ɖڂ����������B�����Đ[���킯������̂��낤�Ǝv���A������荇���ɂȂ邱�Ƃ�����A���݂�f�����B �u�Ȃ��A����l���B���Ă������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł������܂��傤�B��Ȃ������������B���N����͂����Ƃ��̂�����ɂ͖��͈炽�Ȃ��ł��傤�B�v �P�͔߂����ɂԂ₭�ƁA��ꂽ�������������āA�R����čs�����B�Œ��i�����イ�j�̋߂��܂ŗ������A�P�͂ӂƂ̂ǂ��ȉ̐������ɂ����B����ΎR�����̓c�œc�A�������Ă���̂��B �o���ׂ͍����A���ˊԂ͍L�� �}�̂Ђ������ԊԂ��p �@���ɂ��a�₩�ŁA�ЂȂт��̐����B�P�͒ǂ��Ă̂��Ƃ��Y�ꕷ���������B���̋��낵���s�̍���̂��Ƃ��Y�ꕷ�������Ă����B ���炭���Y��ĕ��������Ă����P�́A�}�ɂ͂�͂�Ɨ܂����ڂ� �u���͂�A�����邱�Ƃ͂ł��ʂł��낤�B���̓c�A���̂������Ƃ��A��Ԃ̍K���ł������B�����A���܂ł��A���̉̂̂悤�ȐS�ł������B�v �ƁA�Ԃ₫�A�܂������͂��߂��B ���炭�R���i�ނƁA���͍s���~�܂�ɂȂ�A�傫�ȕ��ɏo���B�P�͊�̏�ɋx�݂ق��Ƒ��������B �ؗ����[���A������ꂩ�����Ă����B�������j�����A�A�𗧂Ăė���鐅����������ɂ����܂��Ă����B �P�͂ӂƁA�₩���ɐ����Ă���A�X�Q�ɖڂ��Ƃ߂�ƁA��������A��������������̓c�A���̂܂˂����Ă݂��B �o�Y�ꑐ�Ȃ��{�ق��� �A���Ĉ�ĂČ��ĖY��p �g���S�����ʂĂ��P�ɂ́A�������̖]�݂��Ȃ������B�B��S�ɂ������A�܂˂邱�Ƃ��ŏ�̍K���������B ����ǂ���͓��̏�܂ōs�������A�P�������邱�Ƃ��ł��������Ԃ��ė����B�₪�ĉ��\�ڂ����낤���Ǝv����q�m�L�̑�̖��̂قƂ�ŁA�P�̂��̂Ǝv����ɂ����܁A���ፁ���������B�P�̋߂����Ƃ�m�����ǎ�͂��������T�������A�������c�A�̂����ɂ����B�s�v�c�Ɏv���߂Â��Č���ƁA�P����̏�œc�A���̂܂˂����Ă���ł͂Ȃ����B �u�������v �u�P���������v �ƌ��X�ɋ��ԂƂ���Ƌ삯�o�����B |
|||||||||||||||
| �Ƃ��낪�P�́A����������ĂȂ������B�������Ɨ����オ��ƁA�ؑ]�̎R�X�ɂ����݂Ƃ���悤�Ȕ��������ŁA�Ō�̈�߂��̂����B �u�Y�ꑐ�����A�A���Ă݂͂��� ���ƂɎv���́@�����c��v �ǂ���͎v�킸�����~�܂�A���̙z�Ƃ����p�Ɍ��������B �̂��I������P�́A�����ƕ��g�����ǂ点���B |
 |
||||||||||||||
| ���̂��Ƃ������Ă���A���̕��͕P���ƌĂ��悤�ɂȂ����B���l�����́A���̕P�N�������Ɏv���A���̂قƂ�ɕP�{�����ĕP���˂�ɂƂނ�����B �܂��A�P���B���Ă���Ȃ��������̕��ł͖����炽�Ȃ��Ȃ�A�P�̂��ፁ�̂��ڂꂽ��́A���ፁ��ƌĂ��悤�ɂȂ����B�����Ă��̓c�A�̂́A����ȕP���v���A���̎����ӂ���Ɖ̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƁB�i�㏼���@���q�j |
|||||||||||||||
| �P9�|�P�P���P | |||||||||||||||
| �@�́A�����ƌ������������Ă������A���s������Z���o�Ėؑ]�H�𗷂��ė����P�������B�P�́A�F����̐킢�Ŕs�ꓦ�����������������ˁA�悤�₭�����܂ŗ����̂����A�ؑ]�H�͐V�A�c�A���̍��������B �@���A����̗��A��������ɒ������Ƃ���ŁA�P�͒ǎ�Ɍ������Ă��܂����B �@���́A��ʂɐ����閃���ŁA�P�͑��l�ɗ��݁A�g���ɉB�����Ƃ����B �@�������A���l�͕P�����l�ł��邱�Ƃ�m��ƁA��������A�P���������Ă͂���Ȃ������B�������Ȃ��P�́A�ɂޑ�����������A�R���𐼂ւƋ}�����B �@���q�̓����z���鍠�ɂ́A�[�z�͌�Ԃ̎R�����ɒ��݁A���蓹�̂Ƃ��������ɂ́A�J��̐[�������������B �@���̎��A���̕�����ǎ�̎҂ǂ��̂̐����������A�P�ɂ��͂ⓦ����͂Ȃ������B �@�P�́A���̓r���Ō��������������̓c�A���̂��v���o���A�߂��ɐ����Ă����X�Q�����A��̏�ʼn̂��Ȃ���A�c�A���̂܂˂��͂��߂��B �@�@�@�@�@�@���͂��܂����@���˂܂͍L�� �@�@�@�@�@�@�}�̂Ђ������@���ԊԂ� �@�@�@�@�@�@�Y�ꑐ�Ȃ�@�@��{�ق��� �@�@�@�@�@�@�A���Ĉ�Ăā@���ĖY���� �@�@�@�@�@�@�Y�ꑐ�����@�@�A���Ă݂͂��� �@�@�@�@�@�@���ƂɎv���́@�����̂��� �@����邷�ׂ̂܂������Ȃ��Ȃ������A���߂č����̎v���o�ɁA�c�A���̂Ȃlĵ��Ă݂��̂ł���B �@���́A���������̂����܂����Ƃ��Ȃ��A�P�͊ቺ�̟��Ɏ���̎Ⴂ���������Ă��܂����B���̌�A�R�X�����ɐ��܂�[���ǂ��A���̟��̐��炩�Ȑ��̒��ɕP������A�c�A���̂ȂǕ�������̂ŁA���l�͂��̟����u�P���v�Ɩ��Â��A���̂قƂ�ɎЂ����āA�˂�ɕP�̗���J�����Ƃ����B �@���A���ꂩ�瓇�ł́A�����炽�Ȃ��Ȃ����Ƃ������B |
|||||||||||||||
| �P�X�|�Q�P�� �Q | |||||||||||||||
| �@���Ƃ̗��l�Őg�Ȃ�̗��h�Ȃ��P�l���ؑ]��Â����ɏ㏼�܂œ����Ă����B�u���R�����s�������Ƃ��܂��Ă��܂����낤�v�ƒ��R�����͂���Ėؑ]��̎x���Â����ɎR�̉��ւƓ����Ă����B���Ƃ��������܂ŗ��Ĕw�̍��������������ς��ɂ͂��Ă���̂����āA��ǎd�������Ă������S������ɁA�u���͒ǂ��Ă��܂��B���͔w���Ⴂ�̂ł��̖��̒��ɉB�ꂽ��A�����炸�ɂ��݂܂��B���Ȃ����ɂ͌����Ė��f�͂����܂���B�������̖��̒��ɉB��邱�Ƃ������Ă��������B�v�Ɨ��݂܂����B���������̂��S������͌����邱�Ƃ�����āA���P�l�̗��݂��܂���ł����B���P�l�͔߂��݁A���̐l������ŁA�u�����͂������͂ł��Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�v�ƌ��������܂����B���N��R�̖����ł��Ă������̕����́A��������薃�͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B �@���P�l�͎R�̉��ւƓ����A���x�͍��q�֗��܂����B���q�ŔN�V�������ꂳ���P�l���Ăю~�߂܂����B���P�l�͂��ꂳ��ɖ��b���܂����B�u���킢�����Ɂv�Ƃ��ꂳ��͂��P�l�������̉ƂɘA��čs���A���т�H�ׂ�������A�����ւ�e�ɂ��Ă���܂��� ���̂��ꂳ��͂��ŋ߂�������l�̑�����a�C���Ȃ����Ă��܂�������ł����B���݂������ꂳ���ɕP�ɂ₳�������Ă��ꂽ�̂ł��B �@���ꂳ��Ɗy�����ЂƎ����߂������̂����̊ԁA�ǎ肪���ł��P�l�̂��Ƃ��āA�ǂ������Ă��܂����B�u��������ȂƂ���ɂ��Ă͌������Ă��܂��B�v�Ƃ��P�l�������悤�Ƃ��������ꂳ�u������Ƒ҂��Ȃ����B����ȂȂ�ł͎R���͕����A�l�̖ڂɂ��t���₷���B�v�Ƃ����đ����̒��Ă�����ǒ����o���Ă���܂����B���P�l�͂��ꂳ��ɒ��J�ɂ���������ĉƂ��o�܂����B�����ԕ����Ă苴�̏��܂ŗ��܂����B�u�����܂ł͒ǂ�������܂��v�Ƒ傫�Ȑ̏�ŋx��ŁA�̂��̂��Ă��܂����B����Ƒ吨�̑������������A�����Ƃ����Ԃɂ��������܂Œǎ肪�����Ă��܂����B�u��������ȏ�͓������܂��v�Ǝv���A�������̏ォ�炫�ꂢ�ɐ��݂�������̒��ɐg�𓊂��Ď���ł��܂��܂����B���ꂩ�炱���́u�P���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B |
 |
||||||||||||||
| 20 ������̓`���@�P���̔ߘb | |||||||||||||||
| ���q�Ȑm���̌�q�P�{�͉F���̐킢�œ��������������ؑ]�J�ɋ��邱�Ƃ����A�ǎ�̓�����킵�Ȃ��狞�����l����Ă��܂����B���鎞�͑��l�ɂ����܂��܂����鎞�͌������ꂽ���l�Ɍ�������Ȃ���K���ɓ���������ɏ���̗��ŕP�͌������Ă��܂��܂��B�P�̎����܂��l�����ǎ�ɚk���t�����Ă��܂����̂ł��B���悢�擹���ʂāA�[������O�ɓ����邷�ׂ��Ȃ������P�́A��������r���Ō������Ɏ����c�����i���v���o���A���������Ƒ����v���A�c�A���̐^�������Ȃ���c�A���̂��S���܂��B �����Ă��̐��炩�Ȑ��������邩�����Ȃ������Ɏ��畣�ɐg�𓊂��A�Ⴂ�����������̂ł����B�^�g�̉͌��T�c�L���炭�t�̗[��ꎞ�̂��Ƃł����B |
 |
||||||||||||||
| �Q1�ς����蟺�̎� | |||||||||||||||
| �@ �č��n��ł�����[���u�ς������蟺�v�ŁA��҂������ő����������Ԃ��āA���̏`�ɓ������݁A��x�ɑ�R�̋����Ƃ낤�Ƃ��Ă����B �@�����ցA��l�̔N�V�������̖V���ʂ肩����A �u�ނ�ŋ����Ƃ�́A�������܂���Ēނ��邩��d���Ȃ��Ƃ��āA�ŏ`�ɗ������߂A���܂���Ȃ������݂�Ȏ���ł��܂��B�ǂ����A����Ȃނ������Ƃ́A��߂ɂ��Ă�������v �@�ƌ������B �@���A���������̊y���݁A��߂���͂����Ȃ��B��҂����́A�V����̗��݂��ƂȂǑ���ɂ��Ȃ������B �@�V����́A�߂���������ė����������B �@���ꂩ��V����́A�ꌬ�̔_�Ƃɗ������A�܂���т����������ɂȂ����B �@�����āA���̔_�Ƃɂ��ƁA�ŏ����ɂȂ�z�E�Z���J�����]���ꂽ�B �@���A���̉Ƃɂ͂Ȃ��ƒf����ƁA�܂��߂����������A�ǂ��ւƂ��Ȃ����������čs�����B �@����A��҂����͂Ƃ����Ί�X�Ƃ��āA�p�ӂ����ŏ`���ǂԂǂԂƁu�ς������蟺�v�ւƗ������B����ƁA�݂�݂邤���ɋ��������A���������݂��A�������ς��ɕ����オ���Ă����B �@���̂����A�Ō�ɕ����яオ�����⋛�����āA��҂����͊̂��Ԃ����B �@����́A����܂Ō������Ƃ��Ȃ���⋛�ŁA�ЂƂ�ł͕������������Ȃ��قǑ傫�������B �@��҂����́A�����������̑�⋛�𗿗����āA������邱�Ƃɂ����B �@�����ŁA�����قǖV������������ƂɏW�܂藿�����Ă��炤���Ƃɂ����B �@���k����́A���܂�ɑ傫�Ȋ⋛���C���������ĂȂ��Ȃ����t�����Ȃ��ł������A��҂����ɂ͂₵���Ă��A����ƕ��𗧂������Ă݂�ƁA������o�Ă������̂Ƃ́A��قǂ��k���V����ɂ����グ���܂���т������B �@���k����͂т����肵�č����ʂ����A���̊⋛�͖V����Ɏp����������ė����u�ς������蟺�v�̎�ɈႢ�Ȃ��ƌ������B |
|||||||||||||||
| 22���Ђ��� | |||||||||||||||
| �́A�ؑ]��тɓ��Ƃ�̑��������Ƃ��������B �ؑ\��͐��������A�݂���������������Ɍ����Ă����B�c��ڂɐ����Ђ������a�́A���킫�����āA��������L���L���P�����肾�����B������ɐ����Ă��鑐�́A���肫��Ɨt�������A���ɂ����ꂻ���������B �c�A�����߂��Ƃ����̂ɁA���납���ǂ���ł͂Ȃ��B�S�����イ�͋�����グ���ߑ��������B���̂ɁA��ɂ͂ЂƂ�����̉_���Ȃ��A���z�����ڗ��F�ɋP���Ă��邾�����B �Q�o�̗��̏����A�ׂ����A�J�̂��Ƃ���S�z���Ă����B �u���̂܂܂ł́A�c�A�����ł���B�Ă��Ƃ�Ȃ���A���̓~�A�Q�����ɂ�����̂��o��B������܂˂��Ă�����L�u�����ĉJ������Ă݂悤�B�v ���̖�A�ׂ��́A���̗L�u���W�߂āA��P�x�_�Ђ̗��{�ւ̂ڂ����B�����܂̉���˂ēo���čs�����B ���ꂩ����A�J����͂��߂��B �J��͂����ӂ��������A�J��͖̉閈�ɑ傫���Ȃ��Ă������B�͂��{�̏��̎}���������A�Q�������A�V�����܂��オ���Ă������B ���ꂪ���ƂɂȂ��Ă��A��ɂȂ�ƁA�������̎R�A�������̎R�ɁA�_�X�Ƃ����܂̉��̂ڂ�A�J��͖̉閈�ɑ����Ȃ��Ă������B ��Ƃ��Ȃ�Ɩؑ]�̎R�X�͉J��̉ɏƂ炵�o���ꋰ�낵�����肾�����B �ؑ\���̐l�X�̋F��́A�ق̂��ƂȂ��Ă������܂������������𗧂ĂāA���ɂ܂��オ���Ă������B ���́u�����[��A�����[��v�Ɖ��i�������A�Ԏq�͂��т��ċ������B�R�̏b�͎R�𑖂���A�Q�ڂ������́A�M�ɓ˂����B ����ł��A�J�͈ꗱ���~�炸�A���ݐ��ɂ�����悤�ɂȂ����B ����̓��A�������肵���ׂ��́A��ꂽ�̂��Ђ�����悤�ɂ��ĎR�����肽�B �����̑勴�̏��܂ŗ������A�ׂ��͋��̂����Ƃɔ��ւ��Ƃ���������Ă���̂��������B �ׂ��͘m�ɂł������肽���C�����ŁA �u�Ȃ��ւ�A�J���~�点�Ă���̂��B�����~�点�Ă��ꂽ��A��l���̂�����������Ă��������̂��B�v �ƂԂ₢���B ���ւ͂��̌��t���킩�����̂��A����������グ���Ȃ����ƁA����邵��鑐�ނ�ɓ����Ă������B ���炭�o�����A���܂ł���Ȃɐ���Ă����ɂ킩�ɓ܂�A�嗱�ȉJ���ۂ�ۂ�ƍ~�肾�����B �J�݂͂�݂��J�ɂȂ�A�����������n�ʂɋz�����܂�Ă������B���ꂻ���ł��������͐��������Ɠ��������グ�A�R�̖X�̗��N�₩�ɂȂ��Ă������B �ؑ\��͍��������グ�A�������̂悤�ɗ���͂��߂��B �ؑ]�J�̕S�����イ�́A���тœc�����炦�����A�c�A�����͂��߂��B �Q�o�߂̗��ł���Ăɓc�A�����n�܂�A�������̓c��ځA�������̓c��ڂŁA�͂��c�A�̂����������B �u�c�����@�Ȃ��c�̂�[�� ���˂���@���Ăǂ�����邼�ȁ[ ���̓c�̂�[�@���˂���[�� �����Ƃ߂́@�c��A���Ă�[�� �����A���[ �c�̐_�͂ȁ[�@�c�ɏo�Ă�[ �c�������@��[���v ��тɖ������̐��́A�R�̗ɋz�����܂�Ă����B�ׂ��́A���̂��肳�܂�܂���Ō��Ă����B �������x��Ă����앨�̂܂����A�A���t�����ǂ�ǂ�͂��ǂ��Ă������B �₪�ĉĂ������B �ׂ��v�w�Ɩ��̂������O�l���A���̓c��ڂŁA�c�̑��������Ă��������B���h�Ȑg�Ȃ�����������ׂ���K�˂Ă����B �ׂ��͋����ĉ������Ɛq�˂Ă݂��B ���ނ炢�́A �u���͋�P�x�A�Òr�ɏZ�ޗ��ł��B�������ʂ�A�J���~�点�Ă����܂����B�����玄�̉łɈ�l�����������������ƎQ��܂����B�v �Ɨ�V�������������B �ׂ��́A���̖���̓��̖��v���o���A���܂�̂��ƂɁA�����݂���₨�����̕���U��������Ƃ��ł��Ȃ������B �u�Ȃイ�����Ă����ꂾ���B������Ȃ��āA�������𗳂̉łɂ��Ȃ�āA����܂肾�B�v �����݂���͋������Ⴍ�����B�������͂��܂�̂��ƂɌ����������A�ւȂւȂƂ��̏�ւ����ꂱ��ł��܂����B ���炭���Ėׂ��́A �u���͊m���ɒv���܂����B�������A�������͉����m��܂���B��������ɂ������Ƃł������܂��B�ǂ����������̂����ɁA���̖��������グ�܂��B���ɂ���Ȃ�A���Ȃ�Ƒ����ɂ��Ă�������B�ǂ��������������͊��ق��Ă�������B�v �Ɨ��B ���́A�߂����Ɏ�����ɂӂ�ƁA�����܂����Ɏp��ς��A�_���ĂсA�͂邩��P�x�ւƔ�ы����Ă��܂����B |
|||||||||||||||
| �����Ƃ��قǂ���ƁA���܂Ő���n���Ă�����́A�ɂ킩�ɂ܂������܂�A�������������A�嗱�ȉJ���~��o�����B�J�̐����͂��̂������A����̐��͂����܂����ӂ�A���͓c�̓y������z���A���ɂ���͗����ꂻ���Ɍ������B �������������ŁA�͂傤��A����ł��炳��A�ؑ\���͂܂��呛���ɂȂ��Ă����� |
 |
||||||||||||||
| ���̂��肳�܂��A�������͂��т����ڂŌ��Ă����B �u���A�������łɍs���Ȃ�A���������A����������߂ɂȂ��Ă��܂��v �������̓��̒��ɂ́A�ؑ\�����A�����ӂ��グ���A�J��̉̂��Ƃ��A���e�̂₹���S�z�����Ȋ炪�A�����Ċ�тɖ������c�A���̂��肳�܂�������ł͏����A�����Ă͕�����ł����B �₪�āA�����Ɗ���グ���������́A �u�������A�������̂�������Ƃ͗ǂ����Ƃł��B�ǂ����������𗳂̂��łɂ���Ă��������B�������łɍs���Ȃ�A�܂��ؑ\���̐l����V������Ȃ��B�ꂿ���߂��܂Ȃ��ŁA�������͌Òr�֍s���܂��B�v �Ƃ��������Ǝv���ƁA�ׂ��v�w���Ƃ߂�Ђ܂��Ȃ��A���炵�̒��ւƑ��苎�����B ���炭����ƁA���܂ł���قǂɍr��Ă������炵�͉R�̂悤�ɂ����܂����B�s�v�c�Ɨ����ꂽ�c���Ȃ��A�ؑ]�̂��イ�͂����Ƌ����Ȃł��낵���̂������B ����Ȃ��Ƃ������Ă���A�ׂ��v�w�͂������̏Z��ł���Òr�����X�����˂�悤�ɂȂ����B ����Ƃ����r�̒ꂩ�邨�����̉̂��u�c�A�́v���������ɕ������Ă���̂������B�����Ēr�̂͂��ɂ́A�������̎p�ɂ悭�������Ђ������A�ЂƂ����炭�悤�ɂȂ����Ƃ����B�i�㏼���@�����j |
|||||||||||||||
| 23�����p�� | |||||||||||||||
| ���i�N�ԁA�㏼���̖���E�˖{�y���q�́A���H���ʂ̒n��E��ˎs�V��ƂƂ��ɐV�c�J���Ɍ����Ċ��삩�猴��֑a�����v�悵�܂��B���������ד��̋��ꂩ�甽�ɑ����A���ɂ͌�w���̖h�Ηp���Ƃ����G��o���ōH����i�߂܂����B������ɂ߂����H������O�L���̑�H���͂��悻�Z�J�N�ɋy�т܂����B�p���͒����A���A�A�Q�o�e�n��ɏ㐅�����ł��鏺�a�R�R�N�܂ň��p����h�Ηp���ɗ��p���ꌻ�݂��Ȃ��e���ʂɎg���Ă��܂��B | |||||||||||||||
| �Q4�|�P�s�v�c�ȕ����P | |||||||||||||||
| ���̐́A�ؑ]�̎V����Q�o�̏��܂ōs�����藈���肷��s�v�c�Ȑ�����܂����B���̐������ƌ��܂��ĕs�K�Ȏ����N���肻��������̑m�����̂��r��ł������߂܂����B �Z���ɂ́u�g�v��퐶�̎��ɂȂ���ĕ�������̗��ꂱ�������v �ȗ����͓̐��������ɕs�K�ȏo�����������Ȃ�܂����B�S���̏㗬�ɂ͍������̐��c���Ă��邻���ł��B |
|||||||||||||||
| �Q4�|�Q���� | |||||||||||||||
| �́A�ؑ]�����Ə㏼�̒��قǁA�ؑ]�쉈���ɍ��ꂽ����y�n�̐l�͔g�v�i�͂���j�̞��ƌĂ�ł������A�q�̞��ƐQ�o�̏��̊Ԃ��A�s�����藈���肵�Ă�����������B �@�u���v�Ƃ���ꂽ���̐́A�㏼�̕��ɗ���čs�������Ǝv���ƁA�܂����̊Ԃɂ����ɖ߂��Ă���B �@�����āA���̐������ƁA�K���ǂ����ōЊQ���N����s�K�Ȃ��ƂɂȂ�B �@����ŁA���̐l�����́A���̐������ƂȂɂ��������Ƃ��N����Ȃ���悢���ƐS�z���Ă����B �@������̂��ƁA����Ă������������낷�u�퐶�̒����v�ŁA�����̘n�݂�H�ׂȂ���A�����̎�l���炱�̘b�������̑m�́A �u���̖@�͂ŁA���̕����~�߂Ă��悤�v �ƁA��l���玆����������B�m�͂��̎��ɉ̂��������B �@�@�@�@�@�@�g�v��퐶�̎��ɂȂ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������̗��ꂱ������ �@�����āA���̉̂��ɖʂ������X�̕ǂɂ͂�A�������Ƃ��o�������Ă����B �@����ƁA���͂҂���Ǝ~�܂�A���ꂫ�蓮���Ȃ��Ȃ����B �@���ꂩ��Ƃ������́A���ɕs�K�͋N���Ȃ��Ȃ�A���̕s�������������ĂȂ��Ȃ����Ƃ����B |
|||||||||||||||
| �Q�S�|�R�ӂ����ȕ����Q | |||||||||||||||
| �����͂�����Q�o�̏��܂ł̊Ԃ��s�����藈���肷����������B���͕̐s�v�c�Ȃ��Ƃɗ���čs�����Ǝv���Ɓ@�܂����̊Ԃɂ������͂��ւ��ǂ��ė��Ă����B���̐������ƕK���Ƃ����قǁA�s�K�Ȃ��Ƃ����������B �@������̂��ƁA�����̂悤�ɂ��̐������̂��������V�����̎�l�́A�u�܂������������Ƃ��N����˂悢���v�ƓX�Řb���Ă����B���傤�ǂ����ɋx��ł�����l�̗��̑m���A���̘b�����Č������B�u���������ԁA�����痷�ւƏC�Ƃ��Ă����̂ŁA���̏C�Ƃ̗͂ŁA���̐��~�܂邩������Ȃ��B�v�ƁA���̉̂��r�B �@�@�@�@�@�g���i�͂���j��@�퐶�̎��ɂȂ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������́@���ꂱ������ �@���ꂩ��@���̐͗���邱�Ƃ��~�߂Ă��܂����̂ŁA�S���̏�ɍ����c���Ă���Ƃ������Ƃł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���i�͂���@�@�@�����͂��̂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�퐶�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̂��� |
|||||||||||||||
| 25���Ƃ������̐� | |||||||||||||||
| �@�́A����������������\�̓�\�O���̗[���A���̖V���܂��A�ؑ]�H��ʂ������̘b������B �@ ���̖V���܂��A���e����ؑ]���n���āA�B�|�܂ŗ����Ƃ��́A���͂Ƃ��Ղ�ƕ��Ă��܂����Ƃ�B����ƁA�ꂯ��A�݂��ڂ炵���S����������������A���̖V���܂́A���̂����̖���ɗ����ĂȁA �u�킵�́A���̎҂ł����A����͂����ɂ��ƌ����Ȃ��A���������Ȃ��n���A�ǂ�����ӂ̏h�ƁA����̔т��߂���ł�������B�v ���ė������ȁB ��������ƁA�Ƃ̒�����A��ڂ�ڂ̂������o�Ă��ĂȁA �u����͌�C�̓łɁA�����ǁA���Ă̂Ƃ���̂���Ƃ��ŁA�H�ׂ���̂�����܂��A�悩������ǂ����������肭������B�v ���āA���܂Ȃ����Ɍ����āA���̖V���܂��Ƃ̒��ֈē����Ă�������Ă������Ƃ��B |
 |
||||||||||||||
��������́A���܂ŁA���Ɏ����Ă���������Â������܂��āA�킴�킴���̒�����A���Ђ����o���Ă��ĂȁA �u�H�ׂ���̂́A����ȒЂ��������Ȃ��āA�v ���āA���߂����A���̖V���܂͂Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ��B �@�̂̐l�́A�Ђ������ʂ�����ȁB�H�̏I���Ɏ�ꂽ���t�̂����ŁA�����̂͒��Ђ��ƌ����Ă��̂܂ܒЂ�����ł�B������Z���̂́A����ł��Ƃ����B�����ŁA�����܂ł́A����Â���H���āA�N��������ƁA���Ђ����o���Ƃ������ɂ��Ƃ������̂��B �@���āA�Ђ����ł����Ƃ����̂��̖V���܂��B���炭���ƁA�ǂ����������Ǝv���ĂȁA �u���ɐ\����Ȃ����A�����䂪�������炢���ς�������ʂ��B�v ���ė����B �@��������͍��肫����������āA �u�킵�́A�����̂Ƃ��葫�������ĕn�R�Ȃ���ŁA�ꗱ�̕Ă��Ȃ��āB�v ���āA�f������������B ���̖V���܂́A�Ƃ̑O�ɂ���͂���ɂ������Ă����Ƃ��������w���ĂȁA �u����������Ƃ��Ă��邪�����B�v ���āA���������������B��������́A �u�Ƃ�ł��������܂���B����͂ƂȂ�̂͂���ŁA����ɁA�킵�݂����ɑ��̈������̂��Ƃ�ɍs���A���Ղł����킩���Ă��܂��B�v ���āA��F��ς��ē������B �u�S�z���Ȃ�ł悢�B�킵���A���O����̑��Ղ�������悤�ɐ���~�炵�Ă���B�v ���āA���̖V���܂́A���������Ă������������B ��������́A������Ƃ���ɁA�͂��ꂩ���Ƃ��������Ƃ��Ă��āA������������ĐH�ׂ������������B �@���̒��ɂȂ��Ă݂�ƁA�ǂ����A�Ⴊ�������~���Ă����B �@���̖V���܂��������Ƃ���A���Ƃ������̐���~�炵���ȁB �@���̖V���܂́A��������ɗ�������ĂȁA�ؑ]�H��k�Ɍ������ė��������Ƃ������Ƃ��B �@���̂��Ƃ������Ă���Ƃ������́A�\��\�O���ɂ́A�ǂ��̂����ł���������H���悤�ɂȂ����������B����ɁA���̓��ɂ́A�����Ƃ��Ƃ������̐Ⴊ�~����ē`�����Ƃ�B �@���ꂩ��ȁA���̌B�|�ł́A���ł��A���̓��܂ŐؒЂ���H���āA��\�O���ɂȂ�ƁA���߂Ē��Ђ����o���悤�ɂ��Ƃ���Ă�B �@���̖V���܂́A��t���܂��Ă����Ƃ��Ă��̂��V�l�������ȁB |
|||||||||||||||
| 26��P�x�_�Ђ̑��X�_�y | |||||||||||||||
| �ؑ]��P�x�R���ɂ����P�x�_�Ђ̉��̋{�ɂ́A�Ր_�Ƃ��ĕېH��_�i���������̂������݁j�A�L���_�i�Ƃ悤���̂������݁j���J���Ă���B �@���̗��{�ł����P�x�_�Ђ́A�����̎Y�y�_�Ƃ��Ȃ��Ă���B �@���́A���{�Ō܌��O���ɍs�����Ղɂ́A�Â�����`�����Ă���u���X�_�y�v����[�����B �@���̐_�y�́A�V���Z�N�i�P�T�R�V�j�Ɏn�܂�A�V�̊�ˑO�̐_�y���ɔ\�y���������݂̐_�y�ɂȂ����Ƃ����A�܂��ˉB�_�Ђ̑��X�_�y���`��������̂Ƃ������Ă���B �@������ɂ���A�o�_�n���̐_�y���Ƃ����邪�A�Â��_�y�̌^���ό`���Ȃ��ŁA�����Ȍ^��ۂ��̂̂܂܂Ɏc����Ă���B �@���ł��j���I�ȁu�l�_�ܕԔq�v�̕��́A�����V��̖ʂ������l�l���A�h�V���A�h�h�h�h�b�ƁA�����������Ƃт͂˂�̂����A���̑��̓��ݕ��ɍł��Â��_�y�̌`�Ԃ��悭�c����Ă���Ƃ����B �@���̓��ɂ��Տꐴ�߂̂��ƁA�{�a�O�̓�Ԏl���̕���ŁA��ˊJ���A��_�����A�K�_���A�_���|���Ǝ��X�ɉ������A�O���̕��ł݂͌��Ɍ����ɂ��荇������A�����̊Ԃ�������ʂ���ȂǁA�R�x�n�̐_�y�̂������낳���`���A�܂���߂����ĕ����É�䕑�A�����䕑�Ȃǂ́A�D��ȏ����I�ȕ��B �@���̂ق��A��p�I�ȕ��A�_�̈Г����������ƁA�ɂ߂đ��ʂȓ��e���������ꂽ���X�_�y�́A��{�̐_������ɓ`���Ă���B |
|||||||||||||||
| 27�Ԃ����̊� | |||||||||||||||
| �@�㏼�̐Q�o�̏��̂ނ����ɁA�u���v�Ƃ�������������܂����B���̕����ƒ��Ƃ̌�ʂ���ϕs�ւł킴�킴���܂������Ē��֏o�Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŕ����ƒ��̊Ԃɂ苴�������邱�Ƃɂ��܂����B�����Ă苴�̊����ɓn�肼�߂����邱�ƂɂȂ葺�̐l���吨�W�܂�n���Ă݂܂����B�Ƃ��낪���̂苴��n���Ă��邤���ɐ�̗��ꂪ�r�����Ă��āA�^���܂ł���ƍr�ꂽ���̒�����Ԃ����̊炪�����܂����B���l�͂��ꂪ���܂�ɂ����낵����Ȃ̂őS���n�肫�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���ꂩ�炢�낢��Ȑl�����̂苴��n�낤�ƒ��킵�܂������N��l�Ƃ��ēn�肫�邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B |  |
||||||||||||||
| 28�։ŗl | |||||||||||||||
| �́A�ؑ]�H��тɓ��Ƃ肪�������������̎��A�㏼���i���̏㏼���j�̐Q�o�߂̗������n�������芣�������Ă��܂��ēc�A�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����ł͑吨�̐l�X���W�܂��Ė����̂悤�ɉJ����������A��H�̉J���~�炸�A���ݐ��ɂ����s���R����悤�ɂȂ����B���܂肩�˂��Q�o�̏����́A��P�x�_�Ђ̗��{�ɂ������āA��S�ɉJ��̊���������B �@���ꂩ�琔������������̓��ɏ����͔�ꂽ�g���Ђ�����悤�ɂ��ĎR������A�����̑勴�߂��܂ŗ������A���[�Ɉ�C�̑傫�Ȏւ��Ƃ�����܂��Ă���̂��ڂɂ����B�������߂Â��Ă悭����ƁA�ւ͂܂����Őg�̏���i��R���j�ȏ���������B�����͓����悤�Ƃ������A�����Ƃ������܂��Ă��锒�ւɁA�u�����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ��B���������Ƃ��ɁA�J�����~���Ă�������̈�l���ł����ł��~�������̂�����Ă�邪�Ȃ��v�ƌ����ƁA���ւ͏��������������Ƃ��킩�����悤�ɁA�}�Ɋ���������グ���B����ƕs�v�c�Ȃ��Ƃɍ��܂Ő���Ă����ɂ킩�ɓ܂��Ă������Ǝv���ƁA�ۂۂƉJ���~���ė����B���̉J�݂͂�݂邤���ɑ�J�ƂȂ��đ�n�����邨���A������̑����݂�Ȑ������������B�������c�A�������݂ق��ƈꑧ���A�����̖�ǎd���ɐ��o���Ă����B �@�ċ߂��ɂȂ������ɂ͔��ւƂ̖���������Y��Ă��܂��āA�e�q�O�l�ŗ��̓c��ڂ֏o�āA�c�̑����Ƃ��Ă����B����Ƃ����֗��h�Ȑg�Ȃ��������l�̕��m������ė����B�����͂��̂悤�Ȃ݂��ڂ炵���S���̏��։��̗p���������ė����̂��낤�Ǝv���āu������p�ł��傤���B�v�Ɛq�˂�Ɓu���Y��ɂȂ�܂������B���͐���A�M��������������ɂȂ�����P�x�_�Ђ̎g���A�Òr�ɏZ�ޔ��ւł��B�ʂ�J���~�炵�Ă����܂�������A���̉łɂ��Ȃ��̈�l�������������ɎQ�サ�܂����B�v�ƌ������B �@���̌��t���Ə����͐���勴�̋߂��Ŕ��ւƖ������Ƃ��v���o���A�܂�ʖ��������̂��Ǝv�������ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����͍ȂƖ��ɂނ����āA�u���܂�A���܂�A�����Ă���v�Ƃ������肾�����B���̎������Ȃ��炻�̘b���Ă���������������āA���̕��������A�u��������A���͔��ւ̏��ւ��łɍs���܂��B��������̂������Ƃ͂悢���ƂȂ�ł��B�������łɍs�����ނ��Ƃł��B�Q�o�߂̗��̐l���肩�ؑ\���̐l�������~��ꂽ�̂ł�����v�ƌ������B�����ċ����Ă����e�̕��������A�u���ꂳ���Ȃ��ŁA���͂��ꂩ��Òr�ɂ܂���܂��B�Òr�͂������炻��Ȃɉ������ł͂���܂���B�Ƃ��ǂ���ɗ��ĉ������B��������A���ꂳ��A�\���N�Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B�̂ɋC�����āA�����������ĉ������B�v�ƌ����ƁA�����Ɩق��đ҂��Ă������ւ̕��m�ɔ����āA�R�����Òr�Ɍ������ēo���čs�����B �@���̂��Ƃ������Ă��珯�����e�́A��l���̏Z��ł���Òr�����X�K�˂��B���̎��ɂ͒r�̒ꂩ�炢���A�K�`�����A�K�`�����A�Ƌ@�D������Ă��鉹���������Ă����B�܂����̌Òr�ɂ́A���ꂩ��������@�̉Ԃ���֍炭�悤�ɂȂ����Ƃ����B |
 |
||||||||||||||
| 29�ւтÂ� | |||||||||||||||
