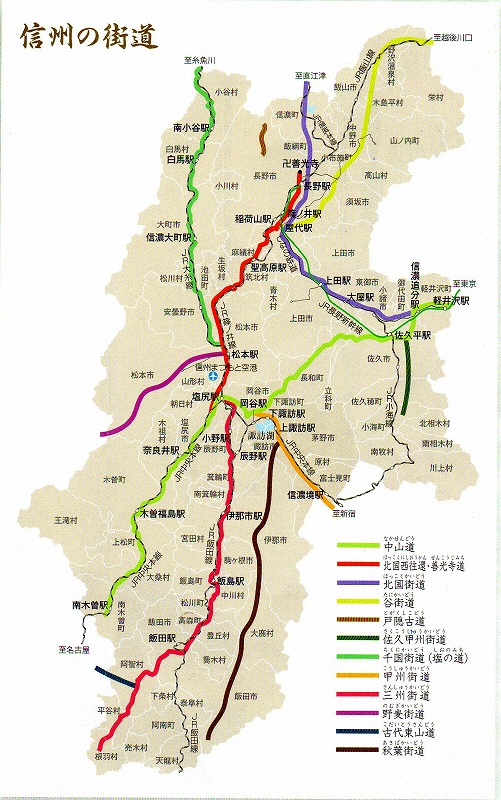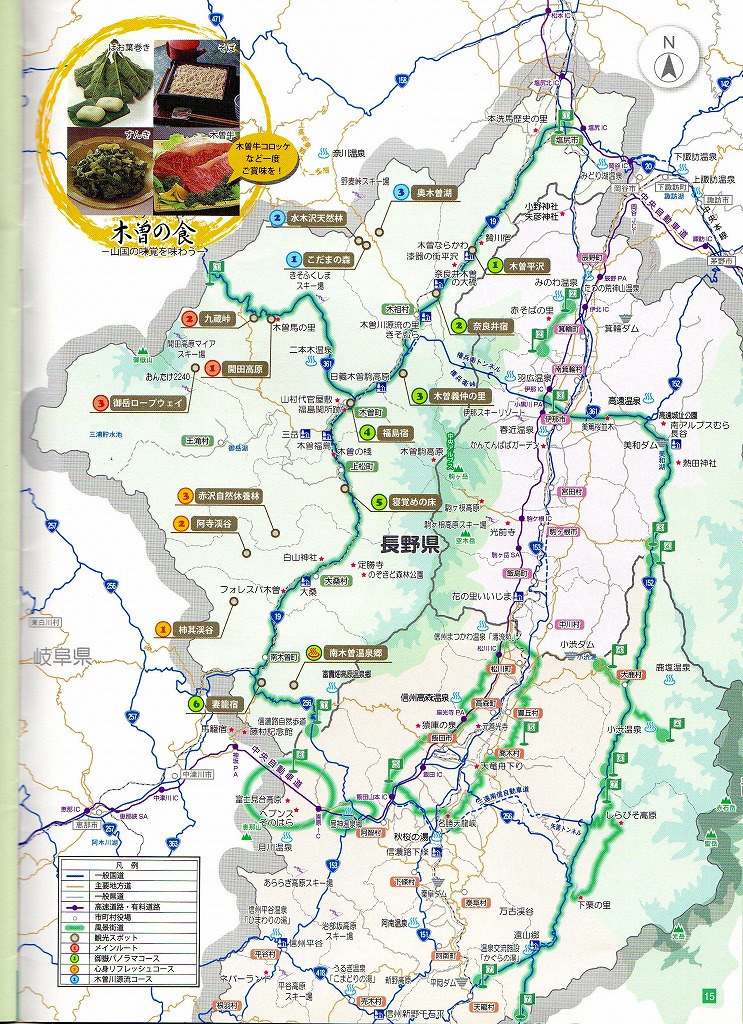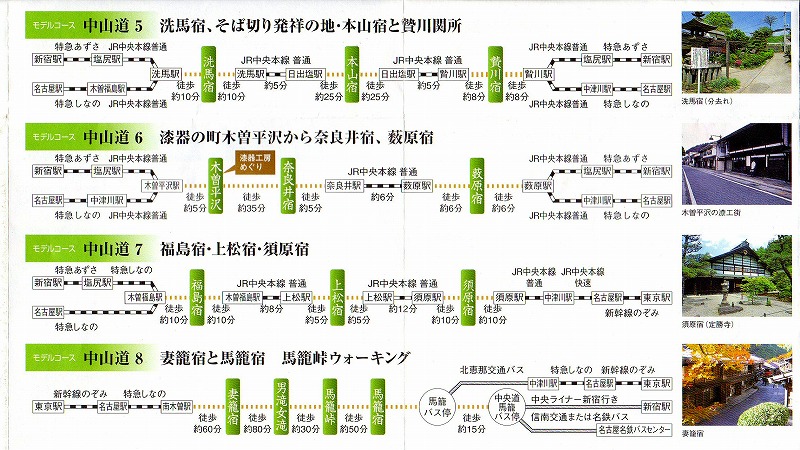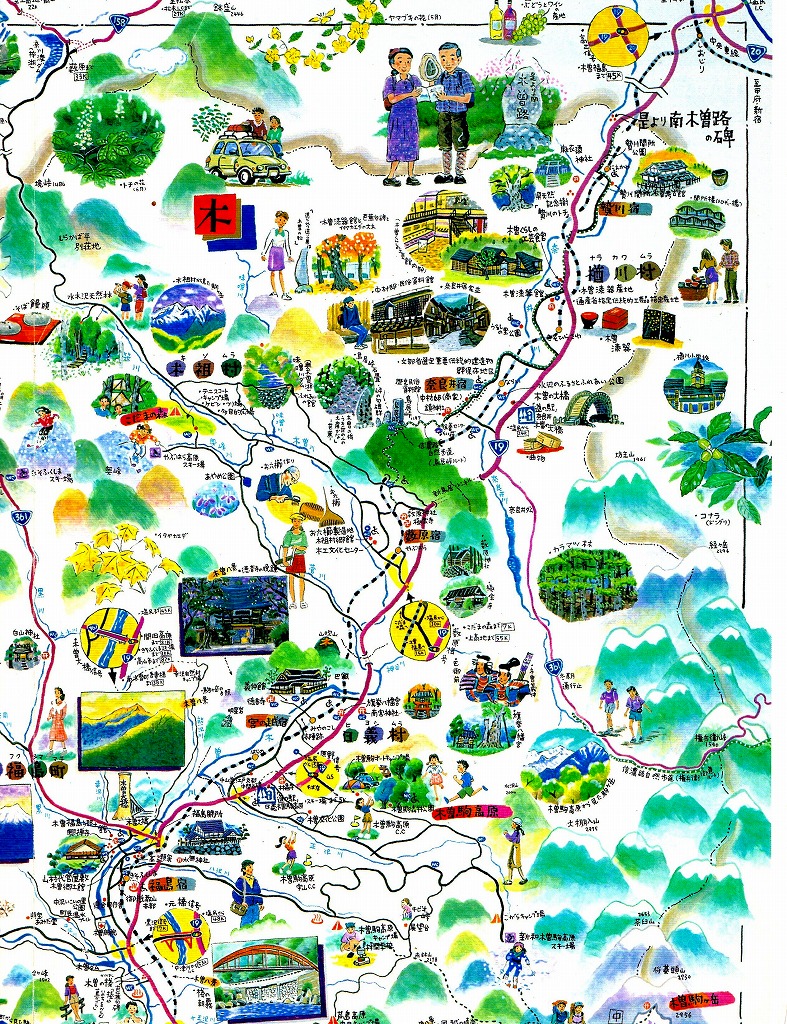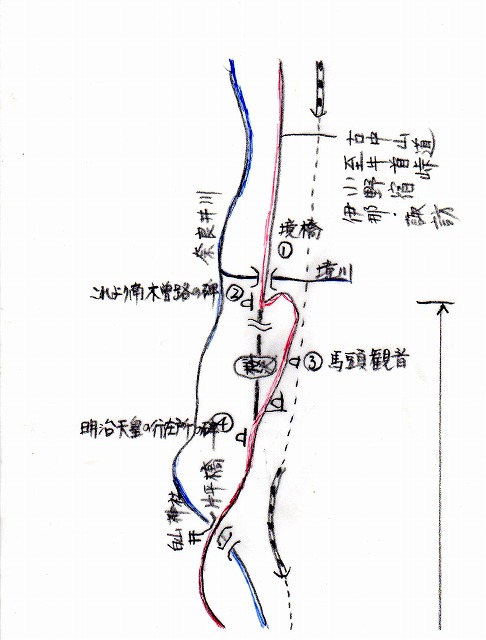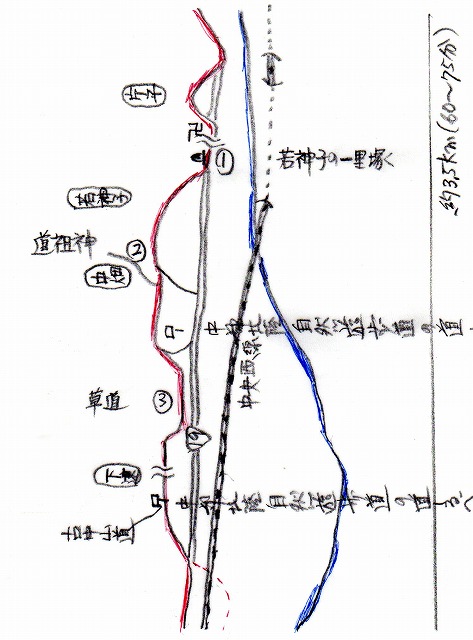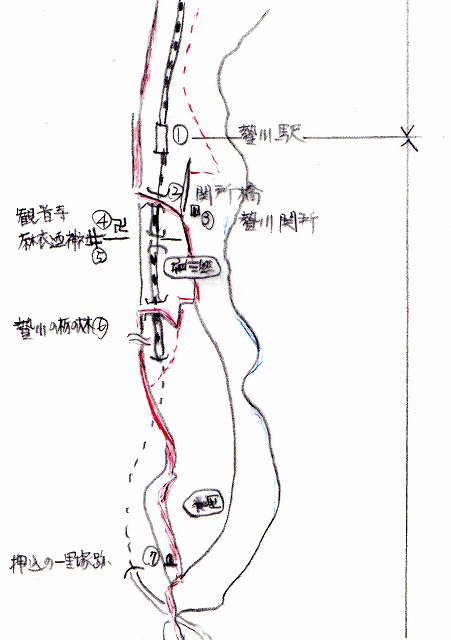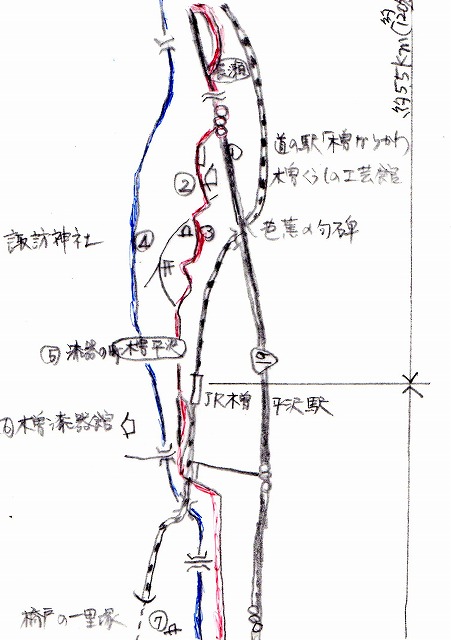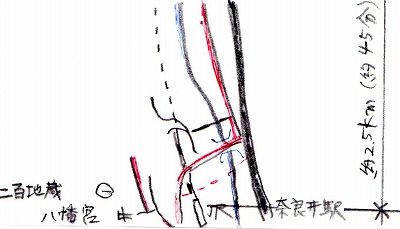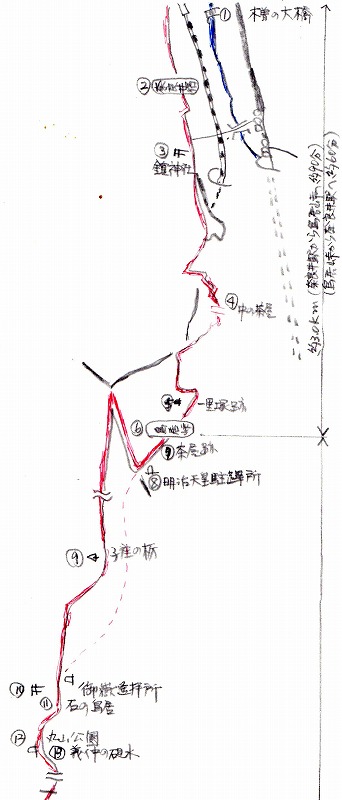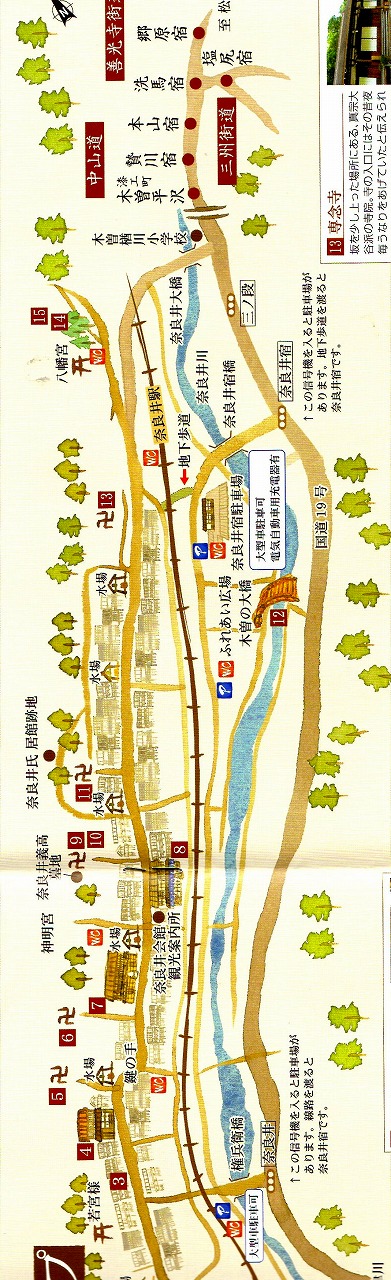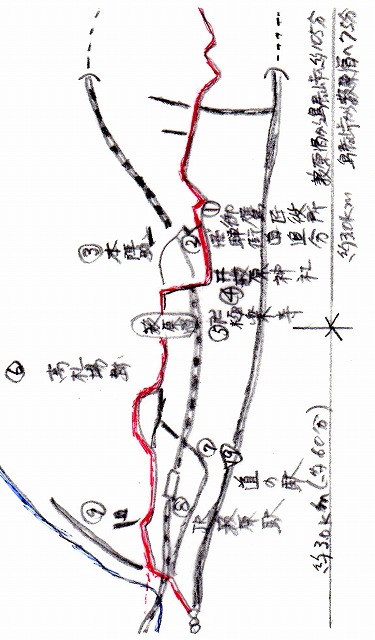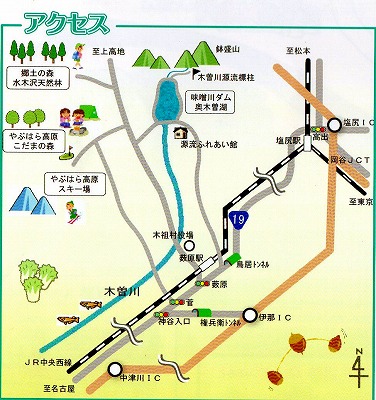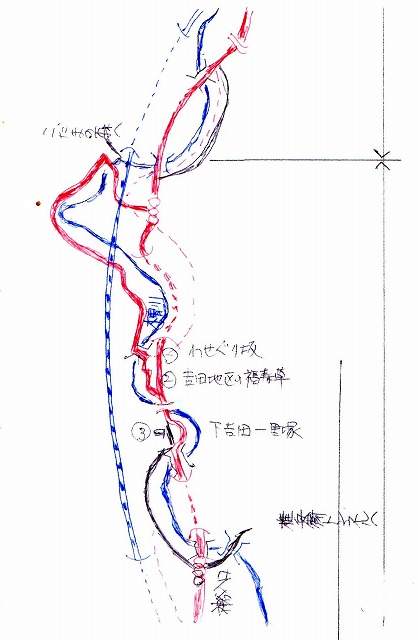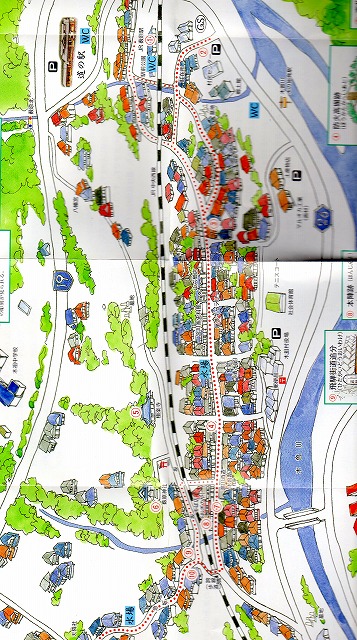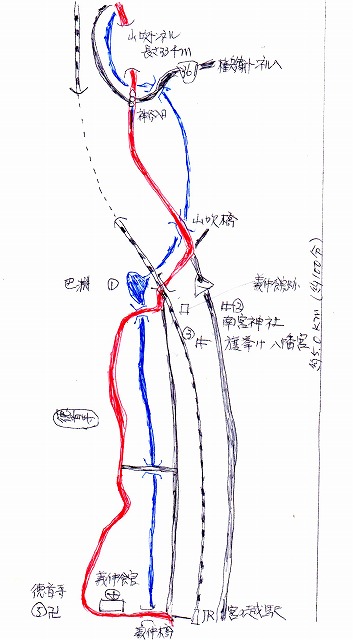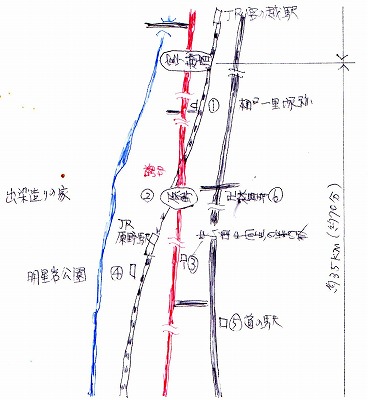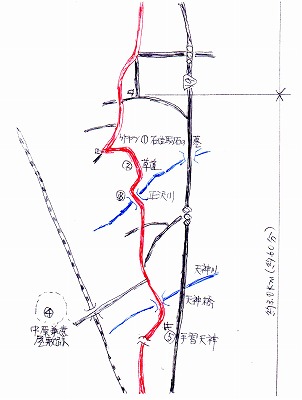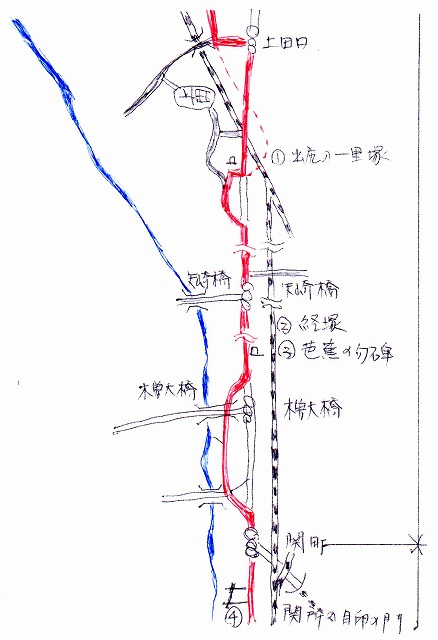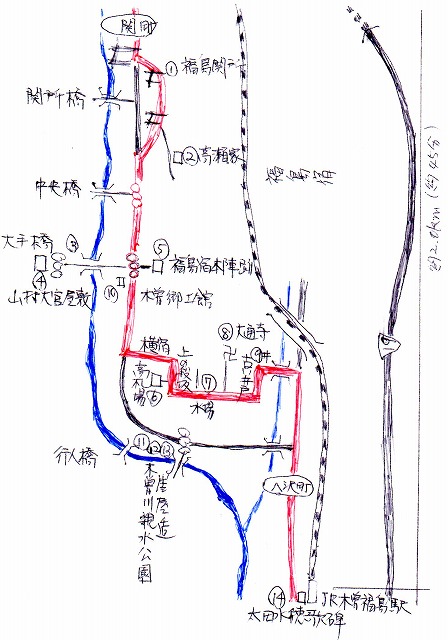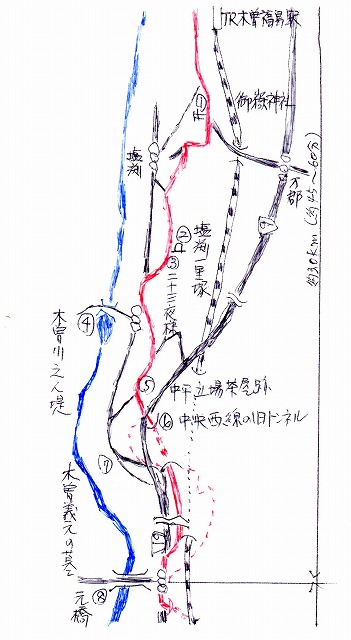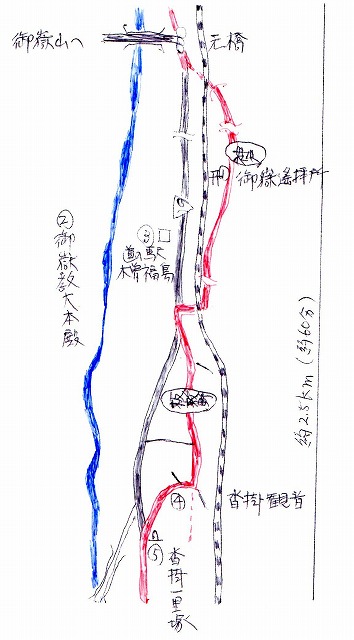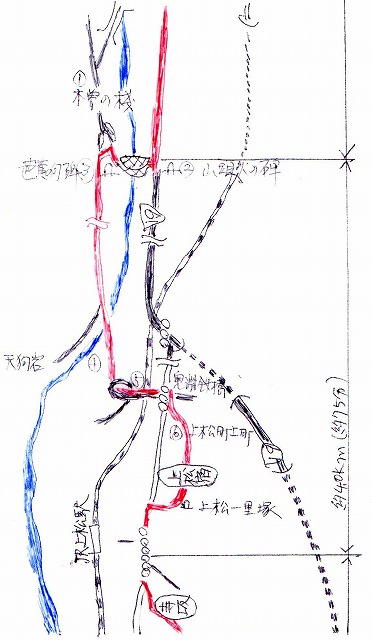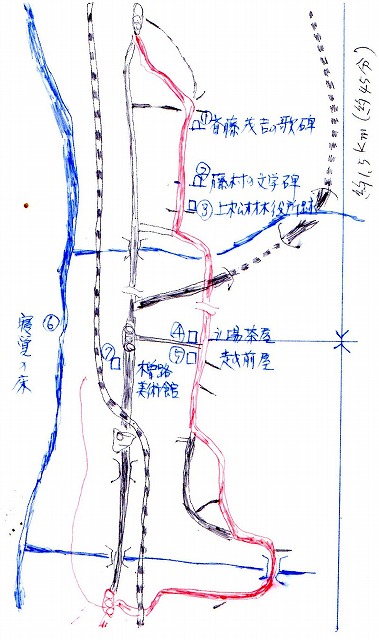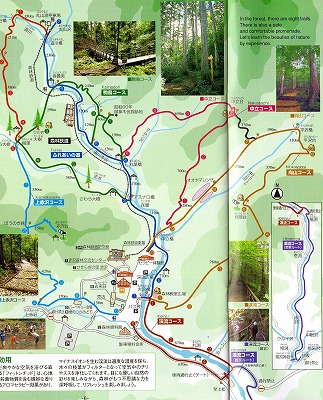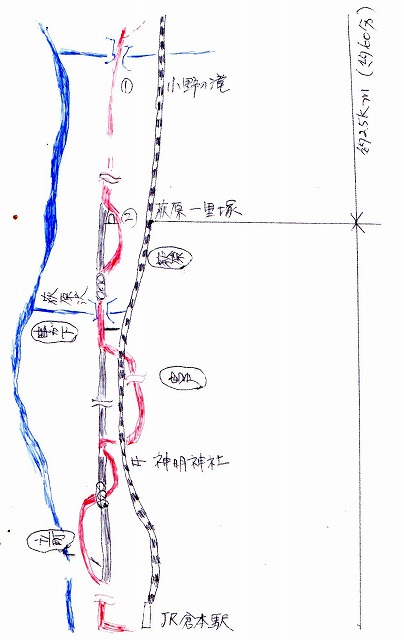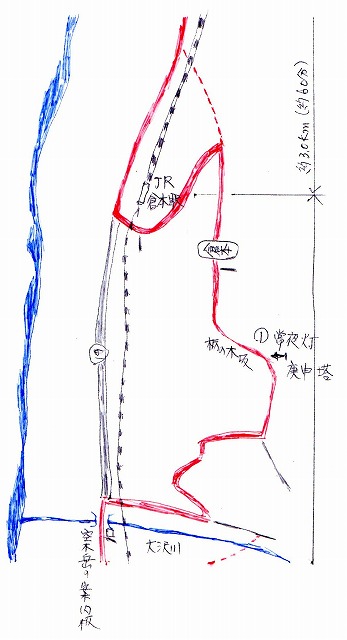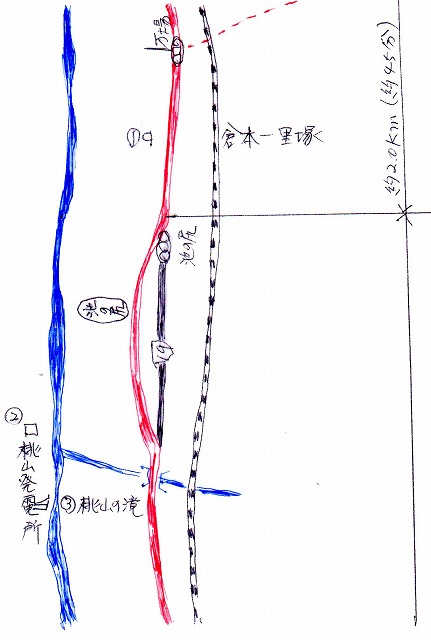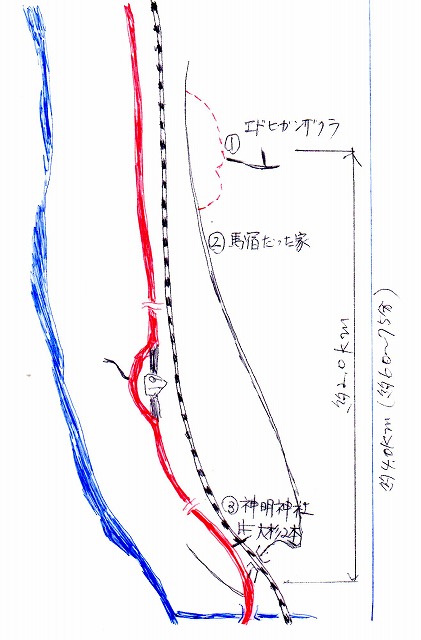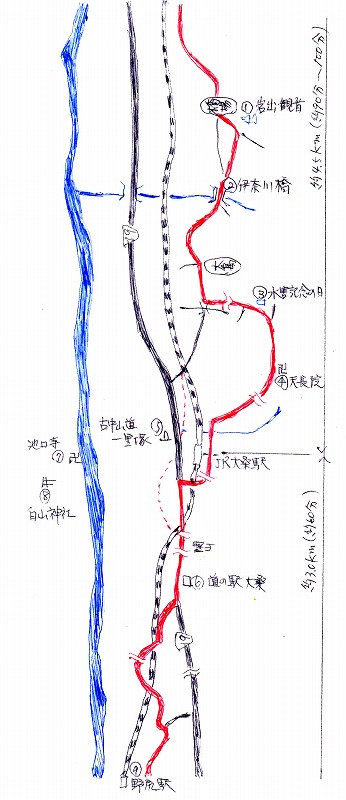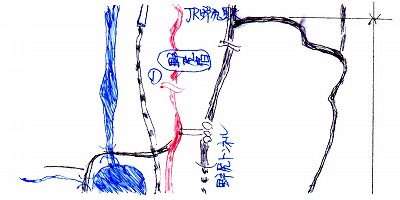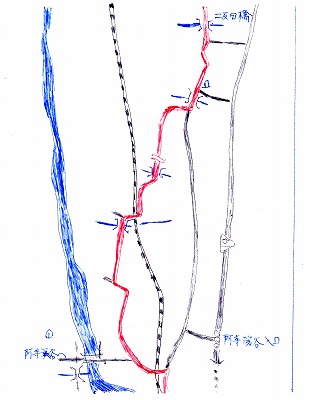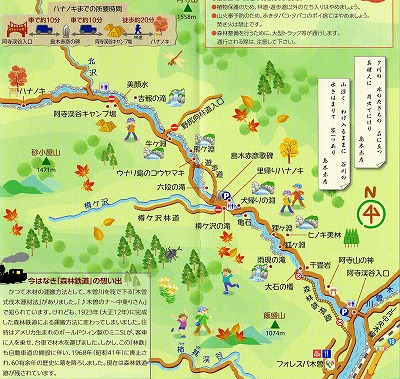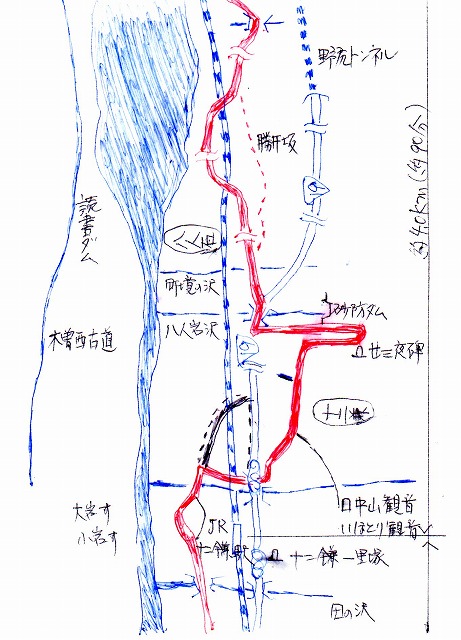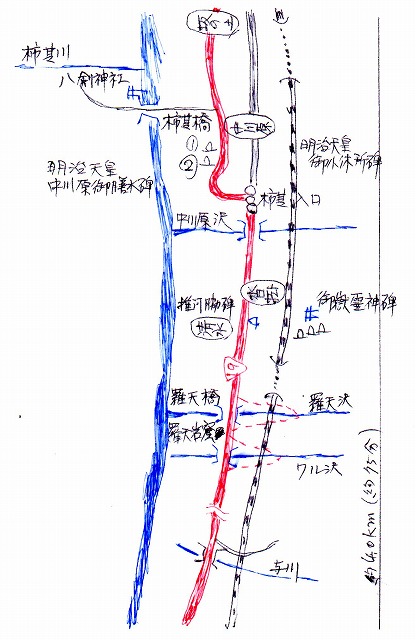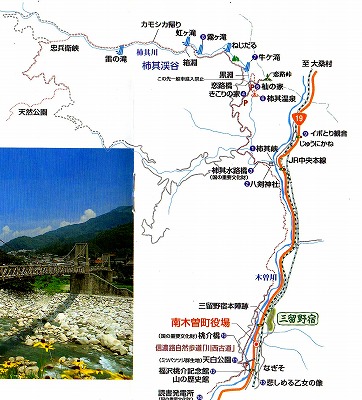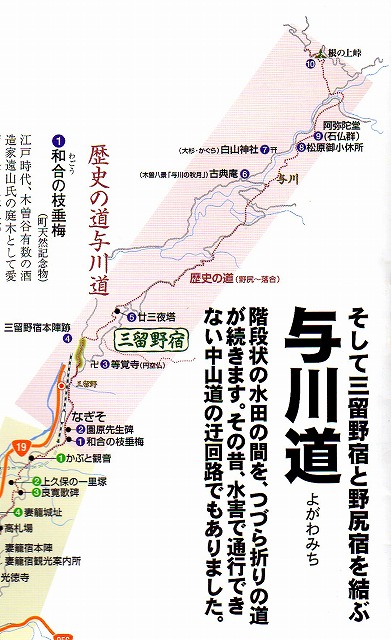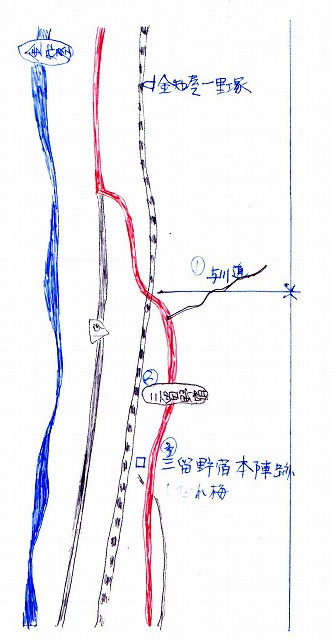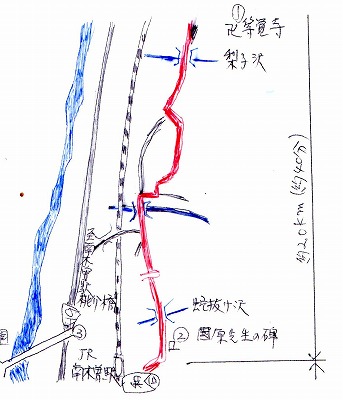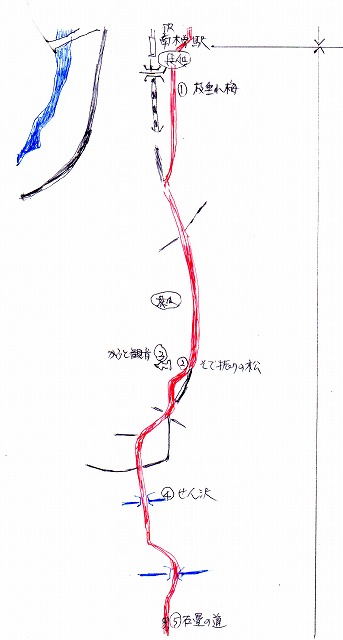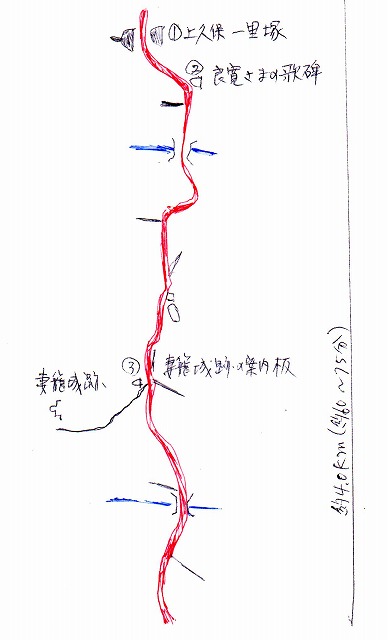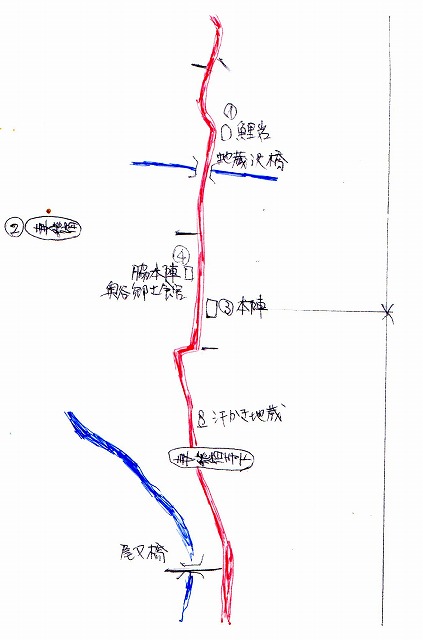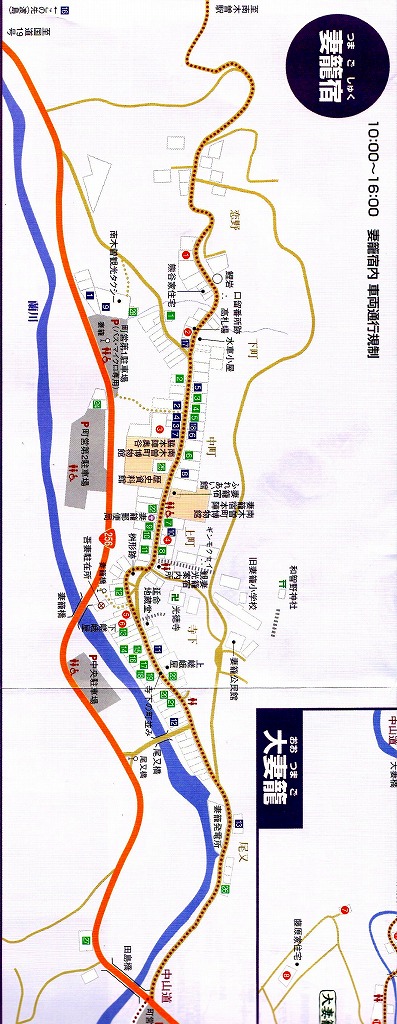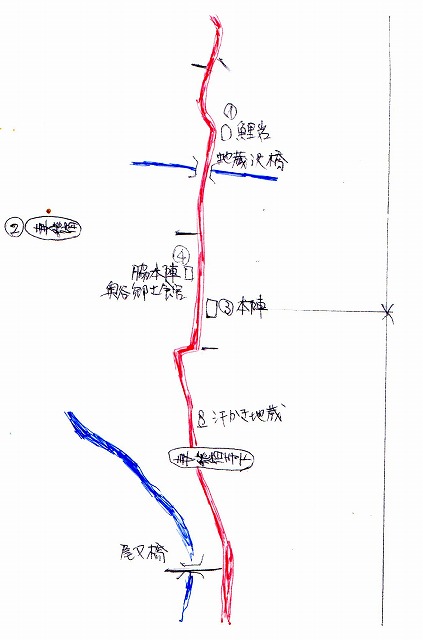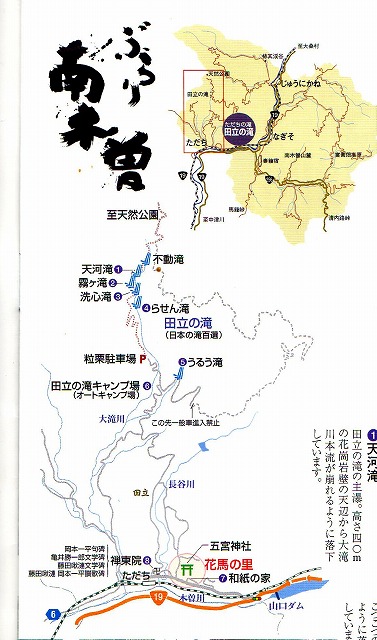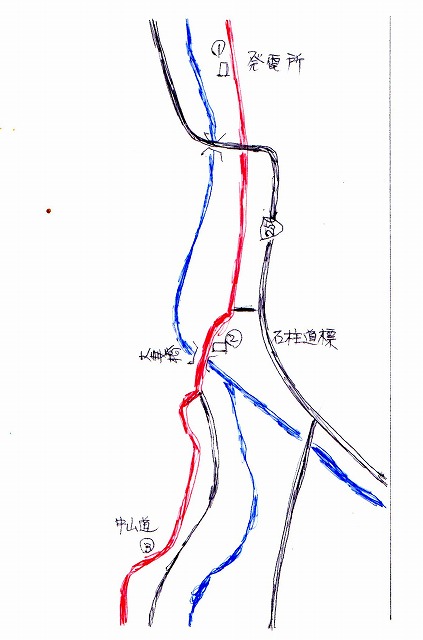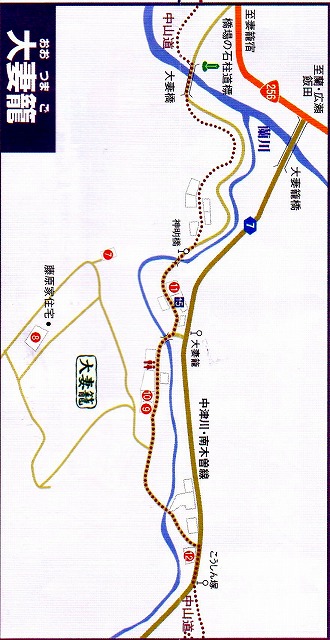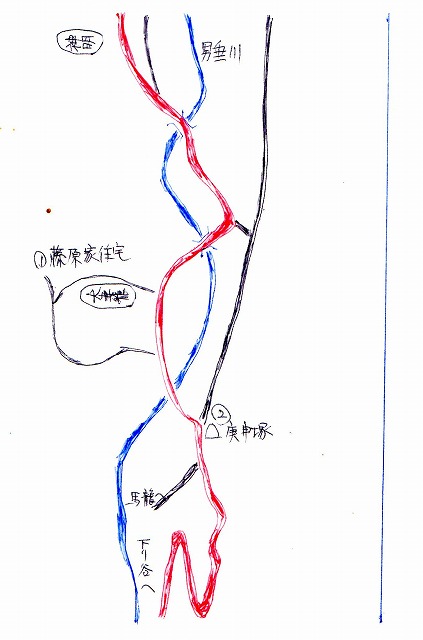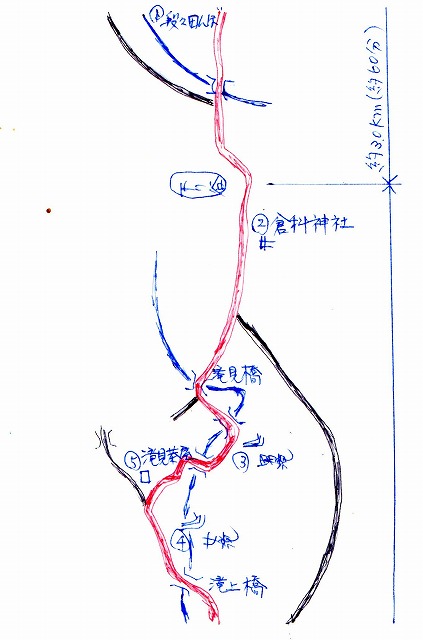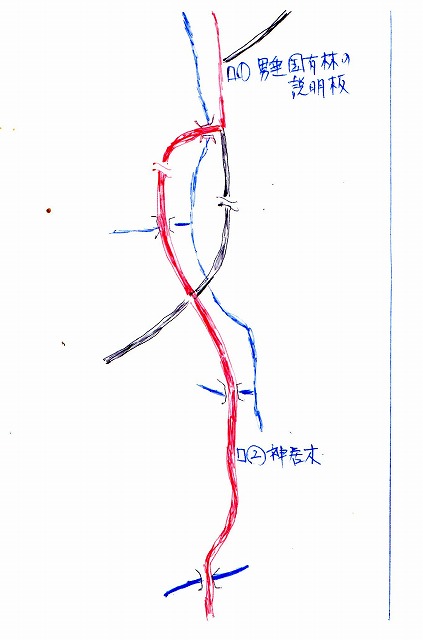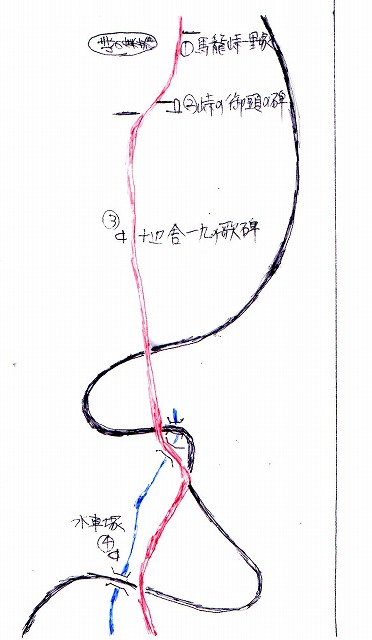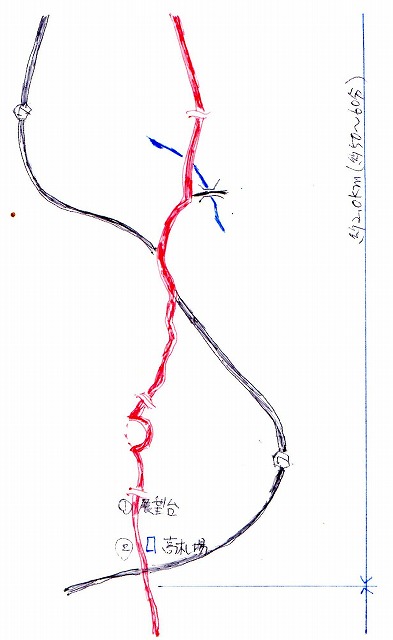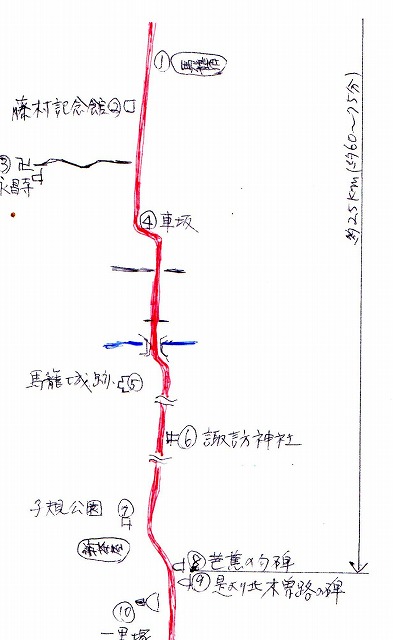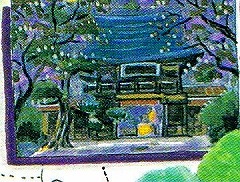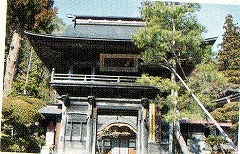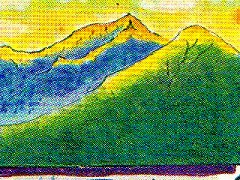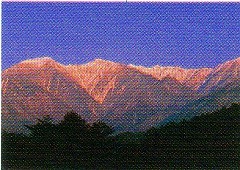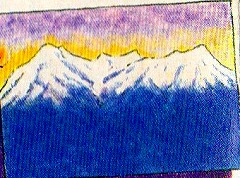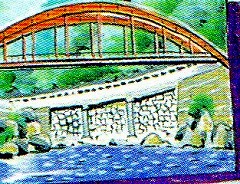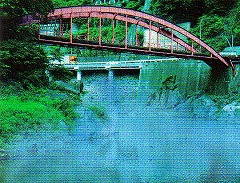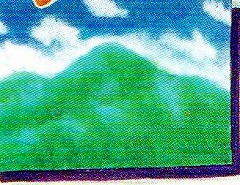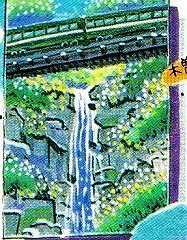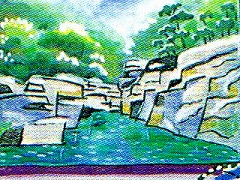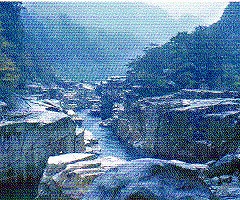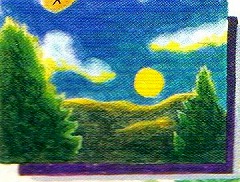| �n�@�@�@�@�@�} |
���ǂ���
|
| |
|
| ���{�b�`���� |
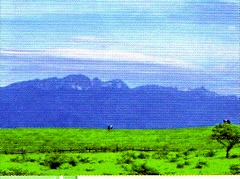 |
|
| |
|
| ���K�h |
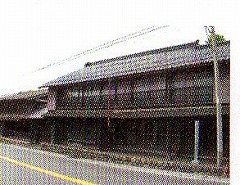 |
| ���o�ꗢ�� |
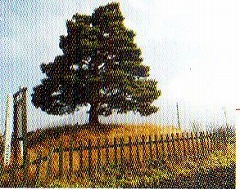 |
���n�h
���n�h�͖ؑ]�`�������n���������ƂɗR�����Ă��̖�������B |
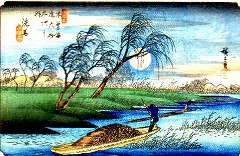 |
���n���ӂ��̐���
�ؑ]�`�����Ɛb���䌓���Ɖ�����ꏊ�Ƃ���邠�ӂ��̐����͎�����Đ�����N���o���Ă���B�܂��h����̂͂���ɂ͒Ǖ����W���c����Ă��蒆�R����H���Đz�K�A�y���A���̏I�_�]�˓��{���ɑ������ƑP�����ւƑ����k�����X���̕���_�ł������B
|
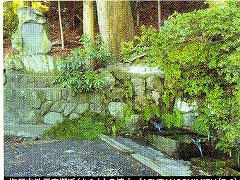 |
���K�s
�{�R�h
�]�ˎ���̕����u�������I�v�ɂ͖{�R�h���u�����蔭�˂̒n�v�Ƃ̋L�^������B |
 |
|
| �P���� (�����Q�T�N�X���P�W���@���j��) |
�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�S����) |
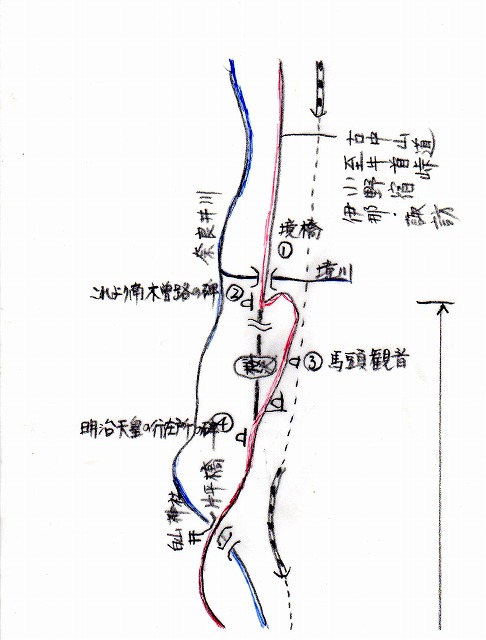 |
| |
�P���ڂ̂P |
| ���o���w�W�F�R�O |
|
| ���o���ꗢ�ː� |
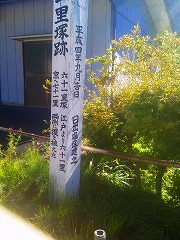 |
�@
���� �E���� |
���Ă̔����ƐM�Z�̍� |
�A
�������
�ؑ]�H�̔� |

���̐Δ�̂�����͓ޗLj��̎x���̈�ł��肱�̑ؑ]�̖k�̍�ƂȂ肱���ɂ�����ꂽ��������삪�u�ؑ]�H�v�ɂȂ�B |
����̍� |
 |
�B
�n���ω� |
 |
| ���R�� |
 |
| ���R�� |
 |
| ���ꒃ�� |
|
�C
�����V�c��
�s�ݏ��̔� |
 |
�����V�c
�䏬�x�� |
 |
| |
 |
| ���R�_�� |
|
����
�y�؊w��E�y�؈�Y |
|
| �����k�����R�����̓������ |
|
| |
�₳����������߂̍炫����
�ؑ]�̎R �@�@�i�����q�K�j |
|
| |
|
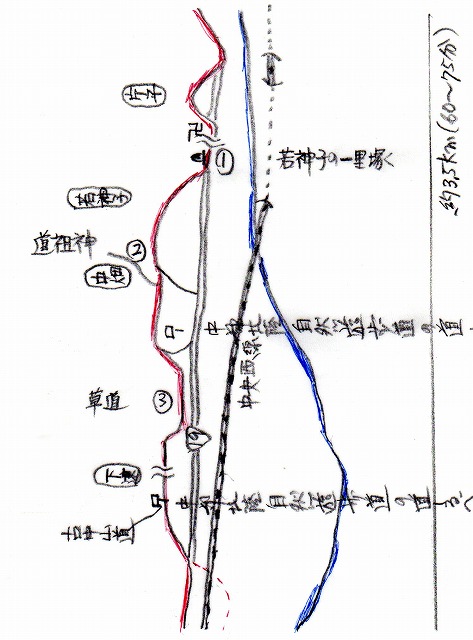 |
|
�P���ڂ̂Q |
�@
��_�q�ꗢ�� |

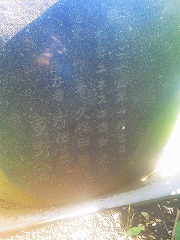 |
| ��_�q�ꗢ�� |
 |
�A
���c�_ |
 |
�B
���n |
 |
| ���������낷 |
 |
| �����k�����R�����̓������ |
|
|
| |
|
������
���a�P�O�N�i�P�X�R�T�N�j���œޗLj䑤�Ɋ|�鋌�����P�X���̋����Ƃ��ďd�v�Ȗ�����S���Ă��������a�R�R�N�i�P�X�T�W�N�j�Ɏn�܂����V�������݂ɂ�苌���͔p�~����Е����͂��̖�ڂ��I�����B
|
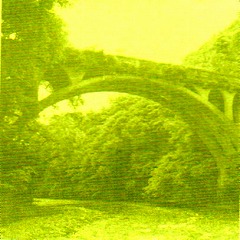 |
| |
|
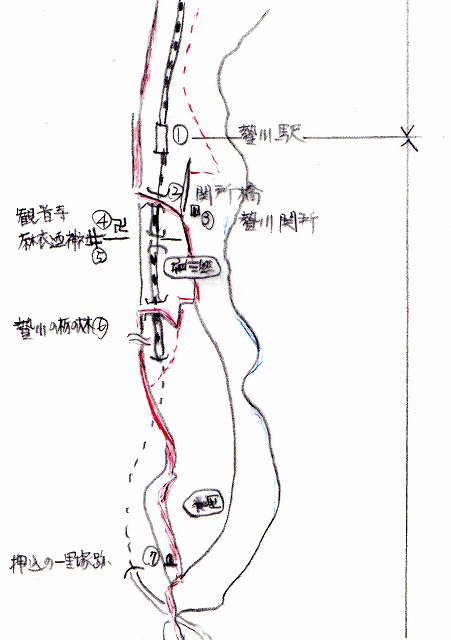
�@
����l
�h�ꂩ��ޗLj��̑Ί݂ɑ���l�ƌĂ�Ă���f�R��ǂ�����B���̊�R�ɂ͑���@���̐Α����J��ꂽ����������w��̊┧�ɂ͂��܂��܂ȕ��̖������Γ�����ʂɒ���t���悤�Ɍ��Ă��Ă���B�V�۔N�ԍ��Ɋω����̑m��������@�������̏ꏊ���J�������Ƃ������l�ƌ�����悤�ɂȂ����B����ȑO�͌�ԍs�҂̗��ł������Ƃ����Ă���B |
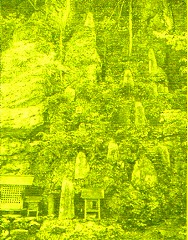 |
| |
|
|
| |
�P���ڂ̂R |
| |
������l�k�ւ̊G�̒����s��
�ؑ]�̎R�H�̉Ă̗[����
�i�g��E�j |
�@
�ѐ�w�O |
 |
| ���̋{�Δ�Q |

���Ƃ͂����ɂ��{������֏���ʂ낤�Ƃ��闷�l���g�Â��낢�������Ƃ����`��������ꏊ�B�]�ˎ���ɂ͂�������⓹��o��Ɩ،˂����肻�̉E��i�����j���֏��ł������B |
��R�R��
�ѐ�h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�Q�T�� |
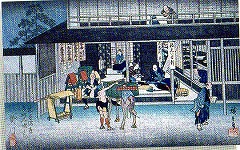
�ѐ�h�̒��ǂ���
���������Ђ������ޗLj�h�ɂ�����ѐ�h�ɂ͔��܂�q�������~�߂���̂��Ȃ������B������[���ɂȂ�Ƌq�������Ђǂ������~�ߕ��������̂ŗz�̍����������ѐ�h��ʂ蔲���悤�Ƃ������l�����ѐ�h�̒��ǂ���Ƃ������t���]�ˎ���ɐ��܂ꂽ�Ƃ����B |
| |
�ѐ�̓�ɗאڂ���ޗLj�͋ߐ���������⎽���Ȃǖؐ��i�̈��Y�n�Ƃ��Đ������Ă����B�ޗLj�ō��ꂽ�w���H�⎽����ѐ삪�S���֔̔����镪�ƊW�����̍��͌`������Ă����B�ѐ�h�̐��Ƃ��ߐ���ʂ��ď��X�ɗ��ʋƂֈڍs�����l�q���u���R���h����T���v�Ȃǂ��炤��������B �܂��s���ɂ���Čo�ϓI���͂�������L�͎҂����݂����Ɠ`�����Ă���B�u�ޗLj�߂������߂����E����߂����{�߂����E�ѐ�߂������߂����v�̌����`��������B
�h�w���x�̔p�~�ɂ��_�ыƂ��͂��߂���̂������Ȃ�͊ݒi�u��̊ɎΖʂɔ_�n���L�����B�������N�̒����{���S�ʂɂ��s���Əh���Ƃ͏I�������B |
�A
�֏���
�������Ɩؑ]�߂���������B |
 |
| |
 |
�B
�ѐ�֏�
�ѐ�h�͒����͖k�̗v�ՁB�u������ؑ]�H�v�̔肪������R�ɂ͓����Ԃ��݂����Ă����B���̏h��̓�����ɂ���̂��ѐ�֏��B�L�b�G�g�̎���ؑ]�ޖ̊Ď��̂��ߓ�̍��Ĕԏ��Ƌ��ɐݒu���ꂽ�B�փ����̐킢�̌㕟���֏����ݒu�����Ƃ��́u���ցv�Ƃ��ďo�������߂�悤�ɂȂ����B�܂��k�̌����Ƃ��ċM�d�Ȗؑ]�w���g���č�����ȕ��⎽��A�؍ނ̖��ڏo�̎����܂���������˂́u�k�̔ԏ��v�ƌĂꂽ�B
�h�̖k�̓�����ɏ��a�T�P�N�i�P�X�V�U�N�j�ɕ������ꂽ�B�A���̏ꏊ�͏������ւ��Ă����Α��Ɉʒu���Ă����B�֏��͖����Q�N�i�P�W�U�X�N�j�ɏh�w���x�̔p�~�ɔ������̋@�\���~�����B |
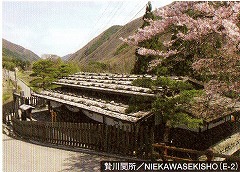

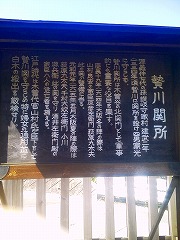 |
| ��ԏ� |
 |
| ���~ |
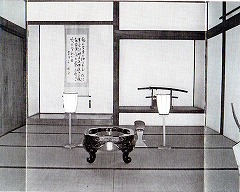 |
���ԏ�
�ѐ���ѐ�牷�����o�������Ƃ���Â��́u�M��v�Ə�����u�M��v�ƌĂ�ł����Ƃ����B |
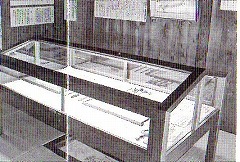 |
�ؑ]�l�Ê�
�ѐ�n����ʏ��Ղ��͂��߂Ƃ��鐔�����̈�Ղ��甭�����ꂽ�ꕶ�������璆������̓y��Ί�Ȃǂ�W�����Ă���B�܂���������̓y�t��E�{�b��E�D�ցi�����䂤�j����Ȃǂ̈╨���W������Ă���B |
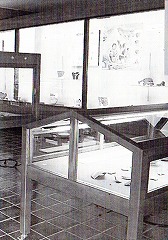
 |
�ዾ��
�����S�R�N�i�P�X�P�O�N�j�P�Q���̒��������S�ʎ��Ɍ������ꂽ�����K����̃A�[�`���B���a�U�R�N�i�P�X�W�W�N�j������p���Ƃ��Đ������ꂽ�B |
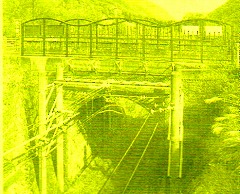 |
���^�[�|�X�g
�ѐ�X�ǑO�ɏ��a�Q�R�N�i�P�X�S�W�N�j�`�Q�S�N�i�P�X�S�X�N�j���ɂ�������i�Ƃ��Đ������ꂽ�Ǝv���钿�����|�X�g������B�Ђ����̏�̍��͗l�ƍ����o�����́u�k�d�sTER�v�̕���������̉��̓��������̂���B |
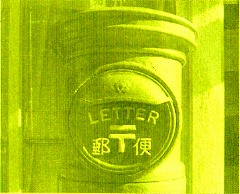
��ʓI�ȃ|�X�g
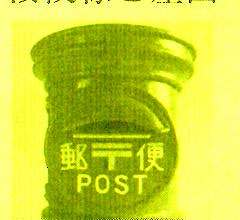 |
�C
�ω���
�ؑ]�J�ɂ�����c���Ă���^���@�̎��@�B���ʂ̎R��i���O��j�͎s�̗L�`�������Ɏw�肳��Ă���B |

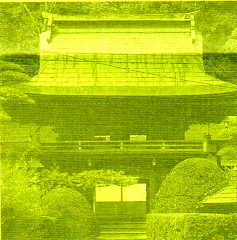 |
�D
����璐_��
�z�K�_�Ђ�{�ЂƋ��V�N�ɂP�x�i�ДN�Ɛ\�N�j�Ɍ䒌�Ղ�����s���
�����ɂ͎l�{�̌䒌�����Ă��Ă���B |

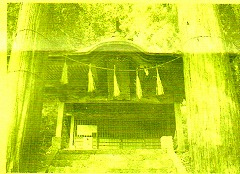 |
�d���Z��
�[�V�ƏZ��
�؍ȁA��d�o���B�Éi�V�N�̖ؑ]�Ɠ��̓`���I���Ƒ���B |

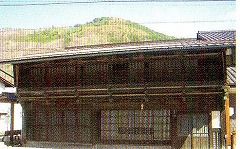 |
�E
�Ȃ̑��
(���w��V�R�L�O���B���a�S�S�N�i�P�X�U�X�N�j�Ɏw�肳�ꂽ�B)
�ѐ�h�쐼�̎R�ۂɐ������P�Q�O�O�N���錩���Ȏ��`�̓Ȃ̖B |


 |
���̋{�̂���
�}����� |
|
| �X�T�m�I�m�~�R�g |
 |
�F
�����̈ꗢ�� |
 |
���̖؈�{
�ꗢ�˂����������邵 |
|
|
| |
|
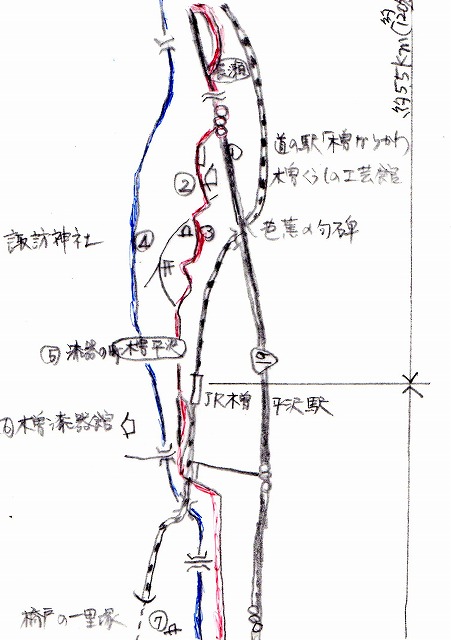
�ؑ]����ɂ���
�ؑ]����̐����͓`���Ƃ��Ē����������Ƃ����Ă���B�ŏ��̎����͊����T�N�i�P�U�U�T�N�j�́u�w���ʋl�o�v�Ƃ��������Ɂu�ʂ菬�ۂڂ�v�̐��i��������w���H�Ɏ���h��Ƃ������Ƃ��������ƍl�����Ă���B�ޗLj䂪�����𒆐S�ɔ��W�������Ŗؑ]����ł͖~��w���ɐ@������t�c�h���{�����i����ł������B���������ɎK�y�Ƃ������n�ނ��������ꂽ���Ƃɂ��傫���ؑ]���킪���W�����B����ɂ��{���n����̐��삪�\�ƂȂ�ؑ]����ɑ傫�ȋZ�p�v�V�������炵���B���̖{���n�����Ƃɂ��������Ȃǂ̋Z�p�̌��r�ɂ�菺�a�T�O�N�i�P�X�V�T�N�j�Ɂu�ؑ]�t�c�v�u�ؑ]�ς��h��v�u�h�蕪���C�F�h��v�̂R��̋Z�@�ɂ��ؑ]���킪���̓`���I�H�|�i�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�B |

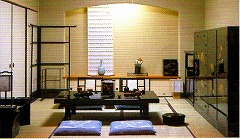
���푽�l�Ȗؑ]����

���s���䎛�ɓW�����ꂽ�ؑ]����̋���I�u�W�F |
| �ؑ]����� |
 |
�|��
���\�Q�N�i�P�T�X�R�N�j���������|�ʼn����������Ƃ��n�܂�Ƃ�����B |
 |
��s���镗�i
���R���������I�ɘp�Ȃ��Ă��邽�߁A�n�����X�H�ƒ��p�ł͂Ȃ��B����䂦���R�ƌ����͊�s���Č������ʂ��A�����Č����邱�ƂƂȂ�B�܂��X�H�ƌ����̋�n�͊����Q�N�i�P�V�S�X�N�j�̑�Ό�����˂ɂ��R�ڂ��Z�b�g�o�b�N������ꂽ���̂ł���B ���������L�͂����܂Ŏ��̂��́i�u����v�j�Ƃ����ӂ���A�K���`�ƌĂтȂ�킳��Ă���B |
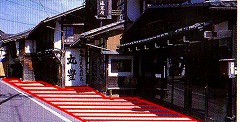 ��s���钬���݂ƃA�K���` ��s���钬���݂ƃA�K���` |
�d����Ƃ��Ă̑�
�y��������̍�Ə�Ƃ��Ďg���Ă���B������ɂ͎��x�Ɖ��x���d�v�ł���y���̓����͎��x�A���x�����肵�Ă��邽�ߍ�ƂɓK���Ă���B |
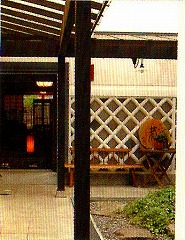 |
�~�n���ւ̒ʘH
�~�n�̉��̑��ɔ����邽�߂̒ʘH���̓h�W�i�ʂ�y�ԁj�������ǂ��瑤�̉Ƃ��쑤�ɂ���B |
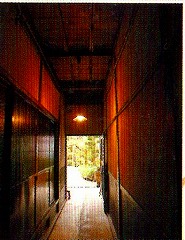
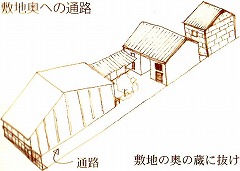 |
�e����̌��������݂���
�]�ˎ���̏o���������łȂ��吳���ォ���O�ɂ����Ă̌�������̌����ȂNJe����̓����I�Ȍ������������Ă���B |
|
| ��ΈȑO�̕��� |
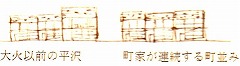 |
| |
|
| �����Ό�̕��� |
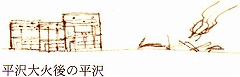 |
�����㔼
�؍Ȃ̏o�����̖ؑ]����ł͐����Ȃ����Č��z�B���ʗ��[�̒���ʂ����Ƃ����̊ԂɊԌ������ς��̓���������`���I�Ȍ`���B |
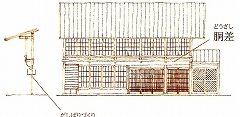 |
���������
��@�ɑ݂��Ă������ɓ��ꉮ�̃|�[�`��������ꑾ���i�q�����̎��t����ꂽ�Ƃ����B�쑤�ɉ��ɑ����ʘH������B |
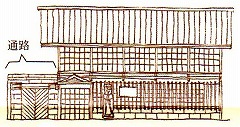 |
���������
�o���� |
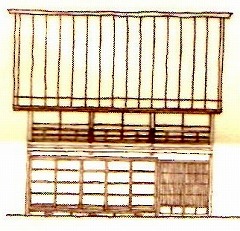 |
�J�~�m�N���i�����R�Q�N�j��
�V���m�N���i ���a�V�N�j
�J�~�m�N���ɂ͖����R�Q�N�̓��ؖ�������B���a�����̈ڒz�B�̑��Ɉ�A�̒u�����ł����߂Ă���B |
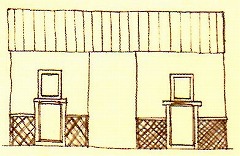 |
�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�N�j
�^�ɒʂ�y�Ԃ����������`�̌��� |
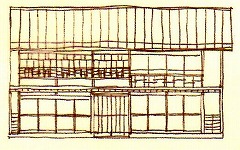 |
| |
|
| ���a�����̕��� |
 |
���a�Q�N�i�P�X�Q�V�N�j
�����^����ǂɃh�C�c�ǎd�グ�Ɠy���Ɨm���ӏ���ܒ����������B�����͓y���̂悤�Ȓu�����B |
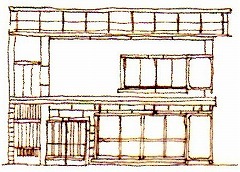 |
���a�T�N
�̎�Ƃɐ؍Ȃ̎��t���k���^�̉������������Ă���B�j�K�ɉ���������K�͂ȏ��X���z�B |
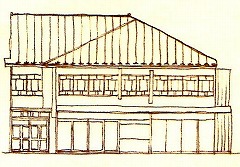 |
���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j
�ؑ]����ł͒������y�����\�ɂ���B�ʘH���쑤�ɂ���B |
 |
���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j
�ʏ́u�ʑ��v�����^���h��̗m�قɍ�����d�グ�̓y������̌��������������悤�ȊO�ς��ڂ����������B |
 |
���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j
�o�����̌����B���K�Ƃ��c�i�q���͂ߍ��ݐ��؍\���̏��݂������Ă���B |
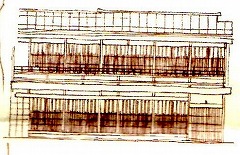 |
���a�X�N�i�P�X�R�S�N�j
���ꉮ�A�V�����̉����̏d���Ȉ�ۂ̌����쑤�ɉ��֑����ʘH������B |
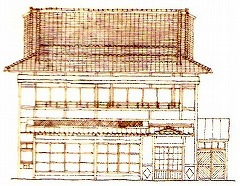 |
| |
|
| ���̕��� |
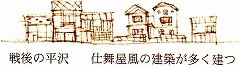 |
���ʂ͏��a�Q�O�N��ɑ��z
�o�����̌����ł��邪�j�K�̌��̏o�����������̏�ɏ��݂�t����ȂǐV�����v�f��������B |
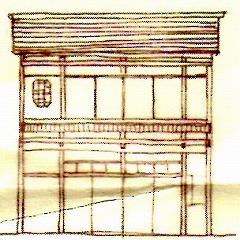 |
| |
|
| ���a����̕��� |
 |
���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j
�ؑ]����ōŏ��Ɍ��Ă�ꂽ��J�Α��B�߂̉��H���Ղ����@��ɂ����̂Ƃ킩��B�Ȗ،��F�s�{�s��J����S���Ɣn�Ԃɂ���ĉ^�ꂽ�ʼnF�s�{����H�������Č��z���ꂽ�B
|
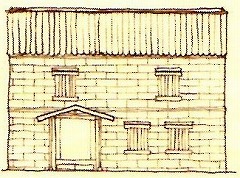
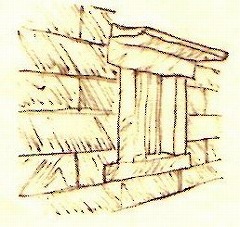 |
���a�R�T�N�i�P�X�U�O�N�j
�h�W��ʂ��ĉ��֍s���ƎO�K���̑�J�̑�������B |
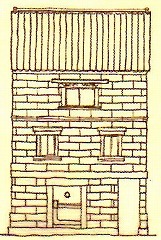 |
|
|
�P���ڂ̂S |
|
 |
�@
���̉w
�ؑ]�Ȃ炩�� |
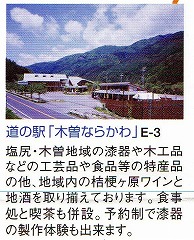
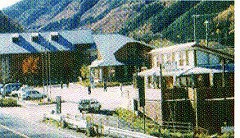 |
�A
�ؑ]���炵��
�H�|��
12:00���H |
 |
| �ɓ���R�L�_�� |
|
�B
�m�Ԃ̋��
�z�K�_�Ћ����ɗ��B�����N�ԂɕҎ[���ꂽ�u���R�����ԉ��G�}�v�ɂ͌��݂̏ꏊ���班���ѐ���ɕ`����Ă���Ƃ����B |
����������͂ăn
�ؑ]�̏H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�ȋI�s�@�@�m��

 |
| �������C���H�[ |
 |
| �����_�� |
|
| �����_�Ђ̗N�� |
|
�C
�z�K�_��
�{�a�͓V���P�O�N�i�P�T�W�Q�N�j�̕��c�����Ɩؑ]�`�N�̍���ŏĎ��B���ۂP�V�N�i�P�V�R�Q�N�j�ɍČ����ꂽ�B���ʂ͍Ղ�̂Ƃ��̂��邱�Ƃ��ł���B�O���̕�������r�I�Â������ɂ͕ǂ��Ȃ��̂Ŗ{�a�̑��ʂ����邱�Ƃ��ł���B |
���c�����̖ؑ]�U�߂̖{�w�ƂȂ����B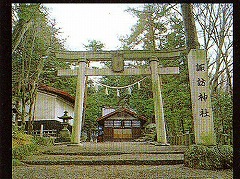

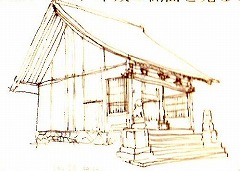 |
| �z�K�_�Ќ䒌 |
 |
�䒌��
�z�K��ЂɂȂ炢�V�N�ڂ��ƂɌ䒌�Ղ��J�Â���Ă���B |
 |
| �{���_�� |
|
| �z�K�� |
|
�D
���H��
�ؑ]����
�ؑ]����͌c���R�N�i�P�T�X�W�N�j�ɓޗLj��̍��݂ɂ����������E�݂ɕt���ւ���ꂽ���Ƃ��_�@�Ɏ��ӂ̎R�ѕt�߂ɐ������Ă����l�X�����̓������ɋ��Z���邱�ƂŏW�����`������Ă������ƍl�����Ă���B���̓��͌Ñ㒆���ł͋g�h�H��ؑ]�H�Ȃǂƌ����Ă��������얋�{�ɂ���Ē��R���̈ꕔ�Ƃ��Đ������ꂽ�B�ߐ��ɂ͓ޗLj�h�̍��Ƃ��Ĉʒu�Â����w���H����̐��Y�Ő��v�𗧂ĂĂ����B�ؑ]����̐����d�v�ȑf�ނ̈�ł���ǎ��ȎK�y���m�ۂł������Ƃ��疾���̏��ߍ�����Y�ƂƂ��Ă̊�Ղ��m�������H���Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�吳�P�R�N�ɂ͐V���ȊX�H�����R���̐����ɒz����������Ƃ��Ċg�債���B���{�L���̎��퐶�Y�n�Ƃ��ĔF�߂���ؑ]����͎��H�Ƃ����`���H�|�̐E�l���Ƃ��ĕ����P�W�N�ɑS���ŗB�ꍑ�̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳�ꂽ�B |
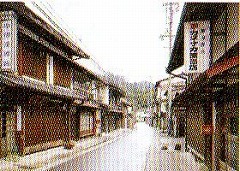
 |
�E
�ؑ]����� |
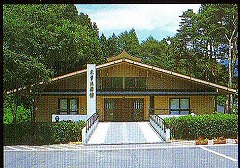
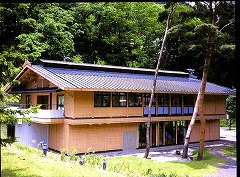 |
| �f�X�W����~�G�I�����s�b�N���܃��_�� |
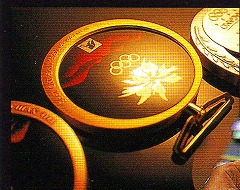 |
|
|
| �o���_�� |
|
| ����_�� |
|
| �����q�_�� |
|
| ���R�_�� |
|
| �쌴��א_�� |
|
| ��Ԑ_�� |
|
| ���ˑ�R�L�_�� |
|
�F
���˂̈ꗢ��
�ꗢ�˂͌c���X�N�i�P�U�O�S�N�j�ɍ]�˖��{�̖��ɂ��ꗢ���ƂɊX��������łQ��ݒu���ꏼ��|���A����ꂽ�B |
 |
�ؑ]��쏬�w�Z
��쏬�w�Z�̋��H��Z�b�g�͎��̊킪�g���Ă���B |
 |
| �����@ |
|
| |
|
|
| |
|
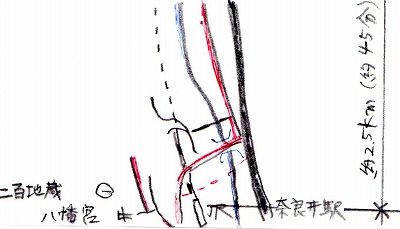 |
| |
�P���ڂ̂T |
��S�n��
���̎��ӂɂ������ω��l��n���l�̐Ε������킹�J���Ă���B |
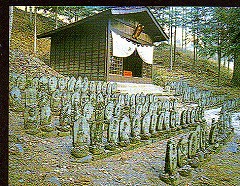 |
| �����̈ē��� |
|
�����R��
������
���̋����\���{���ԌÓ��B |
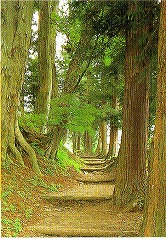 |
| �����{ |
 |
�ޗLj�w
�P�T�F�P�O |
|
|
| |
|
| �Q���� (�����Q�T�N�P�O���P�T���Ηj��) |
�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�R����) |
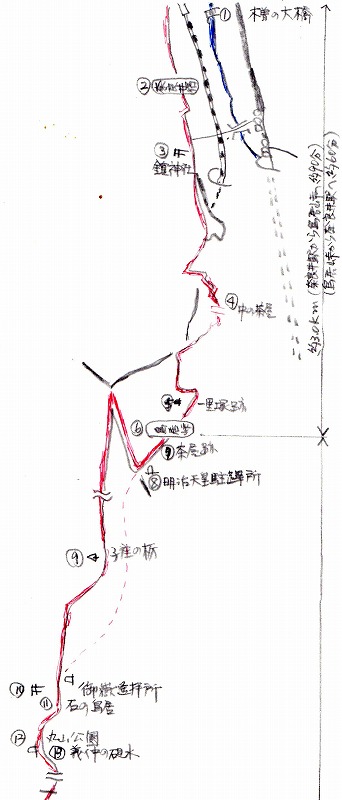
| �����ƌ��z�N�� |
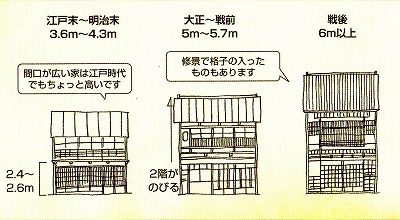 |
| �����̐��ʈӏ��ƕ������� |
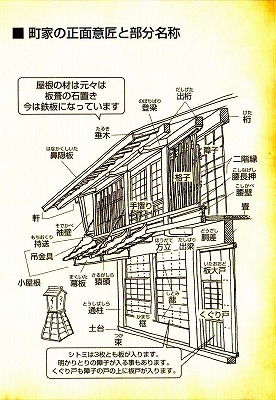
| ���� |
�����̍ނ͂��Ƃ��Ƃ͔��̐Βu���B���͓S�ɂȂ��Ă���B |
|
| �� |
|
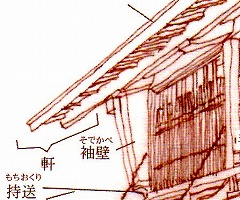 |
| �ԉB�� |
|
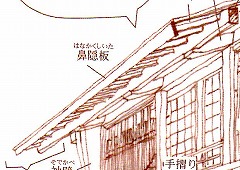 |
| ���� |
|
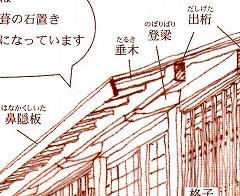 |
| �o�� |
|
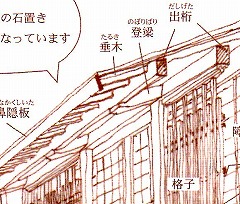 |
| �o�� |
|
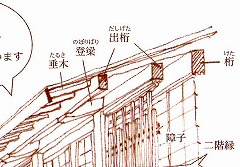 |
| ������ |
�������A���ǂ�������
�V�ۍ��̌��z�B |
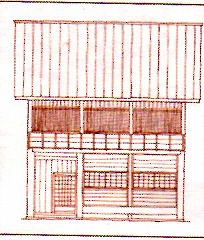 |
| �݂���� |
|
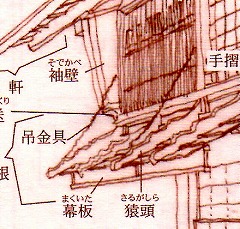 |
| ���� |
|
 |
| ���� |
|
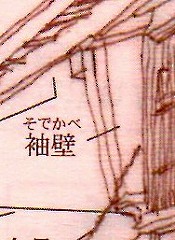 |
| ���� |
|
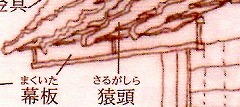 |
| ���� |
|
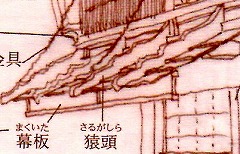 |
| �萠�� |
|
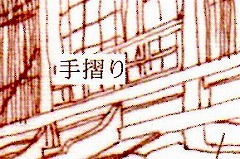 |
| �i�q |
���������̌��z�B���ʂ͂P�K�Q�K�Ƃ��Ɋi�q���ڂ������B���ʂ������I�ȋߐ�����ŋ߂܂ő������������B |
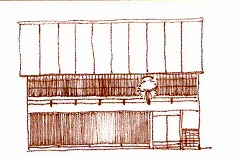 |
| ��q |
|
 |
| �j�K�� |
|
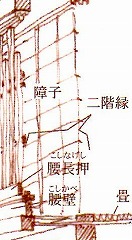 |
| ������ |
|
 |
| ���� |
|
 |
| �� |
|
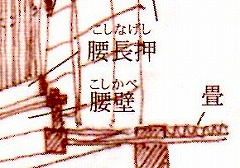 |
| ��� |
|
 |
| ������� |
��q�̌˂̏�ɔ˂�����B |
 |
| �o�� |
�V�ۂW�N����P�S�N�i�P�W�R�V����P�W�S�R�j�̊ԂɌ��z�B�Ԍ����������ɐ[������œޗLj�̒��Ƃ̓T�^�B�o�����ɂȂ��Ă��Đ��ʂ͎�������B |
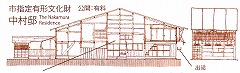 |
| ���� |
|
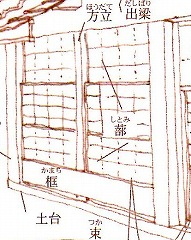 |
| ���� |
|
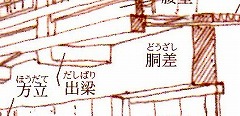 |
| �� �i���Ƃ݁j |
�R���Ƃ�������B������Ƃ�̏�q�����邱�Ƃ�����B
�P�K���ʂ͎��Ƒ�˂ɂ�����˂��c����Ă���B�V�ۍ��̌��z�B |
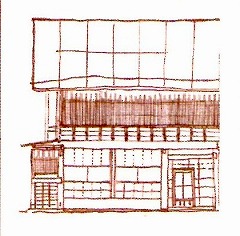
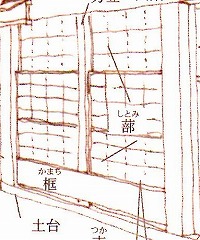 |
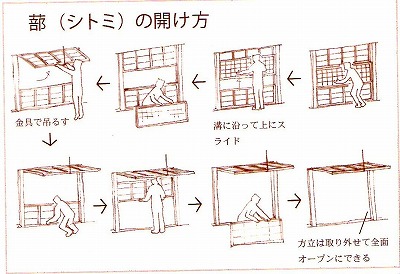 |
| �y |
|
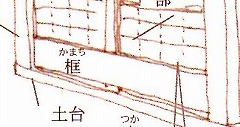 |
| �ʒ� |
|
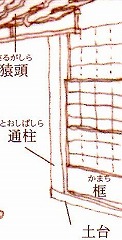 |
| �y�� |
|
 |
| �� |
|
|
|
| �ޗLj䎁���ِՒn |
|
�@�R��
��y�@�̎��@�B�փ����̍���Ɍ������r������G�����ꎞ�؍݂��w���Ƃ��Ďg�p�����Ƃ̋L�^���c��B |
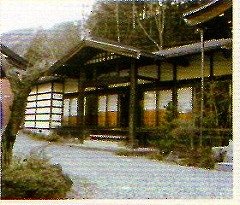 |
| �ޗLj�`����n |
|
���
�ؑ]�H�����_���V�l�B�V���P�O�N�i�P�T�W�Q�N�j�ޗLj�`��������̕�Ƃ��ĊJ�����̂��n�܂�Ƃ����B�ՍϏ@���S���h�̎��@�B |
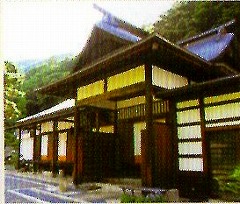 |
���
�}���A�n��
���a�̏��ߏZ���ɂ���ċߗׂ��M�̒����甭�����ꂽ�B������L���V�^���������ɋF�邽�߂ɍ�������̂Ƃ������Ă���B
|
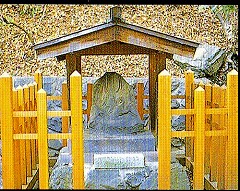 |
| �_���{ |
|
����
�����@�̎��@�B����ƌ��ɂ��n�߂�ꂽ�F�������]�˂ɉ^�ԁu�����ٓ����v�̏h�����Ƃ��Ė��N�g�p����Ă����B |
 |
��
�ޗLj�܃����̂����ł���ɂ���^�@��J�h�̎��@�B�����ƐΈ�ߎO�͂��̎��œ����ؒ����𐧍삵���B |
 |
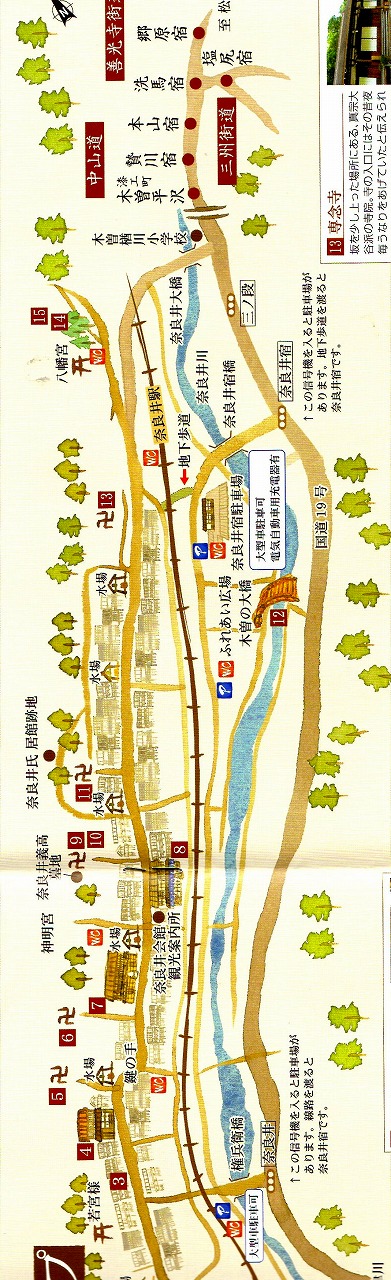

|
| |
�Q���ڂ̂P |
�ޗLj�w
�W�F�S�T
�����S�Q�N�i�P�X�O�X�N�j�J�ƁB�g���X�����g�݂̉������������Ă���B |
 |
��R�S��
�ޗLj�h |
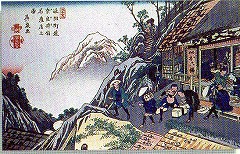 |
| �ޗLj�h��܂� |
 |
��O��
�^�@��J�h�̎��@�B���̓�����ɂ͂��̖̐閈���Ȃ�������Ă����Ƃ����u���Ȃ�v������B |
 |
| ���� |
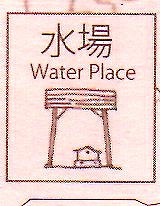 |
����
��O���������������j�K�ɑȉ~�̑�������B���̎���̑��ɂ͂ق��ɔ���`��~�`�Ȃǂ�����B |
|
�@
�ؑ]�̑勴
����R�O�O�N�ȏ�̑��q�m�L����B���r�̂Ȃ����Ƃ��ėL���̑傫�����ւ�B |
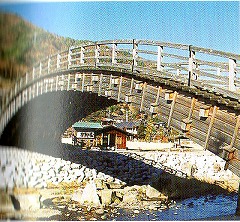 |
| ���� |
|
�A
�ޗLj�h
�ؑ]�H�͌×���ʂ̗v�ՂƂ��ĉh�����B�ؑ]�H�̒��ł��ő�̓�ł��钹�����̖k�Ɉʒu���y���ޗLj䎁�����ق����܂����ޗLj�̒n�͌�ʂ̂��Ȃ߂ƂȂ�h�Ƃ��Ĕɉh�����B�c���V�N����ƍN�ɂ�蒆�R���̏h�w����߂��ޗLj�h�����{�W�҂Ȃnj��p���s�҂�Q�Ό��̑喼�ʍs�̂��߂ɐl�n����������B�܂��ߐ��ޗLj�͞w���H�A�h���A�����Ȃǂ̖؍H�Ɩ����ɂ���đ����̎����Ă����B�ؑ]�J�̏Z���ɔ����˂�艺�����ꂽ���،�ƖU�O�O�O�ʂ̂����S���̂P�̂P�T�O�O�ʂ��ޗLj�ɓ��Ă��Ă��萶�Y�ʂ��Q���Ă����B�ޗLj�͋ߑ�ȍ~����Ȃ��������Ƃ���]�˖����̌`���𑽂��c�����������c���Ă����B�n��Z���̒����݂ɑ���M�ӂƏh�꒬�̓��F���F�߂�ꏺ�a�T�R�N�ɍ�����d�v�`���I�������Q�ۑ��n��̑I������B |
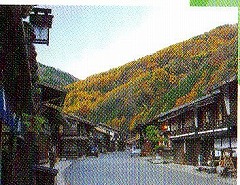
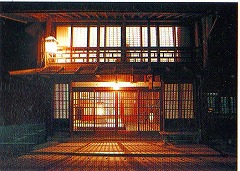 |
��ˉƏZ��
��≮
�j����
�V�ێ���̒��ƌ��z�B�c���V�N�i�P�U�O�Q�N�j���疾������Ɏ���܂œޗLj�h�̖≮���Ƃ߂Ă�����ˉƏZ��B���̏d�v�������B |
 |
�����@
�����̖≮���c��ł��������Ƃ̏Z��B�V�۔N�ԁi�P�W�R�O�N����P�W�S�R�N�j�̌����j�K����������o������o�����A�Z�݂ȂǓT�^�I�ȓޗLj�̖��Ƃ̗l�����c���Ă���B |
 |
���Ђ��܃��P�n
�ޗLj�h�͕����Q�R�N�x�m�g�j�A���e���r�����u���Ђ��܁v�̎B�e�n�Ƃ��Ďg��ꂽ�B�h��͖�Q�O�O���i���̎�`���_�Ђ̊ԁj�ɂ킽���|����ȃZ�b�g���g�܂ꏺ�a�����̒����݂��Č����ꂽ�B |
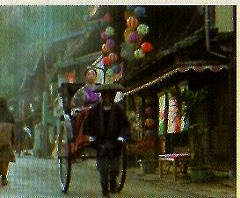 |
�M�Z�H
���R�V���� |
|
�W�����{
�J���}�c
(���w��V�R�L�O��)
�ؑ]�J�ƈɓߒJ�����Ԍ����q������ѓ�����������L�тɓV��˂��������Q�T�O�N�̋����͓��{�ő�Ƃ����Ă���B |
 |
������
���a�����܂ŗ��ĂƂ��Ďg���Ă����B�s�̗L�`������
�V�ۍ��̌��z�B |

���y�قƂ��Č��J |
| ��{�l |
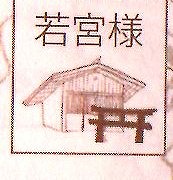 |
�B
���_�Ђ�
���D��
�ޗLj�h�̒���B���Ƃ��ƒ������Ɍ�������Ă�������ŏĎ����ޗLj�`���ɂ���Č��݂̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ�����B |
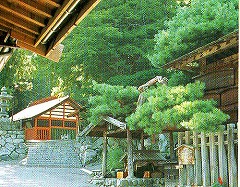
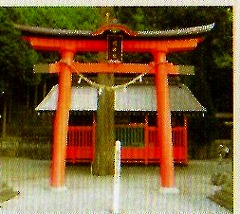 |
| ���_��� |
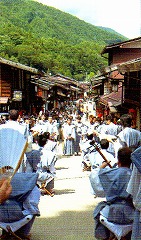 |
| ���D�� |
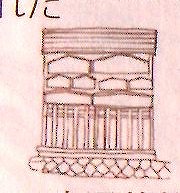 |
�����j����������
���蓡�����u�����v�ɂ��������ԋ��̌��^�ł��鎽����h��ŗ��ʂ��������̏h�D�Ȃǂ�W�����Ă���B |
 |
�C
���̒��� |
�e�r���́u���Q�̔ޕ��Ɂv�̕��� |
�F
�������@������ |
 |
| ��ԎR�̗�_�� |
|
�D
������
�ꗢ�ː� |
 |
| �������Ɏc��Ώ� |
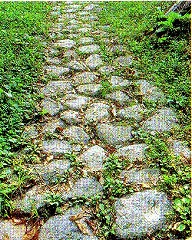 |
| ���R�� |
 |
�G
�����V�c
���J���� |
 |
�H
�q�Y�݂̓� |


�ؑ]�̓Ȃ������̐l�̓y�Y���ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�� |
| �Ȃ̖،Q |

 |
�E
������
�ؑ]�`�������{�̏��}�����Ɛ�����Ƃ���Ԃɐ폟���F�肵���������߂��̂ł��̋L�O�ɒ����𗧂Ă����Ƃ��璹�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B |

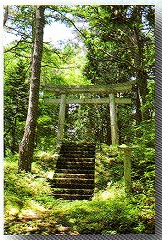

|
�I
���ꡔq��
��Ԏl��
�k�@������
��@���ꑺ��
�O�Y�R
���@�ؑ]���J�c������
������
���@�ؑ]�������i���⋽���j�̐_�� |

 |
�J
�̒��� |
 |
| ��Ԑ_�� |
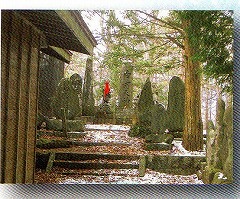
 |
�G
�ێR���� |
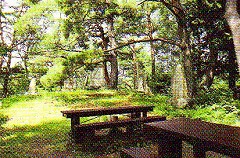 |
| ���������� |
|
| �m�ԋ�� |

�Ђ����ɂ₷�낤������ |
�L
�`������ |

 |
|
| |
|
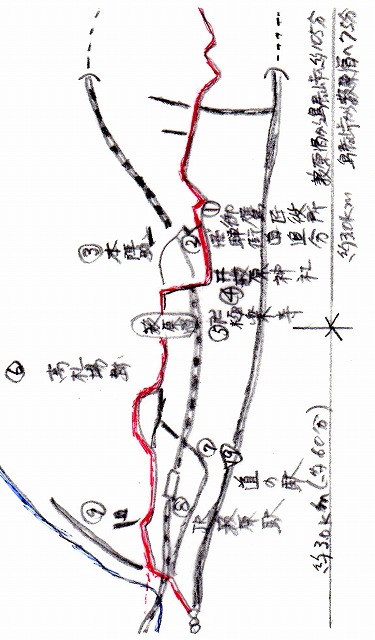

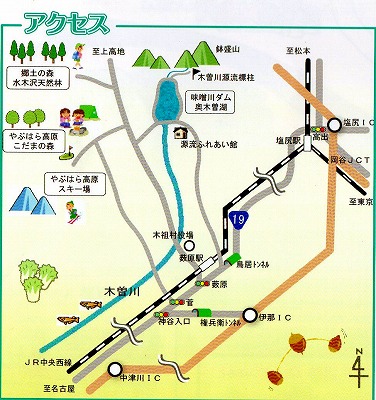
| |
|
���X��_��
���ؑ]��
�ؑ]�쌹���ɂ���_���� |


 |
| ���X��_���h�Ў����� |
 |
| ���̉�L |
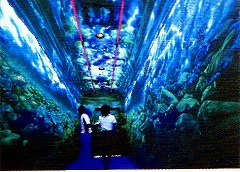 |
���ؑ�V�R��
�i�ؑ]�����ؑ]�j
����Q�O�O�N����ؑ]�w�ȂǂɍL�t������������X�ю����B�u�����̖����S�I�v�ɂ��I�肳��Ă���B |
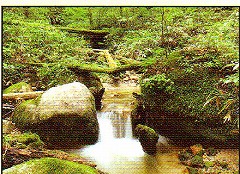
 |
�����̑�
(�ؑc�����ؑ])
�ؑ]�쌹���̎x���u������v�ɂ����B�����Q�O���ŊK�i��ɗ��ꗎ����P�O�O���̈ꖇ�������悤�ɗ����u�����̕����v�ւƂȂ���B |
 |
| �����܂̐X |
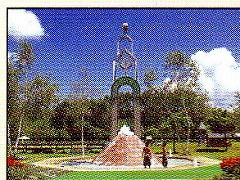
 |
| ��Ԃ͂獂���X�L�[�� |
 |
�c�m��ω�
�i�ؑc���E���ؑ]�j
�ؑ]�O�\�O�ԎD���̂�����ܔԎD��
���O���̊������̓��B�����̎}�����͖ؑc���V�R�L�O���B |
 |
��t���̍�
(�ؑc���E��) |
 |
�����_��
�o�_��Ђ̕��ЁB���{�ŗB��u�����v�̖������_�ЁB |
 |
|
|
2���ڂ̂Q |
�V �n���ω�
�����Q�S�N�����̕� |
 |
| |
�����̂�ł͐����Ȃ��߂Ă�
�ؑ]�͉Ԃ����� �i�R���j |
�@
��鏠������ |
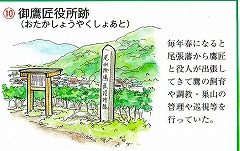 
 |
�A
��ˊX���Ǖ� |
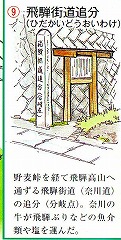 |
�B
�{�w�� |
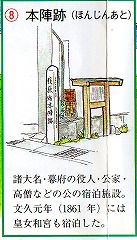 |
�C
�M���_��
����10�N�ɗ���a�l�Y�x�������݁B
�Â��͌F��ЌF���_�{�Ə̂��ꂽ������4�N���M���_�ЂƉ��̂����B��?���т̓�������ѓ����q�̒���������B |

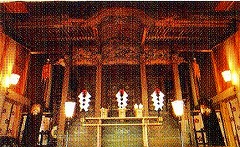
 |
| �M���_���� |
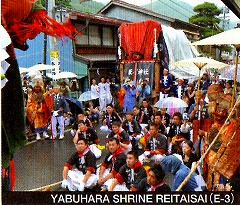 |
�D
�Ɋy��
1550�N��̑n���Ɠ`������ՍϏ@�̌Ù��B�ω����̓V��ɂ͏C�{�ɖK�ꂽ�A�����M�h�̉̐l�������c�����悪����B�����ȗm��Ɠ��c�k����ߓ��_��H�̉������B���B���̒뉀������B |

 |
�{���
������ |
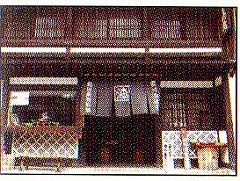
 |
��R�T��
�M���h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�P�O�� |
 |
| �M���h�̒��� |
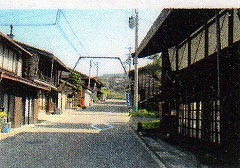 |
| ���Z���̓X |
 |
| ���Z���Y�n |
���l�ɂ��̏����͕������
�ؑ]�H�͂����Ǝw���ċ�����
���c�쐤�i冎R�l�j
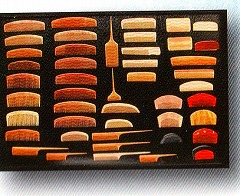 |
| �h������ |
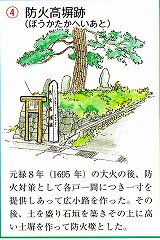 |
�E
���D��� |
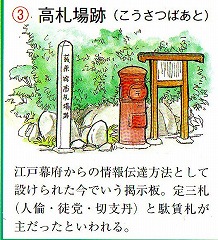 |
�F
���̉w�ؑ]�쌹���̗�
�����ނ� |
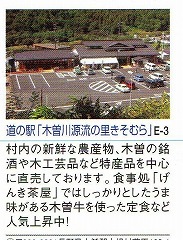
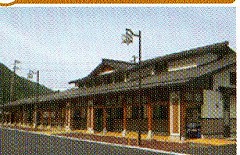 |
�ؑc��
���y�� |
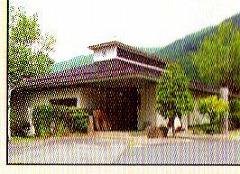 |
�G
�M���w
�P�Q�F�O�O
���H |
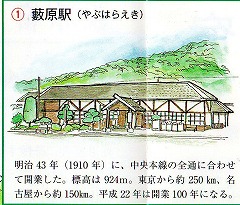
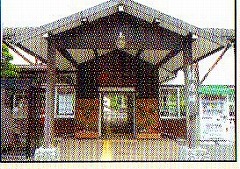 |
�H
�ꗢ�ː� |
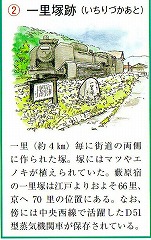
 |
| �ؑc���؍H�����Z���^�[ |
 |
|
| |
|
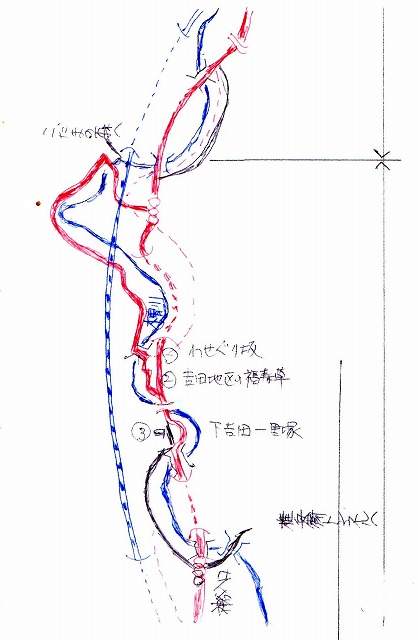
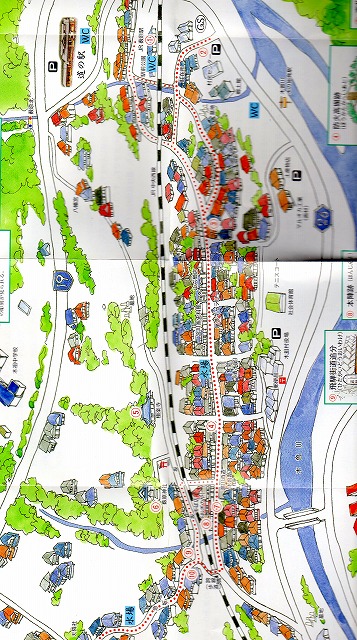 |
|
�Q���ڂ̂R |
| �ߍX���_�� |
|
| �g�c���̑�� |
|
| �g�c���� |
|
�@
�킹����� |
|
�A
�g�c�n���
������ |
 |
�B
���g�c
�ꗢ�� |
|
| �R���g���l�� |
|
|
| |
|
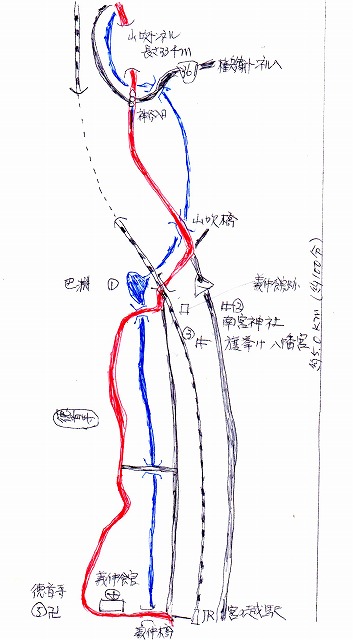
�_�J�z�K�_��
�n���N�͕s���B�����q�X�������̐_�J�ɎY�y�_�Ƃ����J���Ă���B���Гa�͖����\���N�i�P�W�W�S�N�j��J�ɂ��_�J��y�ё�̍^���̂��ߗ��o���Ă��܂����̌㌻�݂̏ꏊ�ɍČ����ꂽ�B �����̏��߂Ɋe�n�̎Ђ͓�{�_�Ђ֓������邱�ƂɂȂ������S���čs���r���̐�z�̏��ŋ}�ɏd���Ȃ��Ă��܂����̂Ő_�l���{���ē����Ȃ����̂��ƈ����Ԃ����̏ꏊ�֖߂��������ł���B |
 |
�������n��̂���חl
�{�m�z�������n��̗��R�ɂ����̐Ԃ��������������ēo�����Ƃ���Ɉ�א_�Ђ��J���Ă���B�����E�̐ΐς݂̏�ɂ͔n���ω���얳����ɕ��������E�����Ⓦ�������{��������ł���B�Βi�̗����ɔn���ω��̕����肪�����邪�E���̔�́u�n���ϐ�����F�E��������@���v�ƍ��܂ꍶ���̔�́u����@���n���ω��v�ƍ��܂�Ă���B����@���͋��̔w���ɍ����Č���邱�Ƃ��狍�̎��_�Ƃ���Ă����B�n���ω��Ɠ����悤�ɋ��̋��{���Ƃ����J��ꂽ�̂��Ƃ����B |
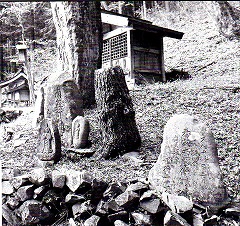 |
�������̔n���ω�����
�Βi�̐��ʂɂ��������蒆�ɂ͔n���ω����������߂��Ă���B���ʂ��猩��Ɠ����ɂ���͂��̔n�̊炪�݂��Ȃ������̏�ɕ��ɂȂ��ĕt���Ă��Ĕn���ω��ł���Ɗm�F�ł���B |
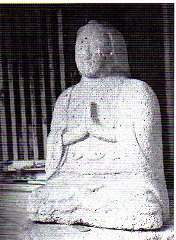 |
| |
|
�����q�X��
�Ă̖R�����ؑ]�J�Z���͈ɓߒJ���璲�B���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������̂͒������⋍�A���K�����z���đ��肷�邵����i���Ȃ������B�����Ő_�J�ŋ��������Ă����Ô������q�͉W�_���Ɠ�|�����z����ߓ��̉��C���v�����㊯�̓��ӂĖ≮�̋��͂̂��ƍ����ˎ�̓��ӂ邱�Ƃ��ł����B��N�Ԃ̓�H���̌㌳�\��N�i�P�U�X�U�N�j�ɓ�\�l�L���̓��H���������V���������q�X���ƌĂѓ�|���������q���ƌĂԂ悤�ɂȂ����B
�����\���N�i�Q�O�O�U�N�j�����q�g���l���J�ʁB |
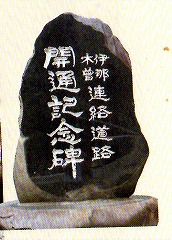 |
�W�_���̌����l
�_�J�n�悩��H���n��ւ̓����W�_���Ƃ����B���ŐU��Ԃ�ƌ�ԎR��]�ނ��Ƃ��ł��H���n���ꡔq���ɂ͒�����Δ肪�J���Ă���B |
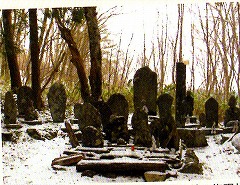 |
�n����
�������獂�R�ւ̊X�����ˊX���ƌĂђn�����͍ő�̓�ł������B���ɓ���̑��̎R�̐_���͋}�s�ŋ�J���������Ă����B���̂��߈����Z�N�P�W�T�X�N�ɂ��̓���I�邽�ߑ��̒f�R��ǂ��@�킵�ĕ���ȓ��������������B������������V����n��Ȃ����������낷�X�������_�̊댯�ȓ��ł������B���a�����ɂ悤�₭�ԓ������������n�����W�]�䂩�璭�߂��ԎR�͍ł��ϐ��̎�ꂽ�p�Ƃ�����B�B
|
|
���쓻
���a�Q�O�N��ɂȂ��ċ㑠����ʂ�I�H�̌v�悪����܂ł͐��쓻������Ă����B�q�ǂ��������w�Z�֒ʂ��ʊw�H������������������B�������ւR�O�O���[�g���̏��ɂ��т������Ă���R����R�ŕW���P�S�Q�Q���̎R�ł���B�퍑����͍Ԃ������ː��̐N��������ƘT���������ĕ����֒m�点�Ă����B��������_���̐Δ�Ȃǂ��J���Ă���B |
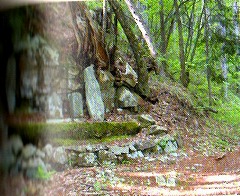
���쓻�̐Δ�Q |
������
���쌧�Ɗ��̌����ɂ��铻�B���a���N�i�P�X�Q�U�N�j�ɕ����҂��Œ��H�����������R�����펞���͋ΘJ��d����g�D���Ēn�����̊J��������a�S�P�N�i�P�X�U�U�N�j�t�ɂ悤�₭�������܂œ��H�����������B |
 |
���˓�
�����S�R�N�i�P�X�P�O�N�j�ɓS�����J�ʂ��Ă���͓��H�������i�݃o�X�ʍs���n�܂���������܂ł͌�e���̕��獇�˓����z���č���ɔ����Ă����B���ɂ͒��������荇�˓�ꡔq������̌�ԎR�W�]�͑f���炵����_����J���Ă���B |
 |
| |
|
| |
|
|
|
�Q���ڂ̂S |
�ؑ]��
�ؑ]���́u���{�ōł����������A���v�ɉ������Ă���B |
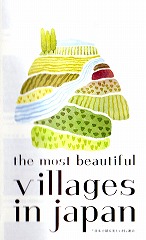 |
| �����`�� |

 |
| �R���R |
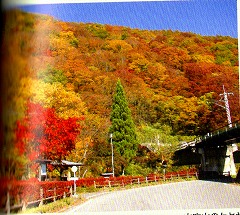 |
����ۂ���
�ؑ]�`���̊��g���n���`�n��ł͖��N�W���u����ۂ���v�Ƃ����ؑ]�`�������Ղ������B�R���R���珼�����������č~��Ă��镐�ҍs��͒������s�i���`�����̕�Q�������B�����͔b���ۂ̉��t���s���B |


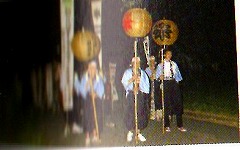 |
�@
�b���� |

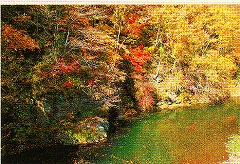 |
�A
��{�_��
�`�����Y�y�_�Ƃ��ĉ��c�_�ЁE���c�_�ЁE����_�Ђ���O�_�Ђ����B���{�����̕����������{�_�ЂƏ̂��ꂽ�B�`���̎���O�_�͏�B���J��ꂽ���ߔ��Z�i���s�j�S�j��{����̓�{�_�Ђ�����R�F�V���i�V�Ƒ�_�̌Z�_�j�Ђ����B�n���N�����͕s���B�����ɂ͏\��Ђ��J���Ă��ĉ����t���o��i�y�U�j������B�O�Ɏ�h��̖̒������̎��ɐ̒���������q�a�E�{�a�Ƃ����w����B |
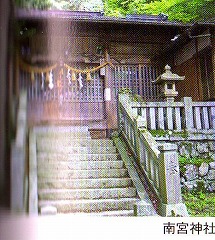 |
��{�_�Ѝ�
���ǂ���͒������s��Ŕh��Ȉߑ��𒅂�����҂������X�����̒������Ƃ��M�b�V�M�b�V�Ɨh�蓮�����p�͑s�ςł���B�s��Ƌ��ɉS���钷���S�͏j���S�Ƃ��Ēn��ɍ��t���Ă��艃�ȂȂǂł悭�S����B |
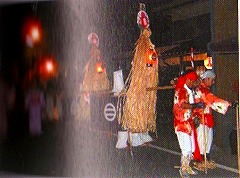 |
| �`���ِ� |
|
�B
���g��
�����{
�c������ۂƖ��t�����{�����������Ɉ�Ă�ꂽ�ؑ]�`�����͂��̂�����̕��n�ɏ���\�������{���J�����Ɠ`�����Ă���B�P�R�ɂ��Č����A�ؑ]���Y�`���Ɖ��ߍ��q�̋{�i�Ȑm���j�̗ߎ|�����莡���S�N(�P�P�W�O�N)���R���]�������œ|�̊��g�����������B���ɋ`���Q�V�ł������B |

 |
���g��
�����{��
��O
���`�ɂ͌Â�����`���̎��{�O�ƌĂ��O�̋����������B����������̂͊��g�������{�̋����ɂ���O�݂̂ł���B��_�ł����O�͕����P�S�N�̔_�w���m�ł������ł���l���l���̒����ɂ��Ƌ������͂P�Q��������R�O�������W�O�O�N�Ƃ��ꂽ�B�����ɂ�菝����ꂽ��O�͉����ƕۑ��̂��ߕ����P�S�N�R���ɂ��̐����͂��}�P�{�ɂ����邱�ƂɂȂ茻�݂̌�p�ɕς�邱�ƂɂȂ����B
|

 |
�C
�`����
�������R�u�ؑ]�`���v�̔g���ɖ������Z�����U���G��ɂ��ēW�����Ă���B |
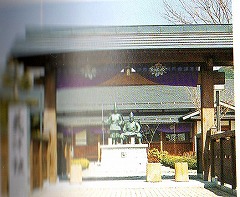 |
�D
������
�ؑ]�`���̕��
�ؑ]�H�����_
������V
�������͌��������Ƃ����`���̋F�菊�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�B����N�i�P�P�W�S�N�j�`�������Âœ���������S�M�ł�������v�V�o�����`���Ƃ��̈ꑰ�̗���J��`���̖@���u�������a�`�R����勏�m�v��蓿�����Ƃ����Ɠ`�����Ă���B�J�R�����R�ؑ]�`������勏�m�Ƃ����B�ŏ��͐^���@�ɑ����J�R�͉~����苗��B�O��͋��ۂW�N�i�P�V�Q�R�N�j���R��听�����l���K�̕ꓰ�̊�i�ɂ��B�R�ۂɂ͋`���E���}��O�E�b�E���䌓����̕悪����܂��|����������Ă��ċ`���|�����J����Ă���B |
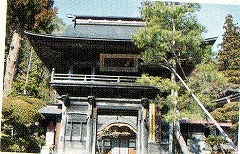
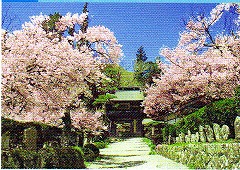

 |
| �������̋`������n |
 |
�ؑ]���i
�������̔ӏ� |
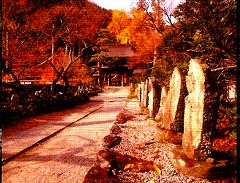 |
�ؑ]�`���ё���
�i�������j |
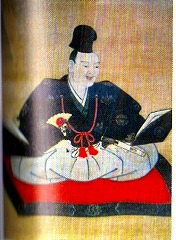 |
�b��O�ё���
�i�������j |
 |
�ؑ]�`���������܂�
�i����ۂ���j
�q�ǂ��������������S���Ȃ���ؑ]�`�����̕�Q������铿�����̍s�� |

 |
�{�m�z�w
�P�T�F�Q�O |
|
|
| |
|
| �R����(�P�O���R�O���@���j��) |
�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��X����) |
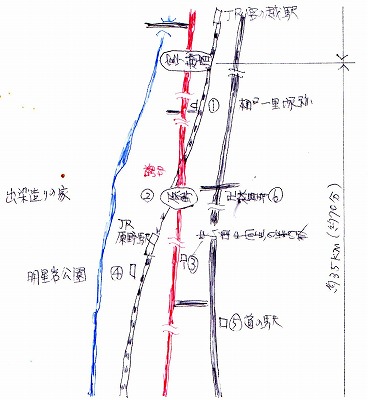 |
|
�R���ڂ̂P |
�{�m�z�w
�X�F�P�T |
|
��R�U��
�{�m�z�h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�Q�S�� |
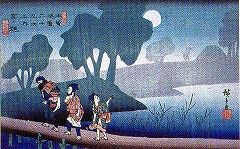 |
�@
�{�m�z�ꗢ��
�]�ˎ��㏉�߂Ɉꗢ���Ƃɒz���ꂽ�ˁB�y������ɉ|�⏼�Ȃǂ��A����ꂽ�B�ؑ]�H�ɂ͂Q�Q�J�����肻�̂����ؑ]���ɂ͋{�m�z�E�o�K�E�����̂R�J��������Δ肪���Ă��Ă���B
�̂̐l�͒j���ň���ɂX�������łT�`�U���������Ƃ�������]�˂��狞�s�܂Œj���Ȃ�P�S������P�T���ŕ������悤�ł���B |
 |
�A
�o����
�h�꒬�Ɠ��̏o�����Q�K���Ă̒����݂��c���Ă���B�{�m�z�͖ؑ]��H�̑����y�n���ł��������ߍׂ��Ȋi�q�〈���Ȓ������{���������肪�����B |
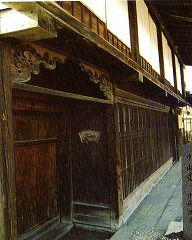 |
�{�w��
�{�w�͌�����N�i�P�W�U�T�N�j�ɍČ����ꂽ�����ł������������\�Z�N�i�P�W�W�R�N�j�ɑ�����������ߏĂ��c�����ޗ����g���Č��Ă��`�Ղ�����B |
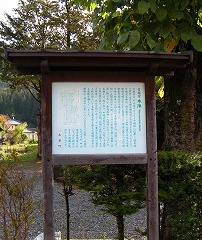
 |
| �e�{�w�� |
 |
�����V�c
��V�� |
 |
���씪���{
���D�y�ьËL�^�ɂ��Όc���O�N�i�P�T�X�W�N�j�ؑ]�Ƃ̋��Ɛb�炪���������싽�̎��_�Ƃ��đn�������Ƃ���Ă���B��Ր_�͗_�c�ʖ��A�{�a���ɂ͐_�����j�̂���B�{�a�̗����ɓƗ�����?�i�����j������B�����͗��������Ɩ��_�����B |
 |
�E
�я���
�n���R���͋v���N�ԁi�P�P�T�S�`�P�P�T�T�N�j���������̑n���ɂ��Đ^���@����R�n���@�̖����ɑ����Ƃ���B�c���Q�N�i�P�U�S�X�N�j�T�@���S���h�̑m�k�`�Ȃ���̂��s�͂��čċ������B��n�ɂ͒��������̕������B |

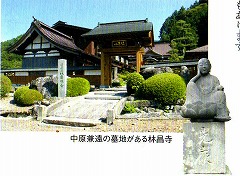 |
| ��߂��ɂ͎牮�厡��̐Ε���������B |
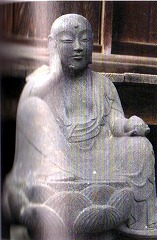 |
��������
�̕� |
|
�B
���R���̒��ԓ_�̈ē��� |
 |
���R����
���ԓ_
���̉w���`�ؑ]����ɂ������ |
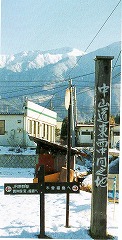 |
�C
���������
���猩�閾����
�ؑ]�`���Ɣb��O���n�ŋ삯�オ�����Ƃ����B |
 |
| ������ |
 |
�D
���̉w���`
�ؑ]��� |
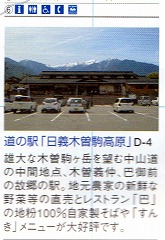
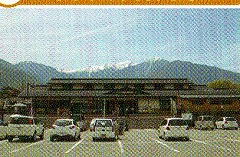 |
|
| |
|
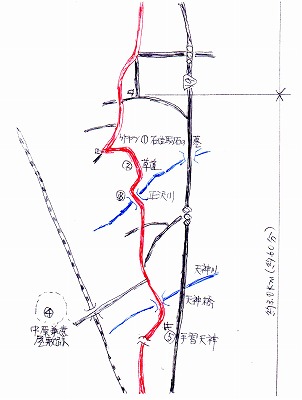
�匴�z�K�_��
�V�J�匴�����ɂ���n���͕s���B�㉮�a�͑吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�N�j�����B�Γ��Ăɂ͓V����N�i�P�V�W�Q�N�j�V���ƍ��܂�Ă���B�����l�N�i�P�V�X�Q�N�j�ɍċ��������̂����݂̎Гa�B�{�a�͗�������Ő��ʂ̗��̒������͂��ߗl�X�Ȓ����ŏ����Ă���B�㉮���{�a���ɂ͌�Ԑ_�ЁE��P�x�_�ЁE��א_�Ђ��J���Ă���B�����ɂ͒n��ʂ̎Ђ����蒹���̊z�ɂ́u�z�K�{�v�Ə����ꗼ�������ƂȂ��Ă���B |
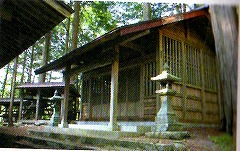 |
��؊ω�
��؊ω��͊J�c�����̊ێR�ω��A��K���̊�o�ω��ƂƂ��ɖؑ]�O��n���ω��̈�ɐ������Ă���B�n��ω��Ƃ��Ă���؊ω��͐́A�ؑ]�n�̕��q�n�ł������ؑ]����̈�p�ɖؑ]�`�����J�����쌱���炽���Ȕn���ω��Ƃ��ċ��n�̑��Ђ��F�O����l�����̌����M���������h����Ă����B���݂̌����͖����Q�P�N�Ɍ��đւ���ꂽ���̂��A���a�R�S�N�̈ɐ��p�䕗�̌�C���������̂ł���B���̓��̗����ɂ͐����O�\�O���ω����J���Ă���B |
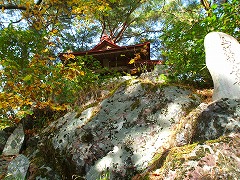

 |
����M�\���Q
�Z�\�N���ƂɖK���M�\�̔N�Ɍ��Ă��Ă����Δ肪����w�߂��̒��R���[�ɂ��������J���Ă���B�Z�\�����Ƃɂ��M�\�̓����K��邪�u���̖�͖����Ă��܂��ƃT���V�Ƃ��������l�̂��甲�������V�ɏ����ēV��Ɉ��s���������Ė����k�߂��Ă��܂��Ɓv���������`��������B�݂�Ȃ��W�܂��Ĉ�Ԍ{���Ȃ��܂ŋN���Ă���̂͂��������M�̖��c�ł���B�ʋ�������{�A�O���Ȃǂ����܂ꂽ���̂�����̂̐M���Â���B |


�ʋ����� |
| �V�_���� |
|
| �ؑ]�������� |
|
�ؑ]���
�g��p���̏����u�V���ƕ���v��u�{�{�����v�̕���ł�����B |
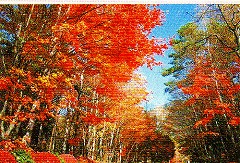 |
| �ؑ]����̃R�u�V |
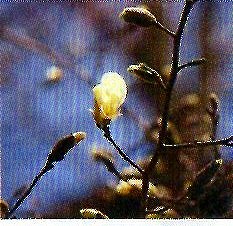 |
| �ؑ]����b�b |
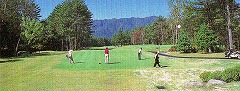 |
�ؑ]��I�[�g
�L�����v�� |
|
�ؑ]��
�X�ь��� |
 |
�ؑ]���
�F�R �b�b |
|
�L�����s���O
�t�B�[���h
�ؑ]�Ó� |
 |
|
| |
�R���ڂ̂Q |
�@
�|�M�̌������Ɍ�����R���r���q�̉Ɛb��
�Α���̕�
�Α����
��P�x���D���ŋ�P�x�̌����邱�̏ꏊ�ɕ悪�ł����Ƃ����B |

 |
�ؑ]�����`�̉������̊W
�ؑ]���̉Ɩ������ł���B |
 |
�A
����
���R������� |

 |
�B
�����
�ؑ]��̎x�� |
 |
�C
��������
���~�� |
 |
���K��
�����������~�� |
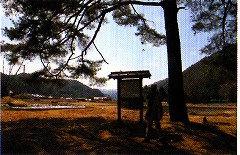 |
�D
��K���V�_
�Â��͎R���V�_�ƌĂԁB���������ɋ`����ؑ]�̎R���ɉB���{�炵���ƋL����Ă��邪�R���͏�c�̌Ö��ŕt�߂ɒ��������̉��~�Ղ�`���̌����̏����̎j�Ղ��c�肱�̂��{�̌Â�����Ă���B |

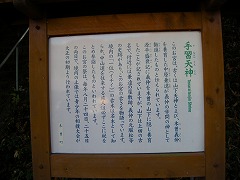 |
�ؑ]�`���̈�Ă̐e�ł���
����������
�ؑ]�`���̊w��̐_�Ƃ���
���s�̖k��V���{���}�����B |
 |
| �Ԃ�������������}�ȐΒi��o��Ƌ���������B�Гa�͂�����܂�Ƃ���������B��c�̑�H�����E���������F��̍�Ő��ʍ��E�Ɏ��q���Əە@�����邪�������ĉE���̎��q��������ɂ����Ă���B |
|
| ��K�V�_�ɂ���G�n |


 |
�����ɂ���
�C�`�C�̖� |
 |
�����ɂ���
���o��
�吳�̏��������N�̑��o���s���Ă���B |
 |
��t��
�������ɂ����t���ɂ͖�t�@�����J���腖��剤���̏\�����J���Ă���B |
|
| �E���ɂ͕�i���N�i�P�V�P�O�N�j���狝�a��N�i�P�W�O�Q�N�j�܂ł́u�얳����ɕ��v�u�O�\�O�P���v�Ȃǂƍ��܂ꂽ�Δ肪����荶���ɂ́u���O��v�ƒ���ꂽ�Δ�Ȃnj܊����B |
|
|
| |
|
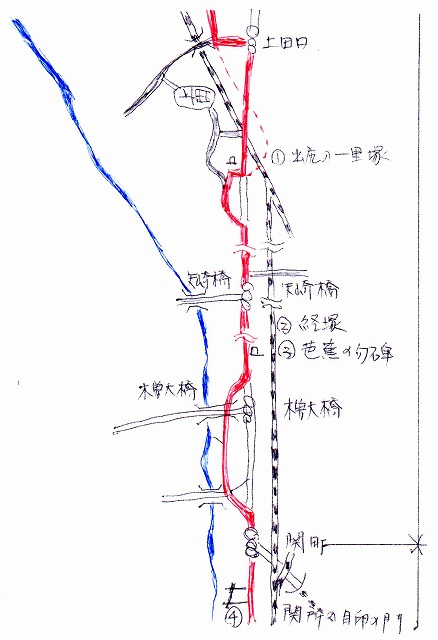
| ���J�c�� |
 |
| �ӂ邳�Ƒ̌��� |
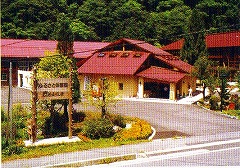 |
����
�͐쉄����P�Q�C�Q�����B����܋��n��㗬��藬��ؑ]��ɍ�������B |
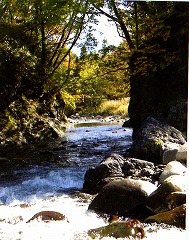 |
���{�����̕�
���{�̐������J�����_�Ђ͑S���ɐ��S����Ƃ����B����̐����m�W���ɂ͈��������̂���Ƃ�����ܗւ̓�������B���̑O�ɂ͎Ⴋ���������̂���������Ă���p�̐Α������邪�����猩��ƕ�e�ł��锒�ς̎p�Ɍ�����B |

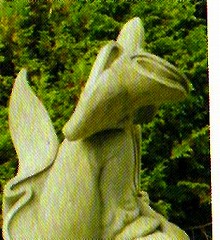
�����ɉ��ƃL�c�l�ɕϐg |
���R�_�Ёi�V�J���l�j
�R���㊯�͖ؑ]�J�̑�H��[�A�ؔ҂�̐E�l�������邽�߂ɂ��ċ{���ɓw�߂Ă�����p��H���H���ɔC���������Ƃł��m���Ă���B�����𒆐S�Ƃ��钁���������̐��A�����I�ȋK���͐E�l���������Ɠ����ɔނ�̂��C�������o�����Ƃ��Ẵv���C�h����Ă��B�������Ėؑ]�̑�H�d���͖ڊo�܂������W���ނ�͐M�B�͂������̂��ƒ��R����ʂ��č]�˂֔����ւƊ���̏���L�����B |
 |
���R�_�Ж{�a�̗�
�{�a����|�����͖̂������疾���ɂ����Ċ��������֓���g�B�ؑ]�H�����ł��F��_�ЁA�{�a�����_�Ђ̎Гa�M���_�Ж{�a���̌�����c�����B |
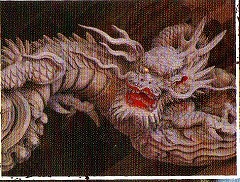 |
���R�_�Ђ̌Ñ�_�y
���싽�̔��R�_�Ђł͖��N�傫�ȍՂ肪�t�E�āE�H�̂R��s��ꂻ�̓s�x�Ñ�_�y����[����Ă���B���̐_�y�͂P�X�T�Q�N�i���a�Q�V�N�j���Ō�y�̏��Ȃ����É����|��s�̌�ԍu�Ђ̕��ɂP�T�Ԕ��܂荞�݂ŗ��Ă��������Ⴂ�l�����ɓ`�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�������|��ł͍s���Ȃ��Ȃ肱�̗x��͍���݂̂ɓ`����Ă���_�y�ƂȂ����B�V��ނقǂ̐_�y���R�O�N�قǑO����͏��w�����w�N�̏��q���s���u���_�̕��v�����͑�l�ɂ���ĕ�[����Ă���B |

�|�̕� |
���R�_�АΕ�
���R�_�Ђ̒������������������̉��ɑ傫�ȐΑ������J���Ă���B������\�ʑ喾�_�A����@���A�\��ʊω���F�B�\�ʑ喾�_�̕����ɂ͍����Ă���n�������Ă���B
|
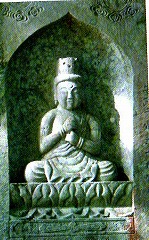
����@����

�\�ʑ喾�_���� |
���J�\�e�R
�����������ّO�̍L��ɂ͓��O��Ǝ\�e�R�������Ă���B�\�e�R�̌��c�͒}�g�R�̘[�ɓ`�����F�P�ł��邪�P��_�i�����Ē����Ă���B���ꒅ�����P����Ă��V�v�w�������Ă���ؑ]�ł͒������Ƃ����B |
 |
����̏t��
����̉�������n��ɂ͌Â�����`���̂Ɨx�肪����Ղ��ڏo�x��������I������h�V��ȂǂŔ�I����Ă���B���t�͊ȒP�ł�����肵���̂ɍ��킹�ď\�\���Δ��Œ@���Ȃlj��̖���͉̂��ł����p����B���ے��q�ɂ�K�����ĕz�ŕ�݂����U���ĉ����o���҂����肠�Ƃ͉��̎蔏�q�Ő���グ��B�x������܂������̂͂Ȃ��̂������Y���ɍ��킹��Έ�l�O�ł���B�����͒j���͔h����@�قƌ����ςɎ�ʂ����Ŗj�������ĒN�����킩��Ȃ��悤�ɂ���̂������ōŋ߂͂��ʂ�t����ꍇ�������B�������ȗx��Ɍ����邪���[�_�[�͌��܂��Ă���单�l�̖ʂ����đ܂�S���ŏ��Ƃ�U���Đ擪���s�i���Ă���B���̑单�l�����Ƃ�U���đޏꂷ��Ηx��͏I������B�x��̓��e���炢���Ėؑ]�n�̎q���ɉh��������̂Ɨx��Ǝv����B
|
 |
�ǂ�ǏĂ��i�̐_�j
�P���P�S���ɍs���B����܂₵�ߏ���Ȃǂ�R�₵���̓��ł��݂��Ă��ĐH�ׂ�ƂP�N�����ׂ��Ђ��Ȃ��Ƃ����Ă���B |

�J�c�����E��̂ǂ�ǏĂ� |
���R�ω�
���싽�̌Ô��Ƃɂ͖ؑ]�Ə\����`�݂�̒킪�{�q���肵�Ă����B���̎q�Əd�͐퍑����̐킢�Ɋ��Ĕ��ˎ�̍��������ꂽ�����ł���B���̔��ˎ炪��i�������R�ω����͖ؑ]�O�\�O���ω�����̈�ŏ\��ԏ��ɂȂ��Ă���B�������ɂ͐����O�\�O���ω��̐Α��������ׂ��傫�Ȓn����F������n���ω��̖{���̎p�ł���O�ʔ��]�n���ω���F���Ȃǂ�����B |

�����O�\�O���ω��̐Α���

�O�ʔ��]�n���ω���F��
|
| �����ӂ����܃X�L�[�� |
 |
����̑�
(�ؑ]���V�J)
�ؑ]�����`�J�c�����Ɍ�������ˊX���n�����̎�O�ɂ���B�����U�O���B���싽���R�_�Ђɕ�[����Ă���u���씪�i�G�n�v�ɓ���̑�̉��Ƃ��ĕ`����Ă���B |
 |
�J�c����
�Y��Ȍ�ԎR��^���ʂɗՂށB�W���P�P�O�O�`�P�R�O�O���̊J�c�����B�Ăł�����Œ���̊��g�����傫���B��ł��뜜���ꂽ�ؑ]�n�̕ی쎔����s���Ă���B |
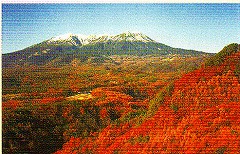
 |
�ؑ]�̖���
�ؑ]�̖��D���͖ؑ]�̖��߂̖��Ŋ��q����̌ÉS�ɉS���Ă���]�ˎ���̋L�^�ɂ��ƌ�ԎR�[�̑����𒆐S�ɑ����̗ʂ̖��D�������Y����Ă������Ƃ��m���B |
|
�n���O�\�O�ω�
�J�c�����n���̋����e�ɖ�ϐ�����F���ƎO�\�O�ω�������B���ω����l�X���~�����߂ɎO�\�O�̎p�ɕω��������̂ɎO�\�O�����g�����邪���̃G�s�\�[�h����ɂ��č��o���ꂽ���̂��O�\�O�ω��ł���B���ߊω��␅���ω��Ȃǂ�����Α����ł͒������Ƃ����B |
 |
���m���̑�
�J�c������ԎR�̘[�A�l�̒r���痬��Ă����쒆���̍����R�O���̑�B��ԎR�J�R�����̑c�Ɛ��߂�ꂽ�o���s�҂�s�҂䂩��̏C�s�̑�B���a�����܂ł͂Q�{�̑�ł����������݂͂P�{�̑�ƂȂ��Ă���B��ԎR���痬�����͐���������W�߂���ʼnĂł������W�x�Ɣ��ɗ₽���B |
 |
| �J�c�����̋����̉� |
 |
�J�c���y��
�ؑ]�n�Ō�̏�����u��R�t�R���v�̂͂������W������Ă���B |

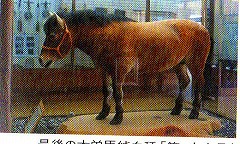 |
�R���ƏZ��
�n��҂ł���n��ł��������B�{������̌��݂̌����͌��z�����̕��ʐ}�Ɋ�Â��Ԍ��P�P�ԉ��s�W�Ԃ̌����ɏC������P�X�X�U�N�i�����W�j�N����Ɏw�肳�ꂽ�B |
 |
�ؑ]�n
�����Z���E����ނ�����̑傫�ȕ��E�Ԃ�ȓ��������邵�����{�̍ݗ��n�B���a�Ől��������
�Ƒ��ƈꏏ�ɕ�炵�Ă����B
�ؑ]�n�̃��[�c��2�`3���I�ɑ嗤����n�������Ñ����n���c��Ƃ�����������B8���I����ɂ͖ؑ]�ɐ��Y�n���`������Ă����Ƃ����Ă���B���q����퍑����ɂ͗D�ꂽ�n�Ƃ��ĕ]�������܂蕐���������������Ėؑ]�n�����߂��Ƃ�����B���a�ȍ]�ˎ���ɓ����Ă���͉^���̔��W�ɂ��v����������ɊJ�c���ŊJ��������ɂȂ�ƎR�Ԕ_�k�n�Ƃ��Ċ����B�Ƃ��낪�R����`�̎���ؑ]�n�͏����Ȃ��߂ɌR�p�n�Ƃ��Ă͕s�K�i�Ƃ���낤����Ő��O�ɂȂ����B���������ؑ]�n��������l�X�����������菭�����������݂P�U�O���]�肪�S���ŕی삳��Ă���B |
 |
�ؑ]�n�̗�
�u���[�x���[ |
 |
| |
|
| |
|
�c�V�R�_��
�{�Ђ͐ΐ쌧�ߗ����̉��ꔒ�R�Ŕ��R�����_�Ђ�{�{�Ƃ��Ă��邪�n�����ꂽ�N��͕s���B��_���e���Q�_�Ƃ��ɜQ���E�ɜQ�f�������J���Ă���B�����l�N�i�P�X�X�Q�N�j�ɔq�a�E�Ж�����S�ʉ��z�����B |
 |
�P���q��
�̊J�c�����c�̑�n��ɉ����ĕP���q�����s���Ă��������̂܂ɂ����ނ��Ă��܂��Ă����B�Q�O�P�O�N���ɕ����̘b�������オ��n���̗L�u���W�܂��ė��K���d�ˍŋ߂͒n��̌|�\�ՂȂǂɎQ�����Ċ������s���n���̐_�Ђɂ���[����Ă���B |

 |
����F��_��
�_�a�͍Y�̌��{��H�֓���g�̍�ő�Б���B���{�Ў����z�j��ɉ����ėL���ȁu�����j�����v�̋Z�@������ł���Éi�V�N�i�P�W�T�S�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ�傫�Ȑ_�a�B�{�Ђ͓����������S���_���F��Ƃ����Ă��邪�a�̎R���F�쌠���ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�Ր_�͈ɜQ�f���E����������E�_�c�ʖ����J���Ă���B �����ɂ͒������k�v���_�肪����k�l�����Ɍ������Ē��������⏜�Ђ��F�閭���M�̔�ł���Ƃ����_����@�̏C�����̓���ƂȂ��Ă���B |
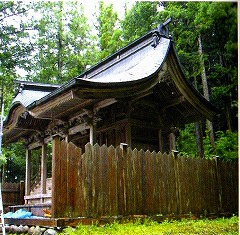 |
| �������V�o�^�J�G�f�����炵�Ă��邪�N���q���^���Ə̂���J�G�f�̕ώ�Ŕ����̌��E�ԏ�R�����Ȃǂ̂ق������̓썲�v���R�Ȃǂɕ��z���Ă���œ쐼�[�Ɏ������Ă���Ƃ����Ă���B |
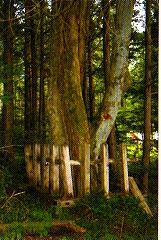 |
������
�J�c������B�͖̂��N�R�������Ƃ������B�{���̎߉ޔ@���͂P�U�U�O�N�i�����R�N�j�ɍ���n���J�R�͌j�x�a���ɂ��P�U�U�S�N�i�����S�N�j���Ƃ�����B�������ω����͂P�V�O�R�N�i���\�P�U�N�j�ɑ剮���i����Ɓj����ڂ��Č��Ă����D������P�{�̟O�̑�ő����Ă���B�����ɂ͎牮�厡��̒n���ቤ���F���Ȃǂ̐Ε�������B |
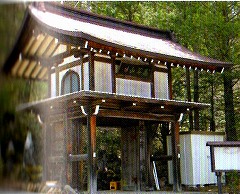
�������̏��O��
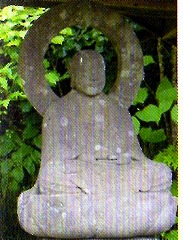
�牮�厡�̐Ε� |
������
�{���͎߉ޔ@���łP�U�U�T�N�i�����T�N�j�ɑn���B�J�R�͒����������V���q�m�a���B�ؑ]�Í����v�u�ɂ��ƂP�U�U�P�N�������N�������Z�������a���J�R�Ƃ���B�ω����͂P�W�S�T�N�i�O���Q�N�j�S���g�����R��Z���T�������㌚���B�{���͔n���ω��E�ɎO�䎛���ӂō��Č��������o�Č������ɑ���ꂽ�@�ӗ֊ϐ������ɐ��ϐ����Ə\��_���̕��悪���u����Ă������P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�R���P�������Ɏ����S�Ă��Ă��܂����B |
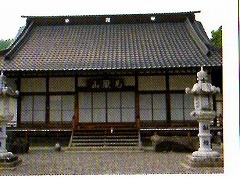 |
���씪���{
���_�V�c��_�c�ʔV���Ə̂��Ď�Ր_�Ƃ��ɐ��c��_�{�E�F��_�ЁE��{�����{�E�Ó����q�_�Ђ̌Ђ���ւ���Ă���B�����^���͕�q�M�̎Y�y�_����n�܂�̂��Ɍ����̕��_�Ƃ��ꐼ�쑺�����E�؉Ƃ̐�c����ƍՐ_�������������Đ��쑺�̎Y�y�_�Ƃ����Ƃ����Ă���B�����ɂ͑c��Ђ��J��ꐅ�m�Ԃ����炵�Ă���B |
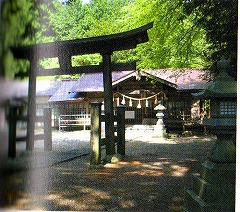 |
��w���̎q���n���i����j
�ɓߐ��t�ߑ��o�g�̋{���S��̐Α��� |
 |
�ێR�n���ω��i����j
������肵���R�̒��ɂ���������傫�Ȕn���ω��������J���Ă���B�����ɂ͓V���Ȃǂ̒������{����Ă���B�����̘e�ɂ͂�������̔n���ω����Ȃǂ̐Α������J���Ă���B |
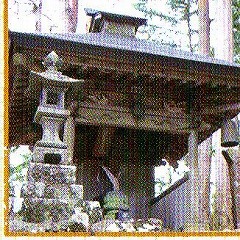

�ω������ӂ̐Α��� |
| ����̑� |
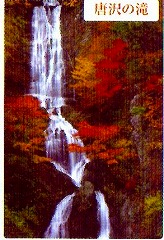 |
�J�c�����}�C�A�X�L�[��
�X�m�[�V���[�ŕ����u�S�̐��[�h�v���J�� |
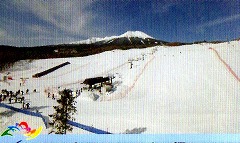
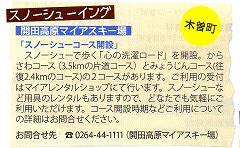
|
| �`���I��x�X�m�[���]�[�g |
 |
|
| |
�R���ڂ̂R |
�@
�o�K�ꗢ�� �� |
 |
�o�K��
�Ȃ̖�
����R�O�O��
�����P�O��������W�C�V�� |
 |
| �ؑ]�勴 |
|
| ���ؑ]������ |

 |
�A
���璬�o��
|
 |
���y�قɓW������Ă����o�˂Ə����ꂽ�G�}�ʁB
���̒n�͒��R������̍������P�T���[�g�����炢�̏��Ō�ԎR�̉E�[�̌p�q�x���݂���Ƃ����B�o�˂͎R���Ƃ̌��ꡔq���ł������Ƃ����`��������B(�瑺�����̂ӂ邳�Ƃ�K�˂Ă��j |
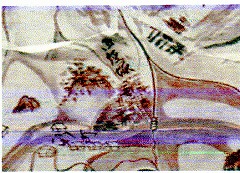 |
�B
�m�Ԃ̋�� |

�����Џo���ؑ]��l���̂������ |
| ��R���� |
|
�C
�֏��Ջ߂���
�傫�Ȋ��ؖ� |
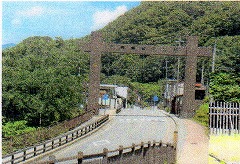 |
��R�V�� �����h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�P�S�� |
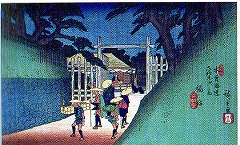 |
�ؑ]��
�ؑ]���𗬂���͂��ׂĖؑ]�쐅�n�ƂȂ��ė���ɐ��p�ɗ��ꍞ��ł���B
�͐쉄����Q�Q�X�����B�ב��ؑc����蕟���E���`�n��𗬂�E���m�̗�����ʂ葾���m�֒����B |
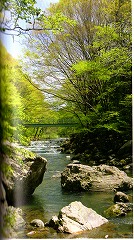
 |
|
| |
|
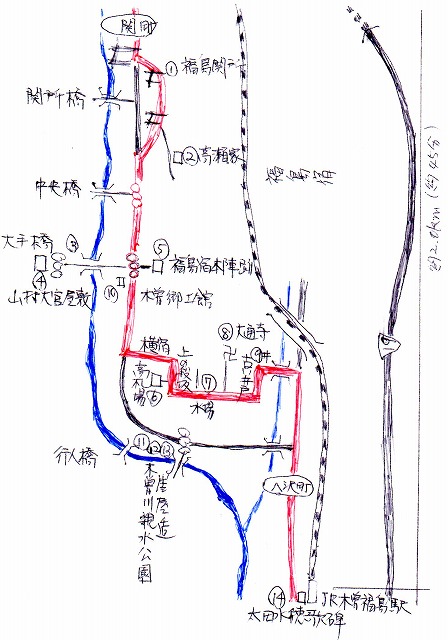
| ���R�@�̓��L���� |
|
|
| �����h |
�吳�P�T�N
�V���X�� |
���B�̍��x�̗��s�̏I���_�Ƃ��Ă����ؑ]�����Ɍ������B�����͍]�ˎ���ɑ㊯�̂����Ƃ���Œ��哹�ł̍ł��傫�Ȋ֏��������ɂ������B���ł͂����̂̎�͂Ȃ��B�n�s�̗����͓��키�Ƃ̂��Ƃ��B�����̂���H���B�y�Y�����D�Ԃɏ��B |
�����_��
���⋽���̎��_�ł��������ɕ������̎��_�ł�����܂����B�P�Q�U�T�N�i���i�Q�N�j�T����ˈ�{�����_�Ђ����̒n�Ɍ䊩�������V�c�Ə̂��J�����B���D�ɂ͂P�Q�V�X�N�i�O���Q�N�j�ؑ]���c�n�̂��݉ƒ��ɂ���Ċ��������Ƃ����Ă���B�P�R�T�V�N�����Q�N�z��̎瓡���̉ƗL���ċ����ؑ]���E�ΐ���O�̎�E�㊯�R�����Ɏ���̎�ɂ���Ėؑ]�����琅���喾�_�Ƃ���Ă���B��Ր_�́u���ƕP���v�B����͂P�Q�O�O�N���鞹�E�O�E���̖Ɉ͂܂�Ă���B |

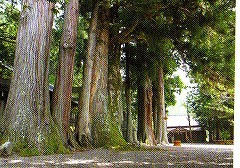 |
�����_����
���N�V���Q�Q���E�Q�R���ɊJ�Â����u�V���̊�Ձv�Ƃ��ėL���Ȃ݂����܂���B���̂䂦��͖��N�V�������d���S�O�O�L����������Ȕ��̑�_�`���Q�R���̖{�Ղ�̖�ɕ����n������u�@���v�u�K���v�̊|�����ŏc�܂���E���܂�������ĉĂ��܂������Ȃ݂����܂���ł���B |

 |
���E����O���u
�̂͊e�W���ŋ���̂Q���ɂ͂˂͂�O���T���ɂ͕S���ՔO�����s���Ă����B���̑��ɂ�����u�E�����u�E��\���u�E���O��u�Ȃlj�����O���u���s���Ă����Ƃ����B�S���ՔO���u�͂P�O�W�O�̎삪���Ă��钷���吔����u�얳����ɕ��v�������Ȃ���̂����P������Έ�l��Տ��������ƂɂȂ�P�O�l�ōs���Έꖜ�ՂƂȂ邩��P�O�O��ΕS���ՂƂȂ�B
�����̐��E����W���ł͌��݂��������Ă��Ē��̖��`�������Ɏw�肳��Ă���B�ؔō���̖�����D�Ə������ꂽ���Ԃ��Ď����A�蕧�d���J���Ă���B |
 |
������
�勝�Q�N�i�P�U�W�T�N�j�m�����ɂ���ĊJ�R�n�����ꂽ��y�^�@���{�莛�����B���͔����[�Ɍ��Ă��Ă��������R�N�i�P�V�T�R�N�j�ƉÉi�R�N�i�P�W�T�O�N�j�ɔ����̍^����Q�����������Q�N�i�P�W�T�T�N�j���ݒn�ֈړ]�����B�����P�V�N�i�P�W�W�S�N�j�ɂ��ɗ��𗬎����čČ������B���̏ꏊ�ɂ͎����ړ]����O����]�ˎ���̊��w�Ґ��̏��ւ��������B |
 |
������
��S��R���㊯�ǖL���̉��������@�@�ɋA�˂��Ċ����N��i�P�U�U�O�N��j�ɑ㊯���~�k���ׂɎ������������̂��n�܂�B�ꎞ���ނ��Ă������������N�i�P�V�W�X�N�j�ɍēx�J�R���č����Ɏ����Ă���B���a�P�R�N�i�P�X�R�W�N�j�ɂ͕������w�Z��Z�Ɍ��z�̍ے����Ɉړ]�����B |
 |
�������_��
�{�a���ʑO�̊z�ɂ͒Ó������V���Ə����ꍶ���ɏ]�܈ʉ��R�ǗR�q���Ƃ���B���㊯�R���ǗR�i�R���h��j�̏��ł���B |
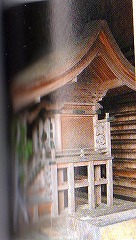
|
�����ɂ���m�ԋ��
�����͂���@���������
�ӂ��×�
���Ɂu�b�i�����̔o�l�j���V�i�����݂̂Ȃ炸�j��X�[�i�ƂƂڂ��j���V���T�N�v�Ƃ���B
���͎V�ɂ��������̂������Q�ɑ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŎV�ɂ͉��߂Ĕm�Ԃ̋������Ă��̂�����Ɍ�����Ó��_�Ђ։^�Ƃ����B |
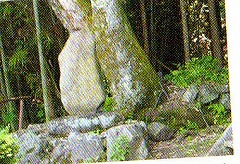 |
��R�j�Ղ̐X
�ؑ]�`���������̍ۂɑł��ꂽ�Ƃ����������퍑����̎R�镟����Ղ�����B
������͐퍑����ؑ]�`�N�ɂ���Ēz���ꂽ�B
�����̒��ɂ́u���ێR��v�u��̒i��v�u������v�̎O�̏邪�������B
|
 |
������
�ؑ]�`�������ƒǓ��̋����̍ۂɂ��̑�ş����F�肵���̎��Ɍ�ԑ匠���������������ƂɗR�����閼�̂Ƃ����Ă���B������S�O���B�꒼���ɂ͏C���҂����s�����邽�߂Ɋ��������䗧�ꂪ�c���Ă���B |
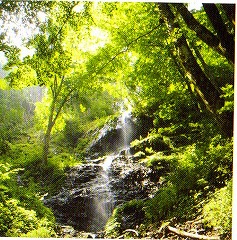 |
| �N���C�}�[�ɂ����͓I�ț����� |
 |
| �~�씪���{ |
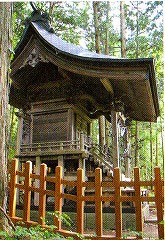
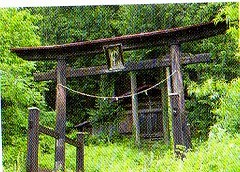 |
| ���R�_�� |
 |
| �r�_�� |
 |
| �匴�z�K�_�� |
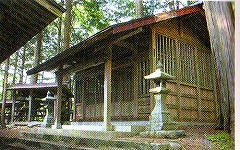 |
�ؑ]����
�l�S�L�]�N�̗��j���ւ�ǎ��Ȗ؍ނƓV�R�����琶�܂��ؑ]�t�c�E�ؑ]�Ŏ�E�h�蕪���C�F�h�͐E�l�����̓`���Z�@�B |
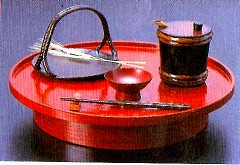 |
| |
|
�������p�i���z�Ɓj
�c�����N�i�P�W�U�T�N�j�������Ő��܂ꂽ�B���z�Ƃ��߂����Ē鍑��w���Ɗw�Ȃ𑲋Ƃ����B �ŏ��͍H���ē����Ă��������l�̋ߑ�I�ȃr���Q�̌��z�v�Ɋւ��悤�ɂȂ����B�����O�\���N�i�P�X�O�T�N�j�ɐv���������J�݂��O�䕨�Y���l�x�X�⌻�݂̐_�ސ쌧�����j�����فE�����l��\�q�ɂȂǂ��肪�����B�S�R���N���[�g�̋��x������������ċZ�@��T����{�̓S�R���N���[�g���z�̐��҂Ƃ��Ċ����B |

�O�䕨�Y�i���{�ŏ��̓S�،��z�j |
| ���l��\�q�� |
 |
����i�y�퐻��j
�؍��ɐ��܂��Q�����E��풆�ɗ���������w�݊w���Ɏ���p�v���̍u���ŃX�g���f�B�o���E�X�̉��̉𖾂͉i���ɓ䂾�Ƃ����b���o�C�I��������ڎw�����Ƃ����B�������ǂ��֍s���Ă������Ă��炦�Ȃ������B�ؑ]�����֗��Ă���͓y�؍H���Ɍg���Ȃ����o�C�I�����H��̏]�ƈ���K�˂ēƊw�Ŋw�B��P�x���݂���y��Ɏ����Ŋۑ����������Ăĕ�炵�Ă����B���a�\��N�i�P�X�V�U�N�j�A�����J�ŊJ���ꂽ���ۃo�C�I�����E�r�I���E�`�F������҃R���N�[���ɂ����ĘZ��ڒ���ڂŋ��܂���܁B���a�\��N�P�X�W�S�N�ɖ��Ӎ�����Ƃ̓��ʔF��ƃ}�X�^�[���[�J�[�̏̍������^���ꂽ�B������\�l�N�i�Q�O�P�Q�N�j�ɐɂ��܂�Ȃ���i�������B���鎁�͖ؑ]�����ɗ��邱�Ƃ��Ȃ�������o�C�I��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����Ď茳�ɒu���Ă���������̃o�C�I������ŐV��ȂǂR���ؑ]���Ɋ����B |
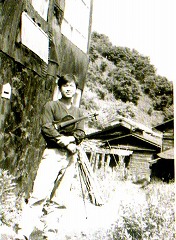 |
| �Z��Ղɐݒu���ꂽ�����[�t |
 |
| |
|
| ���}���S���ɂ��Ɠސ�E���E�R�����܂ߎ��@�͂R�V�����肻�̂����ؑ]���ɂ͂P�S���������ƋL�^����Ă���B���݂͂P�Q������B�ؑ]�͗ՍϏ@���S���h�̂��������ɑ����n��ł���B |
| ��s�� |
��R |
���̏���炵�����B�֏���̊J�����̎��̏��ɂ��s���Ă����B |
| ���V�@�� |
���� |
�����������a���̉B���� |
| |
�������n�� |
���ՂƂ�����Â��ܗ֓�������B |
| |
��ʎ��t�� |
���{�莛�h�ł������P���������������V�a�R�N�i�P�U�W�R�N�j�ɔp���ƂȂ����B |
| ������ |
���� |
�퍑����ɖS���Ȃ��Č�擇�ɖ������ꂽ�ؑ]�`�����̋��{�͗������ɉ����čs���Ă����Ƃ�����B��ɗ������͒������ɍ��������B |
| ������ |
������ |
�������������ՂƂ����Ă���u���~�c�v�Ƃ������O�̓c��ڂ�����B�R���㊯�̏������{�u�ؑ]�Î��k�E��v�̒��ɂ����̋L�q������B |
| ����n��ɂ͏\��̂̓��c�_������ؑ]�n���ł͍ł������B�]�ˌ���ɑ���ꂽ���̂��قƂ�ǁB |
| ��u���o�̓��c�_ |
 |
| ���J�\�e�R��i���F�P�j |
 |
| �Ȗ{�o�̓��c�_ |
 |
| �Ō��o�̓��c�_ |
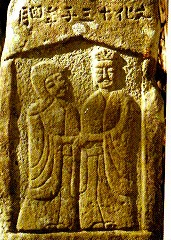 |
���l�o�̓��c�_
���c�F�E�F�� |
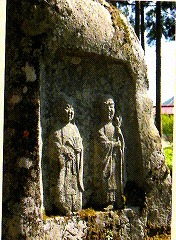 |
| ���q���o�̓��c�_ |
 |
| |
|
|
|
3���ڂ�4 |
| �r��� |
|
�@
�����֏�
�����֏��͉O�X�E�����E�V���ƂƂ��ɓV���̎l��֏��̂ЂƂł��蒆�R���̂قڒ��ԂɈʒu����֏��ł���B�ؑ]��̐�ǂ̏�ɍ\���w��ɗ��R�������ԋ������Ŋ֏��ɂ͂����Ă��̏ꏊ�ł���B
�]�˂���邽�߂̒��R���̗v�ՂƂ��āu���S�C�v�E�u�o���v�������������܂��Ă����B
�u����`�v�͂����Ŗv�����]�˂����������ɂ͉O�X�֏����́u���֎�`�v�����s���ꂽ�B
�c�����N�i�P�U�O�Q�N�j�ɒ��R�����J����ĊԂ��Ȃ������֏��͑n�݂��ꂽ�Ǝv���邪������N�Z���܂ł��̋@�\���ʂ����Ă����B
�p�㏊�{�݂͑S������Ă��܂��Ă��������a�T�O�N�Ăɍs��ꂽ���@�����̌��ʊ����N�ԁi�P�U�U�P�N����P�U�V�O�N�j���̂��̂Ɛ��肳���֏��ÊG�}�Ɍ�����֏���\�̑S�e���m�F���邱�Ƃ��ł����B
������j�Ռ����Ƃ��Đ����ۑ�����v�悪���Ă��j�Ռ����ɗאڂ��ď��a�T�Q�N�S���Q�V�������̔ԏ��������Č��֏������ق����������B
�P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�R���P�R�������Ȃɂ�荑�̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B |
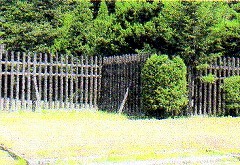
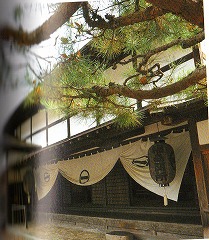

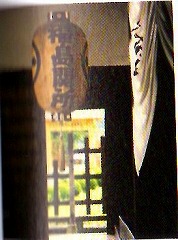 |
�����֏���
�����}�̊Ŕ� |
 |
| �֏��� |
|
| �����֏��Ղ̐Δ� |
 |
�֏��� �Ɍ��z���ꂽ���吼��
�����Q�N�j�Փ��̖��n�̌��L���ɔ�����Q�����@���������{���j�Օۑ��E�������̈�Ƃ��ĕ����S�N�x�ɓ�������Ɩ؍�y�ѕ��Ɖ��~�Ղ̌����������C�i�����������B |
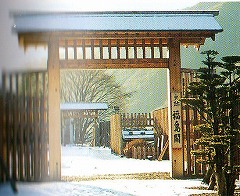
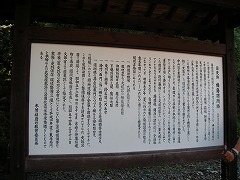 |
| ����� |
 |
| ����� |
 |
| �����֏��܂� |
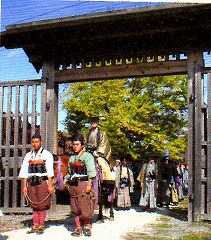 |
�A
������
�������蓡���̎o�u���v�̉ł���B�����u�Ɓv�̃��f���Ƃ��Ēm���Ă���B�����Ƃ͎R�����̉Ɛb�ő�X�֏��Ԃ߂Ă����B
�����Ƃ̑c��͔��̍��i���F�{���j�̏o�g�ő��~�̐w�̍������ɒ��Č�ɎR���㊯�Ɏd�����̂��͂��܂�Ƃ����B |


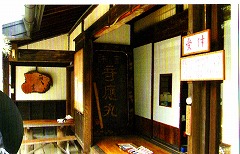 |
���蓡��
�����ܔN�i�P�W�V�T�N�j�ɔn�ďh�̖{�w�E�≮�E���������˂鋌�ƂɎ��l�Z��̖����q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B��̂Ƃ���ԏ�̎o���������������Ƃ։ł����B�����O�\��N�i�P�W�X�W�N�j�ɂ͍����ƂɂЂƉđ؍݂��u�đ��v�̎��҂��������B�����l�\��N�i�P�X�O�X�N�j�ɂ͍����Ƃ����f���ɂ����u�Ɓv�̏����̂��ߑ؍݂��Ď�ނ����B�����̍ȃt�������l�̎q�����c���đ����S���Ȃ������ߎO�̎O�j�����w�Z���Ƃ܂ō����Ƃɗa�����B���̌���悭�����Ƃɂ͗�����菺�a�O�N�i�P�X�Q�W�N�j�ɂ͖閾���O�o�ł̂��ߎ��������ɗ����B���a���N�i�P�X�R�R�N�j���ŖS���Ȃ����B |
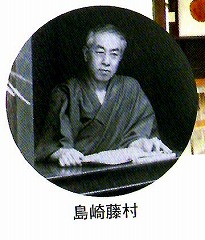 |
| ���������� |
 |
| ������� |
 |
| |
 |
���鎺�і�ǖؑ]�x�ǒ���
�����˂̊NJ��ł������ؑ]���т͖������{�Ɉ����p����䗿�тƂȂ����B�P�X�O�R�N�i�����R�U�N�j�䗿�ǖؑ]�x�����������ɐݒu���ꃂ�_���ȗm�����ɂ����Ă�ꂽ�B�P�X�Q�S�N�i�吳�P�R�N�j�ɒ鎺�і�ǖؑ]�x�ǂɉ��̂���ĊԂ��Ȃ��P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�T���̕����̑�ɂ��Ď����Ă��܂����B�������鎺�і�ǂł͑��͂������ĕ������ؑ]�ܖ̗Ǎނp���čw�������O�ނ��g�p���Ă��̔N�̕�ɂ͌��݂̒��ɂ����������B�Q�O�P�Q�N�i�����Q�S�N�j���ؑ]���L�`�������Ɏw�肳��ĕ����ۑ��H�����s��ꂽ�B |
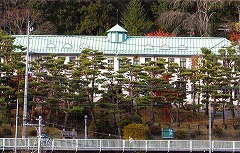
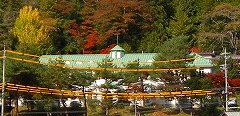 |
�ؑ]����
���y��
�~�n���ɂ͋��J�c������ڒz���ꂽ�����Βu�������؍ȑ���̓T�^�I�Ȗؑ]�̖��Ƃ�����B |
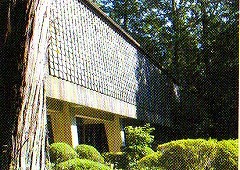 |
���T��
�ؑ]�H�����_
�g�˓V
�ؑ]���\���M�����̕��e�A�e�L�������ێR���z�������ɏZ���Ƃɔ����i���Z�N�i�P�S�R�S�N�j�ɋ��T����n�����ؑ]�`�����̕������B�䗘�������폟���L�O���ĘT����ł���ΔR�R���狻�T���܂ŏ����s����s����O�Ŗؑ]�x����[���Ē����������ł���B�����ɂ͋`������e�ω����ƒ��g��i���g��͖����l�\�O�N�i�P�X�P�O�N�j�ɕی쌚�����Ɏw��j�������������a��N�̑�ŏĎ����Ă��܂����B���݂͗����Ƃ��Č�����Ă���B |
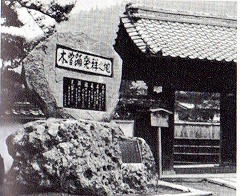
�u�ؑ]�x�蔭�˂̒n�v�̔�
�ؑ]�`���̋䗘�������̐폟���j�������̂Ɛ�������Ă���

�ؑ]�`����A���̎}��������
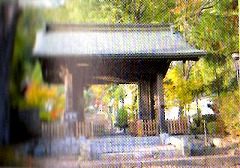
���g�� |
���T���ʼn_��
�͎R���ł͓��m��̍L���ł���B |
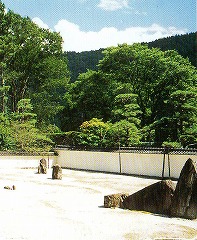 |
| �ؑ]�`���̕� |
 |
| ���T���R���ƕ�n |
 |
�B
��苴
�]�ˎ���ɂ͑㊯���ւ̒ʘH�Ƃ��čł��d������Ă������Ŏ��t�����H���L���H�Ƃ����،˂��݂����ԏ������u����Ă����B�䉮�~�O���Ƃ����Ă����������ɂȂ��đ�苴�Ɩ��Â���ꂽ�B�����ȍ~�Q�x�̍^���ɂ�藬�����P�X�R�U�N���a�P�P�N�H�w���m���������̐v�ɂ�����E�ōŏ��ɑ���ꂽ�R���N���[�g���[�[�����ł���B��������������ɑS���ɉ˂�����悤�ɂȂ蒷�����ɂ��A�����[�[���ʼn˂���ꂽ�����݂͂قƂ�ǂ��V�������V�������ɉ˂��ւ����Ă���B��������苴�͐��E�ōŏ��ɉ˂���ꂽ���Ƃ���Q�O�O�Q�N�i�����P�S�N�j�ɓy�؊w��I���y�؈�Y�Ƃ��ĔF�肳�ꏰ�⋭���{�����ʂɕ�����Y�����Ĉێ��ۑ�����Ă���B |


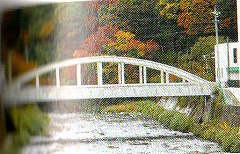 |
�]�ˎ���
�֏����v�u��苴�v�i�R���㊯���~�֓��邽�߂̋��j�u�s�l���v�i��ԊX���ւ̓�����j�̂R�̋����������B |
|
������
��������㒬�Z�l�O�ƌĂꂽ���l�������𓊂��Ċ��������B |
|
| �R���㊯���~����Ղ̐Ί_ |
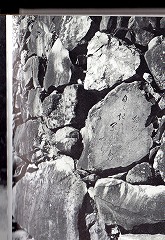
�����̔o�l�����L�̋�
�ה̂Ȃ���͂��������� |
�C
�R���㊯���~
�R���Ɠ`���̕i�X���W������Ă���B
�ꕔ�ɍ]�˒����̊��w��
����
���ցA���R�O���ڒz����Ă���B |


|
���R�O
��X��㊯�R���ǗR�̊�����Ƃ��ēV���̋Q�[�̎��͂�s�����ƘV�E�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�u���v�̏��ւƂ��Ďg���Ă��������B ��������L����B��P�x���]�߂鐼�����̋����ɂ��������̂��R���㊯���~�̕~�n���Ɉڒz�����B |
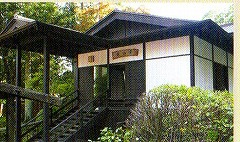 |
��z��
���݂͑㊯�̏Z���̈ꕔ�i��z���j���㊯���~�Ƃ��Ĉ�ʌ��J����Ă���B�n��Q�O�O�N�̌����Ɏg���Ă��钌�͖ؑ]�w�̒��S���̂ݎg�p�u�l�����߁v
���K���X�́u�����K���X�v�Ƃ������{�̋Z�p�ŏ��߂č��ꂽ����
�l�p���|�͉��S�{�ɂP�{�̊����ł��������Ȃ��M�d�Ȃ���
|
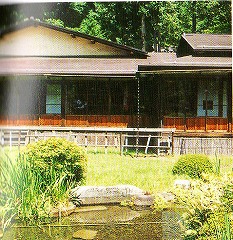 |
�R���Ǐ��͖ؑ]���Ɏd���Ă����B
�Q�O��ؑ]�`�������Ղ��ꂽ��
�Ԍ˂̏��v�����ꂽ�R���Ǐ��i�������j��ؑ]�̕����͍��q�i��t���j�ɂ������փ����̐킢�ʼnƍN�ɖ��������Ď蕿�����Ėؑ]����Z�ɗ̒n��q�̂����B ���R�������h�ɕ����֏����ݒu����R���`�N������̑㊯�ƂȂ�R���Ƃő�X�����p����č]�˖����̏\�O��܂ő������B��X�̑�͂͊w�₪���ӂœ��ɋ��ǗR�i�����悵�j�͗c���̍���蕶�w���D�ݑ㊯�E�̖T�犿����w��������{�܂Ŗؑ]�ōs���Z�p���]�˂ŏC�������B�ǗR���͑h��Ƃ��̂�����F���E��{��ՁE�䕽�F�E���������Ɛe�����[�������̎������R���㊯���~�ɓW������Ă���B�܂��]�˂��炨�����G�t�r��T��e�q��ؑ]�ɏ��������̐_�ЂɊG�n���[�����B |
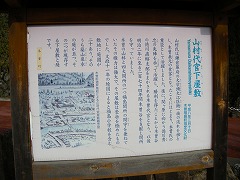
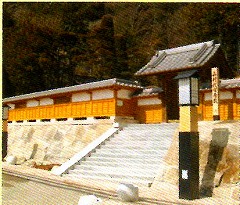
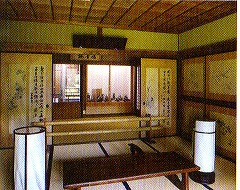 |
�h������M��
�i�㊯���~�j |
 |
| �㊯�����u�R����ׁv�̌�_�̂ł���ς̃~�C���u�����Ђ��܁v���J���Ă���B |
|
�D
�{�w�� |

 |
| �ؑ]�x�� |
 |
| �X��̓��Ղ� |
 |
������
�ؑ]�`���A���c�M���̋��{���R���Ə���
�nj�̕悪����B�ؑ]���P�R��L�������i���Q�N�i�P�S�R�O�N�j�ɊJ�R�����Ƃ����Ă��邪���̑��̔N���ŏ�����Ă�����̂�����B�������̒�������ɗ����������蒷�����ɍ������ė����R�������Ƃ����悤�ɂȂ����B�ؑ]�Ƃ̕��T��ƎR���Ƃ͗nj���܂ł̕�肪�J���Ă���Ƃ�����B�Ǐ�������͓a�������T���ʼn������������ɖ��������悤�ɂȂ����B |
 |
?���ɎR
�n���� |
 |
| �M�B�����̖��H�牮�厡�̒n���{��������B |
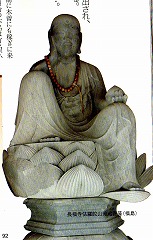 |
| �������ؑ]�Ƒ�X��n |
 |
| ���h |
|
| ��̒i�� |
|
�E
���D��
��̒i�̓��̖��`�̒��ɂ���B���얋�{��˂���̂��B�������m���邽�ߖ؎D�ɏ����č������ɒ���o���Ă������B���D��͊e�������Ƃɂ���{�w�⏯���̋߂��ɂ������B���D��̎���͍������ċߊ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂ���̒��ɂ͌I��~���l�߂Ċ��ɂ��Ă������B���D�ɂ͉ו��ʒ���؎x�O����E���F�E�Ŗ�E����E����E���܌��_�E�l���蔃���̂��ƂȂǑ����Ă������������ܔN�i�P�W�V�Q�N�j�ɔp�~�ɂȂ����B |
 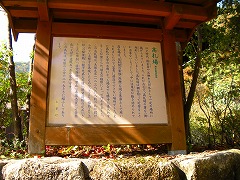 |
| ���܂��� |
|
��̒i
�����h�͖ؑ]�J�̒��S�Ƃ��ČÂ�����h���Ă������ł��邪�c�O�Ȃ��珺�a�Q�N�T���̑�ɂ��قƂ�ǂ��Ď����Ă��܂����B�Č������Ƃ͔������`���ŏd���ڂ����ƂȂ̂Ŗʉe�͎c���Ă���B���ɏ�̒i�n��͑���瓦�ꂽ���ߌÂ��ƕ��݂��c���Ă���A�o�����E�������E��{�i�q�Ȃǂ̌������]�ˎ��ォ��̐���ƒ��a���Ă���B |
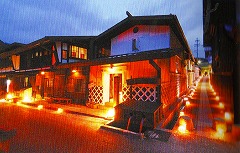
 |
�F
��̒i�̐��� |

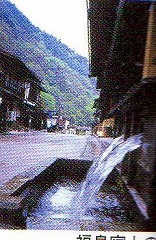
 |
�P�Q�F�O�O
���H |
|
�G
��ʎ����O��
�ؑ]���̉Ɛb�R�����͖ؑ]�㊯�ƂȂ�ؑ]���ِՂɑ�ʎ���n�������B�R���ǂ����̓������ꎛ���������Čj�R�a�����Z�E�Ƃ��J�R�����Ƃ����Ă���B���݂̖{���͕����U�N�i�P�X�X�S�N�j�ɗ��c���������ł���B���O��͈��i�V�N�i�P�V�V�W�N�j�X���{��E����x����H�����E�����E�F��ɂ���Č��Ă�ꂽ�B�ؑ]�����ł͂R�ԖڂɌÂ������ŏ��a�T�S�N�i�P�X�V�X�N�j�R���R�O���ɒ��̗L�`�������Ɏw�肳��Ă���B�����Q�R�N�i�Q�O�P�P�N�j�ɏC�����ꂽ�B�R��Ɍf�����Ă���G�z�͍]�˒����̓��{���\���鏑�ƎO��e�a�̍�ł���B�����͊����S�N�i�P�U�U�S�N�j�Q��Z�E�E�k�`�a���̎���i���ꂽ����Q�����E���̂Ƃ����o���ꂽ���ߏ��a�T�R�N�i�P�X�V�W�N�j�Ē������ꂽ�B |
 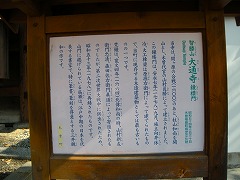 |
�^���P��
���{��
���c�M���̎O���^���P�͖ؑ]�`���ɉł������`�����������Ԍ˂Ŗv������͎O�x�̎R�����̉Ɛb�㑺���𗊂��ďZ��ł����B�R���㊯�͐^���P���v���ʎ��̋����ɋ��{�������Ă��B |
 |
��̒i��
�ؑ]����P�W��ؑ]�`�N���z���{�ہF�֎R�����߂��i�`���Ǝ�������肵���l�V�����J���Ă��邽�ߖ{�ۂ̂��Ƃ��u�ܗ�l�v�Ƃ������B
��̊ہF�����Z������
�O�̊ہF��ʎ������� |
|
���ێR��
�ؑ]����P�P��ؑ]�e�L���z���{�ہF�m�g�j�̓d�g��������
��̊ہF�ؑ]�Z������
�O�̊ہF�u�̏ォ��ؑ]�����w�Ɍ������r���ɂ���א��������� |
|
�v���@
���ۂQ�N�i�P�W�R�P�N�j�S�����T���Z�E�V���j�x�a���ɂ���đn�����ꂽ�B �{���͎߉ޔ@���ʼnE�ɕ����F���ɕ�����F�̎߉ގO�����ł���B�����ɂ͖L������}���������ב喾�_�V���K���J��ꓺ���̊ω���F�\�Z����������Ă��Ė{�����ɂ͔镧�̊ω���F���J���Ă���B�����͐����_�Ђ̂������i�����V��V���q�����ۂT�N�i�P�V�Q�O�N�j�Ɋ�i�������́B�ؑ]�ɂ͒������m���傪����Q�K�����O�ɂȂ��Ă���B |

�v���@�̏��O�� |
�H
��̒i����
��ː� |

 |
�ؑ]�t�c
�ؑ]�������̔���n��͌Ö���x�c���Ƃ����P�R�X�S�N�`�P�S�Q�V�N�i���i�N�ԁj�ؑ]�e�L�̒z�������ێR��̏鉺���Ƃ��Ĕ��W�����Ƃ���Ƃ����Ă���B�ؑ]���͂��̒n�Ɏ���Ǝ҂��Ăъ���ɔ���������̂�����̎n�܂�ł��̌�ؑ]�J�����߂��R����������˂̔�̂��Ƒ傫�����W�����B�ؑ]�J�̞w���H�͋ȕ��E�w���E�h���ɑ�ʂ����B |

 |
�I
�ؑ]���y��
�ؑ]�����ق̕~�n���ɂ���y������̌����B�ؑ]�������������ƐΈ�ߎO��̓��蓡�����R�̂Ɩؑ]�n�̃u�����Y��������B |
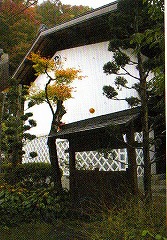
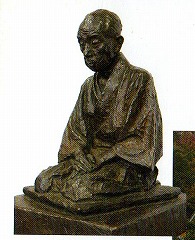
|
�ؑ]���y��
�O�� |


�m�ԋ��@������
������I���͂Ђ̂ڂ鐴���� |
�ؑ]�����ّO�̏��뉀
���蓡���́u�閾���O�v���M���e�p���L�O�肪���a�O�\��N�i�P�X�T�U�N�j�Ɍ������ꂽ�B |

�u�閾���O�v�̔�
���a�R�P�N�i�P�X�T�U�N�j����
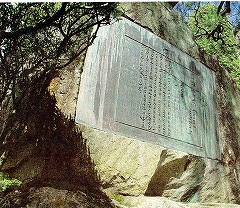 |
�J
�s�l��
��ԐM�̍s�҂��n�鋴����s�l���ƌĂꂽ���͍]�ˎ��㖖���̈����N�Ԃɉ˂���ꂽ���P�W�V�W�N�i�����P�P�N�j�̍^���ŗ��������B�O�x�E���ꗼ���ւ̏d�v�ȋ��̂��߉��}�[�u�Ƃ��ĉ������˂��Ă��̂��P�W�W�O�N�i�����P�R�N�j�ɏv�H�������킸���S�N��ɍĂї������Ă��܂��Č������B�P�X�P�Q�N�i�吳���N�j�ɉ����Ɏԓ������������̂���̋����P�����ꂽ���Q�O�O�T�N�i�����P�V�N�j�ɒ�������̊�t������������Ƃ��ĕ������ꂽ�B |
 |
�K
�ؑ]��
�e������ |
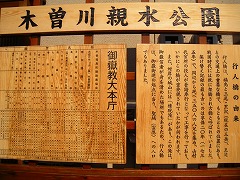 |
�L
�R����
���R���͖{�������̒i�ɓo�蒆���ɏo�铹�ł������}�ȍ⓹�ł��������߂P�X�O�U�N�i�����R�X�N�j�ɖ{�����琼�F�����̊R���@�킵�V����V�݂��ĉI���B�P�X�P�P�N�i�����S�S�N�j�̓S���J�݂ɍ��킹�ē��H�������i�߂�ꂱ�̓��H�ɉ����Ėؑ]��ɒ���o���悤�ɉƂ�����ꂽ�B���̌�������H���ōX�ɒ���o�������y�n��L�����p�����Ɠ��̊R������ƂȂ����B |

�R�������Ė閶�ɓ����Ƃ���
�@�@�@�@�@�ؑ]�����͒J��̒�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c����
 |
�M
���c����̔� |
|
| ���z�p�� |

 |
�ؑ]�����w
�P�S�F�P�T |
|
|
| |
|
| �S���� (�P�P���U���@���j��) |
�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�T����) |
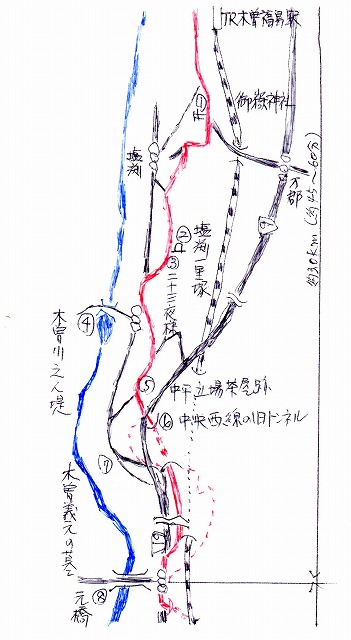
| ���O�x�� |
 |
�O�x�E�H��
��ԁE��ƁE��P�x�̎O�x��������H�����ӁB���O�x���̖��O�̗R���B |
|
| ���̉w�O�x |
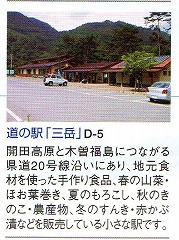
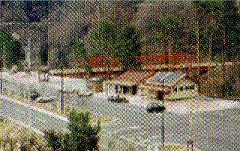
|
| �~ |
 |
| �ؑ]���O�x�����̕����� |
 |
�O�x�����̃G�h�q�K���U�N��
����U�O�O�N�ȏ�
�����P�Q��
������P�A�R�� |
 |
�O�x����W���̐^���P��n
���c�M���͖ؑ]�ɍU�ߓ���ؑ]�`�N�Ƙa�����ۖؑ]�Ƃ͌����̌����p�����Ƃ�����ƎO���̐^���P��ؑ]�ƂP�X��ؑ]�`���ɉł������B�������M���S�����Ƃ͖ؑ]�J�̖�����邽�ߐD�c�M�������ɕt�����c������|���菕����������Ȃ������B�ؑ]�Ƃ͐퍑����̐헐����D�c�M���⓿��ƍN�E�L�b�G�g��ɏ����ւ������ď������B�������G�g���V����������Ėؑ]���n�ɂ������������Ԍˁi��t���j�Ɉڕ����ꂽ�B�ܔN��ɖؑ]�`�����a��������^���P�͗c�q��A��ĎO�x����̏㑺�Ƃ𗊂��Ėؑ]�ɖ߂��\���ŖS���Ȃ����B�㑺�ƂƊِՂ̑�ʎ��Ɍܗւ̓������Ă�ꋟ�{����Ă���B |
 |
���
��������ł��Â��L�^�͂P�U�V�R����P�U�W�O�N����N�Ԃ̎��@�U�߂̎������グ�����̂����ɂP�V�Q�S�N���ۂX�N���n��s�ɍ����o�������̂�����B
�u�P�U�V�W�N����U�N�X������\��
��A�T�@�����R�����������������J�R���������l�����a����T�t�J��m�s�\��
�E�̒ʂ�×�������������ᖳ�����ȏ㋝�ۂX�N�����v
�P�T�R�R�N�V���Q�N�ɔ�����������L�^���c���Ă���̂ł��̎����Ɍ��Ă����̂Ǝv����B�P�U�Q�V�N�m��낳��ɂ���𒆋��J�R����B�P�W�X�R�N�i�����Q�U�N�j�Ɍ��ݒn�ֈړ]�����B�ω����̖{���͏\��ʊω��B�P�W�Q�R�N�i�����U�N�j�R���X�������P�O���O�����{�C�s�Ƃ���P�W�Q�R�N�i�����U�N�j�̑n���ł͂Ȃ����Ǝv����B�����ɂ͏\��ʊω����𒆐S�ɉE�ɎO�\�O���ω����ɏ\���������Ŏd�������w�ɂQ�O���O�w�ɂU�O���̓V��G������B |

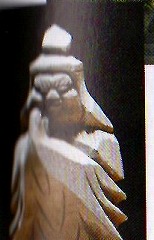
�~����ʓV��

�牮�厡��̐Ε� |
���厛
�P�U�S�P�N�i���i�P�W�N�j�K�����̉����ɂ���Ē����������a�����J�R�����Ƃ����Ă���B�����a���͕��厛�ɒʂ��Ă�����������쐼�n��̕X��}�邽�߂ɋ��J�ɋ����˂����̂Łu�������v�ƌĂ�Ă����Ƃ����B���́u�A�v�̂��Ƃł���B�����ɖ�t��������P�U�V�W�N����U�N�̎��@�����ɍڂ��Ă��Ė{���E��t���Ƃ��P�U�Q�S����P�U�S�R�N�i���i�N�ԁj�ɍċ����������ł���B
�ω����̑n���͂P�V�V�T�N�i���i�S�N�j�{���͏\��ʊω������Œ����ɂ���E���ɂ͏\���������ɂ͖�t�@���E�����E�����̎O���������u����Ă���B�R��͏��O�����˂Ă���P�V�X�Q�N�i�����S�N�j�ɒh�k�ɂ���t����Ă���B |
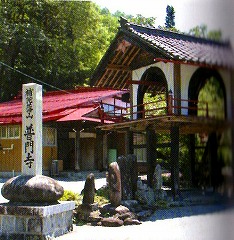 |
�O������ɓ�
�O�x�n��̎O�������̈���ɓ��ɂ͕�������ɑ���ꂽ����ɔ@���̍��������u����Ă��肱�ꂪ�ؑ]�J�ŌÂ̕����Ƃ����Ă���B�ؑ]�u���ɂ��ƌ��݂̏ꏊ�ւ͂P�U�P�Q�N�i�c���P�V�N�j�O�����̌����ɂ��Č����ꉺ���̂�������ڂ��ꂽ�B����ɔ@�����͂P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�ɒ��쌧�̕������̎w������B�����ɂ͕S�̗]��̐Ε�����������̏��l�u�����Ă��n����F��������B |
 |
���ˌ��̎\�e�R���� �i�O�x�j
�ɓߐ��t�ߑ��o�g�̋{���S���B |
 |
�݂����čՂ�
��Ԑ_�З��Ղɍ��킹�V���ɎO�x���Ղ�L��ōs���B�N�A���S����M�_�`�A���_�`�A�q����`���L������������B��M�_�`�͂U�O�O�L��������B |
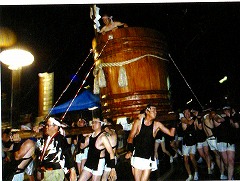 |
��Ԑ_�Б����_�y
�O�x����̌�Ԑ_�ЂŖL����F�肷��Վ��B�S�P�Q�����镑�����N�S�����R�N�őS�������悤�ɕ�����B |
 |
| ����̕X���Q |
 |
| ���͕X���Q���C�g�A�b�v |
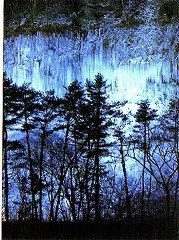 |
| �����k�J�̍g�t |
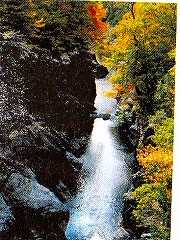 |
���ؔ���
(�ؑ]���O�x)
�w�E�����Ȃ�E�����Ȃǎ���R�O�O�N�𐔂�����������錴���сB�w�p�Q�l�сB |
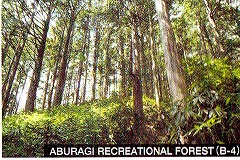 |
| ������т̑� |
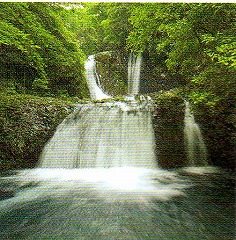 |
�s�Ղ̑�(�ؑ]���O�x)
���Â̎��ォ�炻�̗e�p��ς��Ȃ����߂��̖�������B |
 |
�S�ԑ�(�ؑ]���O�x)
��ԎR�̐�������������ƂȂ��ė��ꗎ����B |
 |
| ��ԃX�[�p�[�g���C�A�X���� |
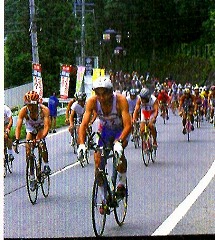 |
�P�̎}����
(���ꑺ)
����R�T�O�N�ȏ�Ō��̎w��V�R�L�O���B |
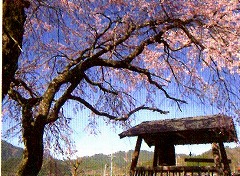 |
�X�щȊw��
(���ꑺ) |
 |
| ��ԎR�j���� |
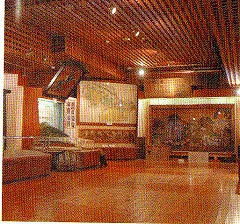 |
| ������͑��L�����v�� |
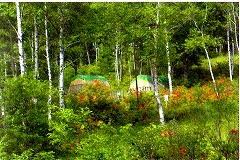 |
��Ԑ_�З��{
�{�Ђ͓V����\�O�N�i�P�T�T�S�N�j�ɖؑ]���n���`�N���Č�����Ƃ���B�c���ܔN�i�P�U�T�Q�N�j�ؑ]�㊯�R���ǖL�i�l��j�������錚�����͖����Z�N�i�P�W�V�R�N�j�Ɋ֓��b�u�Ђɂ���Č��đւ���ꂽ�B�ɂ���ďC�����s��ꂽ�B���v��N�i�P�W�U�Q�N�j�ɔ����ˎ傪��i�����̒����͍����������Ă���B |
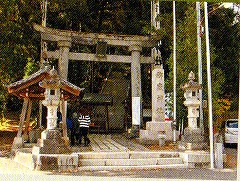 |
��Ԑ_�З���
��Ԑ_�З��{(���ꑺ) |
 |
��Ԑ_�Ў�{
�n���N��͕s�� �B���D�ɂ���Ď�����N�i�P�R�W�T�N�j�ؑ]�ɗ\��ƐM�i�\�O��L���̎��j�j�ɂ���čČ�����Ă���B�{�Ђɔ�Гa���L�����N�s����Ղɂ͖ؑ]���͂��̋����ŗ��L�n�_�����s���R����������������p�����B�Гa�͌��a��N(�P�U�P�T�N)�R���Ǐ��ɂ��Č����ꂽ�B |
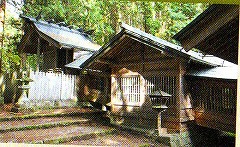 |
| �Z�i������̍g�t |
 |
| ��Ԍ� |
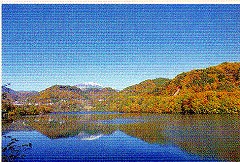 |
���R��
���쌧�����n�k�ɂ��y�Η��Ő삪�����~�߂��č��ꂽ�V�R�B�[����P�O���B�Ő[���͖�Q�O���B |
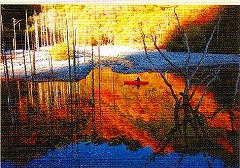
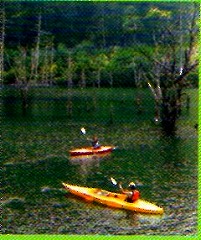 |
| ��Ԑ_�Ў�{ |
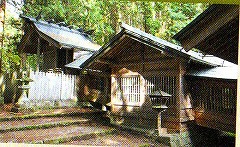 |
�S���ڏ\�j�匠��
�̂P�Q�l�̎q�����j���Ȃɐ旧��������ݎq�̓��ꂪ�Ȃ�����ʂČ�ԎR�Ɉ�S�ɋF�肷��ƒj��������o��悤�ɂȂ����Ƃ��������`��������B���̗쌱����\�j�����l���J�����Ƃ����B�����炩���{�R�Ƃ��������Ȑl�`����������悤�ɂȂ肻�����ċA��Ɗ肢�����Ȃ����N�ɂ͔{�ɂ��ċ�����Ƃ������K�����������Ă���B |

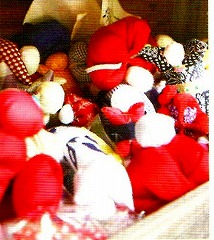 |
����܂��
��ԎR�S���ڔ��ɂ���V���a�t�߂̗�_��̋߂��ɂ���B������U���B |
 |
����(���ꑺ�喔)
���ꑺ����c�̌������������r���̑喔��㗬�ɂ���B������R�O���B��ԏC�����̏�Ƃ��Ēm���Ă���B����s�������Ɛ���ٍ��V���J���Ă���B |

 |
| �~�̐��� |
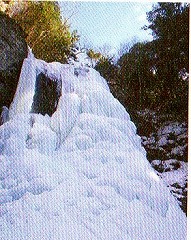 |
�V��(���ꑺ�喔)
�s�҂����������K������B�������悻�R�O���B���ꗎ�����𗠑���������邱�Ƃ��ł��u������v�Ƃ��Ă��B |
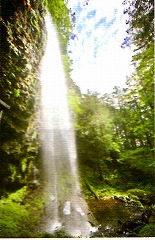 |
��x���[�v�E�F�C
�S���Q�R�R�Rm��ԂT���ځ`�V���ڂ܂ŕW�����T�W�O���[�g������C�ɓo��S���h���B�R���w�ɂ���͖ؑ]��P�x�E��Ɗx�E�����x�E�����x�E��ԎR�ȂǓ��{���\���閼�R�����Ă܂ڂ낵�̋�����W�]�ł���B |
 |
| �c�̌��V�R���� |
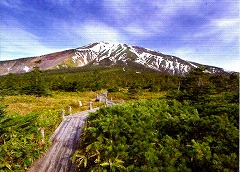 |
| �����c�̌��V�R���� |
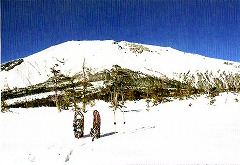 |
| ��ԎR������ |
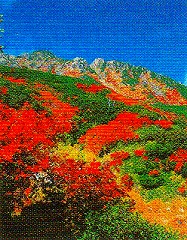 |
������㍇�ڂ̊o���s�ҕ�n
�ؑ]�ɂ���Ėk�t����̊o���s�҂͓V����N�i�P�V�W�Q�N�j�ɏC���ҁi�R���j�����o�q���邱�Ƃ��ł��Ȃ�������ԎR���y���i�œo���悤�Ɋ肢�o����������Ȃ������B�������R�N��ɖ����̂܂ܘA��Ă����M�҂Ɠo�q�����s���߂炦��ꂽ�B������̓o�R�����C�ɂ��͂𒍂��ł��������N�j�̒r�̖T��ŖS���Ȃ����B��̂͋㍇�ڂ��J���Ă���B���ꂪ���������ŌܔN��ɂ͌y���i�o�q�̋����������B���傤�ǂ��̔N�]�˂��畁���s�҂��K��ĉ���o�R�����J�݂����B |
 |
�ŏ��ɗ��Ă�ꂽ�o�����{��
�i��j |
 |
�j�̒r
�C���Q�X�O�T���̓��{�ō����̍��R�B���[�R�C�T���̐����������Ă���B |
 |
��x�R������̌�Ԑ_��
��ԎR����̉��ЁE�R�[�̗��{�E��{����ЂƂ��ē��ꂵ���B���{�̌�_�c���͏��F�V����{�͑�ȋM���A���㉜�Ђ͍��헧���̎O�_������J���Č�ԑ�_�Ƃ���Ԑ_�ЂƏ̂��Ă���B��Ԑ_�Ђł͖��N�ꌎ�l���ɑ����_�y���[���邪�\�������_�y���l�����s���Ă���B |
 |
| ��ԎR |
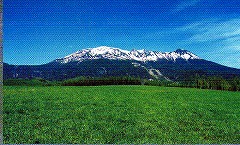
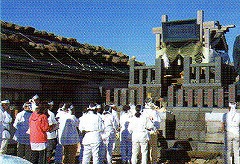 |
�ؑ]���i
��Ԃ̕�� |
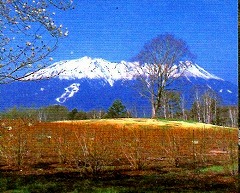 |
| �����Q�Q�S�O |
 |
| |
���@��@�� |
| �O�Y�_�� |
 |
| �O�Y���d�� |
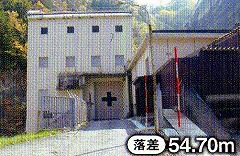 |
| ��z���d�� |
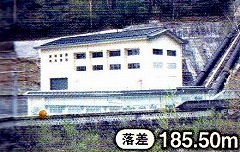 |
| �����_�� |
 |
| �q���_�� |
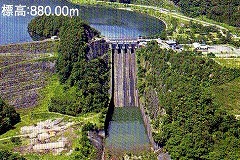 |
| ��x���d�� |
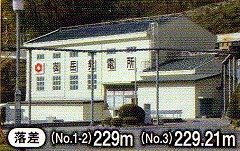 |
| ��Ճ_�� |
 |
| �O�����d�� |
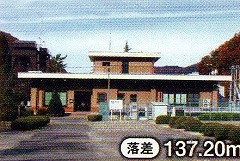 |
| ��Ք��d�� |
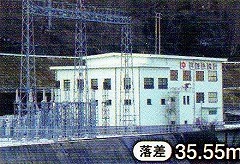 |
| �ؑ]�_�� |
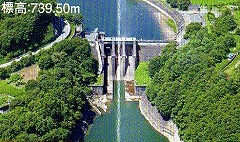 |
|
|
�S���ڂ̂P |
�ؑ]�����w
�W�F�O�O |
|
�ؑ]�����w���ӂ̒��R���͍ŏ��͕x�c����ؑ]��ɉ����ĕ���ȓ��ɂȂ��Ă��������O�N�i�P�V�T�R�N�j�̍^���ŕ��Ă��܂����B�C���̂��悤���Ȃ����S�n��։I�ĉ����։����悤�ɂ����B
����������ɉ��C���ꂽ�n�ԓ��J�݂Ō��̏ꏊ��ʂ��悤�ɂȂ����B |
|
�@
��Ԑ_�� |
|
�A
�����ꗢ��
�]�˃������\��
���֘Z����
�ꗢ�˂͍]�ˎ��㏉�߂Ɉꗢ��i�R�X�Q�V���j���Ƃɒz���ꂽ�˂ʼn|�⏼�Ȃǂ��A����ꗷ�l�̖ڈ��ƂȂ����B�ؑ]�H�ɂ͂Q�Q�J�����肻�̂����ؑ]���ɂ͋{�m�z�E�o�K�E�����̂R�J��������Δ肪���Ă��Ă���B�̂̐l�͂P���ɒj���łX�������ł��T�`�U���������Ƃ�������]�˂��狞�s�܂Œj���Ȃ�P�S������P�T���ŕ������悤�ł���B
|
 |
�����̊Ŕ�
�̒��R����n�̔w���ɉ����悹�ĉ^��ł����Ƃ��낻�̔n���ؑ]��̟��ɓ]�����A�����܂��Ă��܂����Ƃ��납�牖���Ƃ����n���������Ƃ��������`��������B |

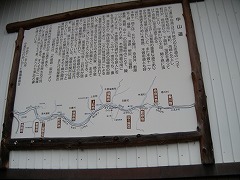 |
�B
��\�O�邳�� |
 |
�C
�ؑ]�삦��� |
 |
�D
����
���ꒃ���� |
|
�E
����������
���g���l�� |
 |
�F
�ؑ]�`���̕� |
|
| �䃖�� |
 |
�G
���� |
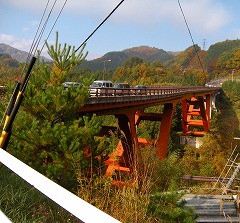 |
|
| |
|
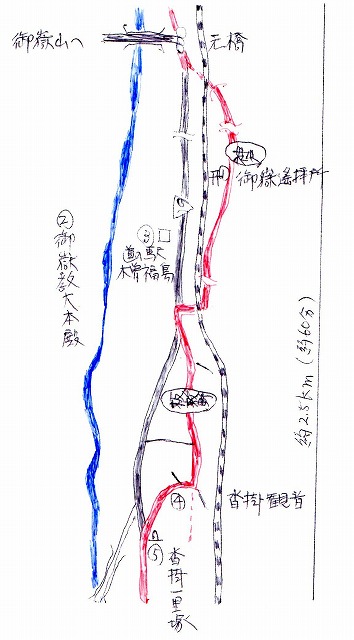
�V�c��n�̘Z�n��
|
�Z�n���͏㏼���ň�ԌÂ��n���l�ʼn���Z�N�i�P�U�V�W�j�����Ɍ������ꂽ�B �����҂̎��������ʂɒ����Ă���B |
�����_��
|
�]�˒����̑�\�I�ȎГa���z�B���N�㌎��{�ɖ����̍��O�͂̐_�c��������`����ꂽ�u�|���炢�Ɓv�Ă�鎂�q��������A�ɂ���ď㉉�����B |
| �������̂��P�l�̓`�� |
�������̐l�̑O�ɒǂ��肩�瓦���邨�P���܂����ꂩ���܂��Ă����悤���肵�܂��������l�͌�������Ēf�����B����Ƃ��P���܂͏������o���Ă��������Ƃ����������l�͏������������グ�Ċ肢�͕����Ȃ������B�r���ɂ��ꂽ���P���܂͎R�H������������̂قƂ�ɐg���B�����ǂ���ɔ���������ɂ͑�ɐg�𓊂����B�ȗ����̑�́u�B���v�ƌĂ�����K�͕P���J�������̂Ƃ����B |
| ��Ԃ̎l�� |
�o�q��C�s�ɂ͂��܂��܂Ȏ����A�����A���@�A�s��A�Ȃǂ���߂��Ă��邪��Ԃ̎l��������C�����ɊW�̂��錈�܂莖�ł���B�l��Ƃ͋g��̋����R�ȂǂŒm���Ă���悤�ɔ��S�i���j�C�s�i��j���i���j���ρi�k�j���w���B��Ԃł͌�Ԃ𒆐S�ɂ��Ă��̎l�傪��߂��k�͒��������͊⋽���i���ؑ]�������j�̐_�ː��͔�ˊX���̒�������͎O�Y�R���̔q�a�R���w�����B ��������ؑ]�J�ɓ����ď��߂Č�ԎR��ڂɂ��邱�Ƃ̂ł���ꏊ�ł���C���҂ɂƂ��Ă͏C�s�̑�ȏꏊ�Ƃ��ďd�����Ă����ƍl������B |
| |
|
|
| |
�S���ڂ̂Q |
�@
���ꡔq��
���i�Q�N�R���ǒ����Č�
���i�X�N�p�\�ʑ��̋L�^����
�����S�N�V�������@�������̉ؕ\�Ɍ��đւ����B
�k�@������
���@�O�Y�R
���@������
��@�_��
�������_�˂�ꡔq���ł͌�x�R���݂��Ȃ��̂ł��̎R�̏�ɂǂ������Ƃ����₪���肻�������x�R���q�߂邩�炻���Ŕq�ނ悤�ɂƌ����Ă����B���ǂ������ɂ͂��������������Ă��錊�����肻�̐��͖ڂɂ����Ƃ����̂ŗ��l�͎R��o���Ăǂ������̐��Ŗڂ������Ƃ����B
|
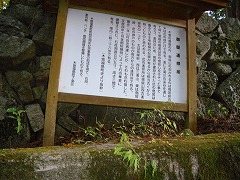

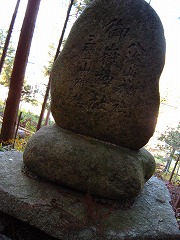 |
�A
��ԋ���{�a |

 |
��ԋ����_��
��ԐM�ł͌�Ԃɐ��܂��ԂɋA��Ƃ̍l�������Ԃ̘[�ɗ�_������ĂĐ�c�̗���Ԃ߂�B�ؑ]��Ԗ{���ł͔��Ȃ��M�҂̂��ߎO�x�ɑc��a�����������N�ԗ��Ղ��֍s���Ă���B |

 |
�B
���̉w
�ؑ]���� |

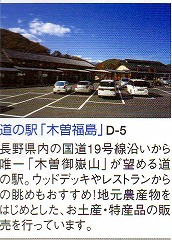 |
���̉w
�ؑ]�������猩�����ԎR |
 |
�C
�B�|�ω�
�쌱���炽���ŗL���Ȃ��̔n���ω��̉��N�ɂ��Ɩؑ]�`�����̖��n�͐l�̌��t���킩�����Ƃ����B�`�����ؑ]�̎V�̐�ǂɒʂ肩����ڎZ�Łu���\�O�Ԕ�ׁv�ƍ��߂��������B�n�͖�������܂ܐ��m�Ɏ��\�O�ԂƂ����ۂ͎��\�l�Ԃ������̂Ől�n�Ƃ��ɐ쒆�֓]�����Ă��܂����B�`���͋㎀�Ɉꐶ�ď������������킢�����ɖ��n�͎���ł��܂����B�����ŋ`���͋��̊ω����点�Ĉꓰ�����ĂĔn�̕������̂����̊ω����̂����ł���Ƃ����B�ȑO�͂���������̊ω���ɂ��������A�����l�\�O�N�̓S���̍H���̐܂ɂ��̒n�ꗢ�˂̏�Ɉڒz���ꂽ�Ƃ����B���̊ω����͓��܂�Ă��܂����Ƃ����B |
 
 |
�D
�B�|�ꗢ��
�ꗢ�˂̏�ɌB�|�ω������ڒz����Ă���B
�ꗢ�˂͐̂͒��R���̗����ɂ������������l�\�O�N�i�P�X�P�O�N�j�����{���̓S���H���̐܂ɎR���i�����j�̈ꗢ�˂͎���쑤�i�����j�̈��c���Ă���B
���֘Z�\�Z��
�]�˃������\�ꗢ |


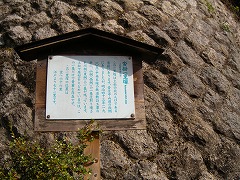 |
|
| |
|
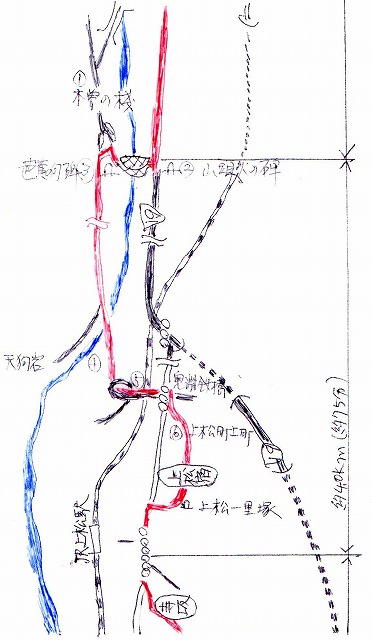 |
| |
4���ڂ̂R |
�@
�ؑ]�̎V
�̂͌�������̊ԂɊۑ��Ɣ�g�������Ō��킦���V�ł����������ۂS�N(�P�U�S�V�N)�ʍs�l�̏����ŏĎ������B�����Ŕ����˂͗��c�����N(�P�U�S�W�N)�ɒ����\�Z��(�P�O�Q��)�����ɔ���(�P�S�C�T��)�̖؋����������ΐς݂����������B���i���N(�P�V�S�P�N)�̑���C�Ɩ����\�O�N(�P�W�W�O�N)�̉��C�̓�x�ɂ킽����C�Ŗ؋��̉��̋�Ԃ͂��ׂĐΐς݂ƂȂ�c����Ă����؋��͖����l�\�l�N(�P�X�P�P�N)���S�������H���̂��߂ɂƂ菜����Ă��܂����B���ݐΐς݂̕����������P�X�����̉��ɂȂ��Ă��邪���̑S�e�����S�Ȏp�Ŏc����Ă��邱�Ƃ�������B |

���낵��ؑ]�̂����H�̊ۑ���
�ӂ���x�ɗ����ʂׂ�����
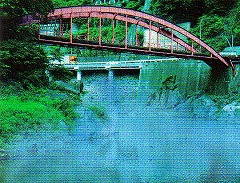
�ؑ]���i�@�V�̒��� |
��ݕǂɎc��V�����̕���
�����˂��c�����N(�P�U�S�W�N)�ɖ؋����������ΐς݂������������Ƃ��ݕǂƐΊ_�ɖ��L���Ă���B |
 |
�A
�R���̔�
�R���̔�݂̂��c����Ă��邪���̑��̔�͍H���̐܂ɖؑ]���̔��Α��Ɉڂ��ꂽ�B |
 |
| �����V�c�̔� |

 |
�B
�ؑ]�̎V�ɂ���m�Ԃ̋�� |

�����P�Q�N�F���V�����̔m�ԋ��
�V�▽������ޒӂ��Â�
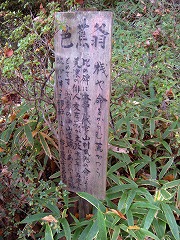
|
�m�Ԃ̋��
���̋��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��������{������č�������̂��Ƃ����B��Ɍ��������m�ԋ��̖{���͖ؑ]�����������̒Ó��_�Ђ̋����ɒu����Ă���Ƃ����B |

 |
| �����q�K�̉̔� |
 |
�C
�V��� |
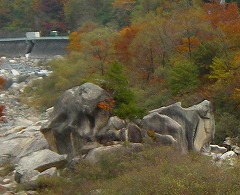 |
�D
�S���S��
�������鍑�Y�ŌẪg���X���B�吳�Q�N�{���ȓy�؋Z�t�O����\�v�̐v�ő��̉��͋������삪������B�S���S���͑S���X�R�C�W���B�������珺�a�T�O�N�܂ŐX�ѓS���Ƃ��Ďg��ꂽ�B�ؑ]�X�ѓS���͓S���̐����ŏ�����E������̋O���������ɉ�����͏��a�T�O�N�T���̔p���܂Ŋ����{�ōŌ�܂ʼn^�s����S���S���̏�Ńt�B�i�[�����s��ꂽ�B���̌�̋S���S���͎ԓ����Ƃ��ĉi�N�ɂ킽���Ēn��̌�ʂ��x���������B |

 |
��R�W���㏼�h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�R�T��
�L�d�E�p��̒��R���Z�\�㎟�̕����G�ɏ㏼�Ƃ��ĕ`���ꂽ����̑� |
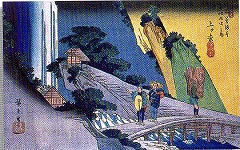 |
�㏼��
�u�㏼���Y �v |
 |
| �\���� |
 |
�E
�㏼���㒬 |
|
| �㏼���̃}���z�[�� |
 |
�F
�{���ꗢ�� �̐�
���֘Z�\�ܗ�
�]�˃������\�ꗢ�B
�]�ˎ���ɂ͍��̔���R�O�������ɓ��̈ꗢ�˂��������B�ꗢ�˂͊ۂ��y���č���Ă���̂œ�Ɍ������ĉE�������̎R�ƌĂэ�������̎R�ƌĂ�ł����Ƃ����B |

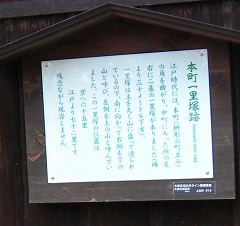 |
| ���`�̂��� |
|
| ���z�R |
 |
�ؑ]���i
���z�̐�
�㏼�h���ቺ�Ɍ����낷���z�R�̒�����ӂ͌��n������̃X�X�L�̌��B
��w�̉ĕ��������z�����߂͗Y��ɂ��đu���B |
 |
| �㏼������ؑ]��P�x��Ղ� |
 |
�ؑ]���i
��̗[��
��P�x
�W���Q�X�T�U�� |
 |
| ���� |
|
| �����{�_��� |
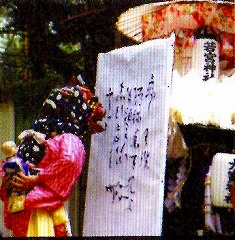 |
���{����
|
���{�����i�X�Q�P�`�P�O�O�T�j�͎��݂̉A�z�t�Œ����̉A�z���܍s���ɂ��V�̊ϑ���̍쐬�⎞�̑����⬒|�Ȃǂŋg�������Ă����B���͈��{�ۖ���͗�͂��������Ƃ��Đ��߂��锒�ρB��q�������������㐳�̂�m��ꂽ��́u�������ΐq�˂��Ă݂�a��Ȃ�M���̐X�̂���݊��̗t�v�̉̂��r�݂���Ɉ��ށu�M���ȁv�̕���͗L���Ŗ��N�t�����{�_�Ђŕ�[�̕�����������B |
| �����{ |
|
| �V�_��(�V���{) |
|
|
| |
|
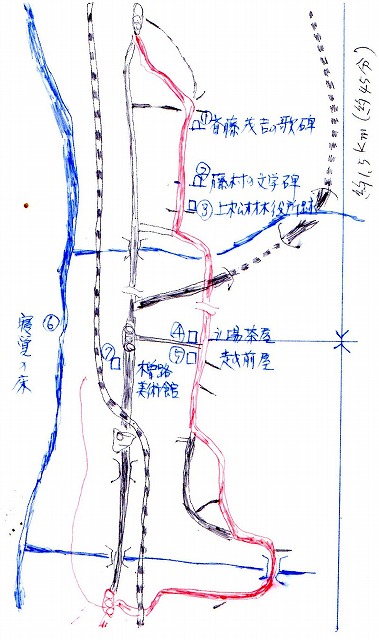
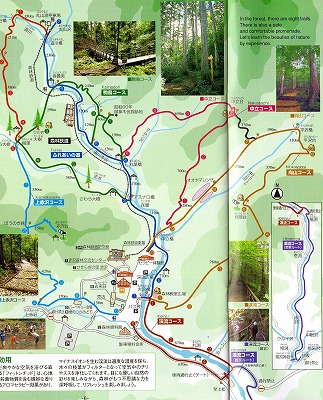
| |
|
�ԑ�
���R�x�{��
�ɐ��_�{�̗p�ޗтƂ��ĕی삳��Ă����B����R�O�O�N����ؑ]�w�̗т����X�ƍL����B���{�̐X�ї����˂̒n�ł�����B���݂͐X�уZ���s�[��n�ɔF�肳��W�̎U���H�������ĐX�ї����y���߂�B |

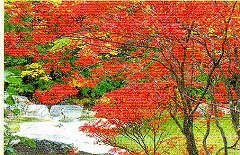 |
| �Z���s�[�̌��� |
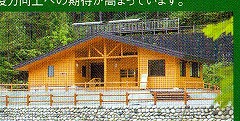 |
�X�ѓS��
�L�O�� |
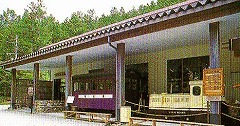 |
| �X�ѓS����� |
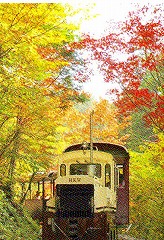
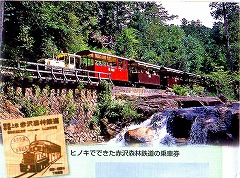 |
| �ӂꂠ���̓� |
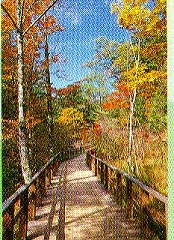 |
| ��R�[�X |
 |
| ���R�R�[�X |
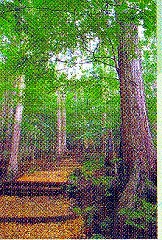 |
| �����R�[�X |
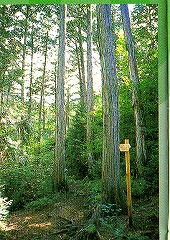 |
| ���R�[�X |
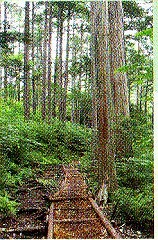 |
| �k���R�[�X |

 |
�O�R����
�Q�O�N�Ɉ�x�̑J�{�s���E��[�n�Ղɂ��킹�I�тʂ��ꂽ��_�i���L�j���g���O�R����̋Z�@�Ŕ��̂����B
��U�Q��ɐ��_�{���N�J�{�̂��ߓ`���̋Z�u�O�R����v�Ŕ��̂�����_�� |
 |
| ���a�U�O�N���̐Ւn |
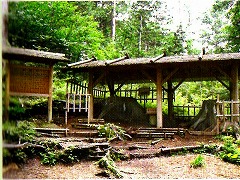 |
| �㏼�� |
 |
| |
| ���R�@�̓��L���� |
|
|
| �Q�o�m�� |
�吳�P�T�N�V���T�� |
�r������̑�����ĐQ�o�m���ɒ����B���̂�����͐앝���������݂̊ݕǂ͊�Ȍ`�ɐN�H����Ă���B��͐[���ΐF�̕��ɂȂ��ĐÂ��ł��邪���̒�ɂ͂ǂ�ȉQ�������Ă���̂��낤���s�C���ł���B���ʂ𔒂��A�����₩�ɂ��˂��Ă䂭�B |
| |
|
|
| ��P�x�_�� |
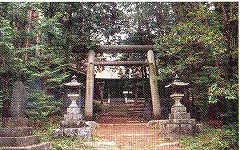 |
��P�x�_���
�O���̕��E�l�_�ܕԔq�ȂǂP�R���̕���ō\��������[�̕��B���悻�S�O�O�N�O�����q���`�œ`����O�s�o�̐_�O�̕��B |
 |
�ؑ]��P�x
�W���Q�X�T�U���B�R������͌�ԎR�E��A���v�X�E�x�m�R��]�ނ��Ƃ��ł���B�o�R���͖ؑ]���A�㏼���B |
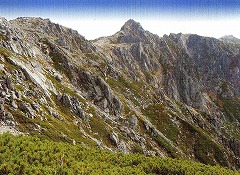 |
��{�_��
�V�Ƒ�_�E�ɕ��O�� �E�ꓛ�j�����Ր_���J��B�����̂��悻�O�Z�Z�˂����q�Ɏ�����A�ɂ���Ċe�˂̈����������s��ꂵ���E�E�j���E�����Ȃǂ̎��q�_�y����[�����B�ꕶ�l�̈�\���������ꂽ���Ƃł�����y����B���a�܋�N�i�P�X�W�S�j���ŕ����q�a���Č��z�̍ہA�q�a�O��œꕶ���㑁���̉��^���y��ЂƐΊ킪�������ꂽ�B |
|
��{�_�З�ՁE�|�K��
(�㏼��) |
 |
| �����{�_��� |
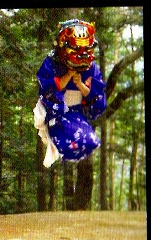 |
|
| |
4���ڂ�4 |
�ʗщ@
�ؑ]�ƂP�U��ږؑ]�`���̎��j�ʗт��n�������Ɠ`�����鎛�B��������S�N�̍����B�R��͖��a�R�N�i�P�V�U�U�N�j�ɑ��c�B
|
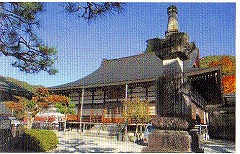
�f�x�n�j�t�q�h�m�h�m�@�s�d�l�o�k�d |
| �ʗщ@�R��O�̒n���� |
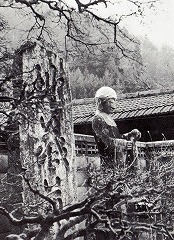
 |
�@
�֓��g�̔� |
 |
�A
�������w�� |
 |
�B
�㏼
�ޖؖ�����
�����O�N����l�N�ɂ����Ĕ����ǂ͖ؑ]���R�̌��������{�����̑唼�������s�R���������Ƃɋ����R���㊯����R�Ɋւ����̋Ɩ������グ�㏼�̌����̒n�ɒ����̍ޖؖ�����������B���̖����͓�k�U�T�ԓ����T�T�ԂłR�T�O�O�Ƃ����L���������B���͂����y���ۑ��ň͂�������������C�܂Ŕ��������łȐw���������B
�w�����ɂ͐��V�{�E�O���喾�_�F�M�c�_�{�E��ԑ匠���E�@�@�̌Ђ��J���Ă������B
|

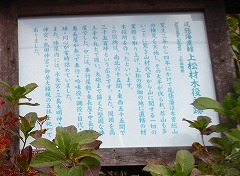 |
| �㏼�̌�w�� |
�ޖؖ����͌�w���ƌĂ�w�̊ۑ����g�����ēy���z�������ɑ�C������錘�S�Ȑw�n�ɂȂ��Ă����B �R����̋Ɩ������グ���R�����ւ̔����˂̌x�����邢�͖ؑ]�J�Z���S�ʂɑ��鎦���Ƃ����w���Ɛ��@���ꂽ�B���ʌ��ւ̎��ځi��C�O���[�g���j�̍��y��Ɂu��w���̏��v�ƌĂꂽ�����A�����Ă����Ƃ����B |
| �z�K�_�� |

 |
| �z�K�_��� |
 |
�А_��
�Зl�Ɛe���܂��А_�Ђ͓V���N�ԁi�P�V�W�P�`�P�V�W�W�j���̍ޖؕ�s����쌹�����ؑ]�R��̈��S�Ƃ����ɓ����[����قɉ���⎖�̂��Ȃ����Ƃ�����Č������ꂽ�Ɠ`������B�ЂƂ͌�ԑ匠���A�M�c��_�{�A�V�Ƒ�_�A�O����ЁA���V�{���w���B�㏼�ޖؖ������J���Ă����������S�N�i�P�W�V�P�j�ޖؖ����̔p�~�����ɐz�K�_�Ђ̋����Ɉړ]���ꂽ�B |
|
��������
���ꒃ�� |
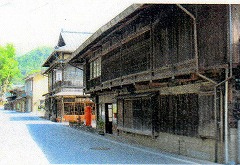 |
�C
���ꒃ�� |

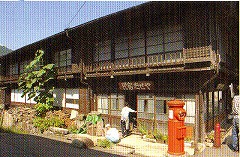 |
�D
�z�O�� |
 �\�ӎɈ�オ������ �\�ӎɈ�オ������
������̖���
�߂��Ԃ̂�����������l�͂ނ��߂ɕ@�т̂��₷��� |
�E
�Q�o�̏�
�u�Q�o�̏��v�Ƃ������O�͔ӔN�����̒n�ʼn߂������Y�����Y�`���ɗR������B�ؑ]��̗��ꂪ�ԛ����N�H���Ă���ꂽ�B�����┧�̊��͛�����E���q��E���ȂǂƖ��t�����Ă���B |
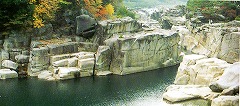
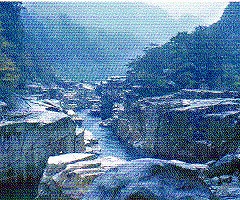
�ؑ]���i�@�Q�o�̖�J
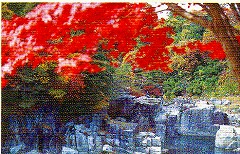
|
�Q�o�̏��@
���̏��
�Y���� |
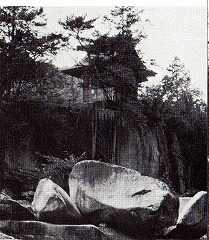 |
�Ր쎛
�ؑ]�H�����_
�ٍ��V |
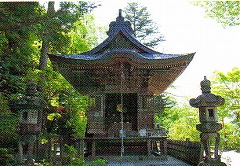 |
| �Ր쎛 |
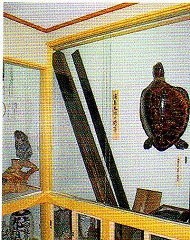 |
�����m�Ԃ�
��� |
 �Ђ��ɂЂ�Q���ӂ��̏��̎R �Ђ��ɂЂ�Q���ӂ��̏��̎R |
�����q�K��
��� |

���_��t��t�̎O�\�� |
�Ր쎛�����̉����L��
��� |
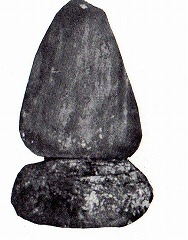
�������m�ɉ�������ސ��炵 |
�F
�ؑ]�H���p�� |
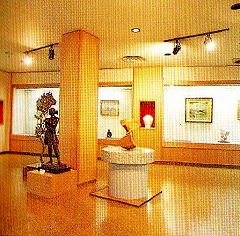 |
���Q�o
�P�O���قlj����ɂ������ߗ��Q�́u���Q�o�v�ƌĂ��B |
 |
�j�̖�
��������㏼���̌j�̖̒��ň�ԑ������̎��͂͂S�C�P��������B
���̏�Ŕ��������R����̍ۂɗ���Ă����j�̕c���傫���Ȃ����Ƃ����`�����c���Ă���B |
 |
| ���싴���C�L�O����� |
|
|
| |
|
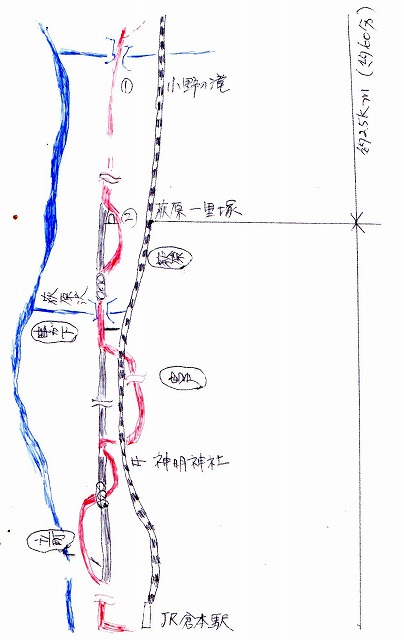
| ���R�@�̓��L���� |
|
|
| ����̑� |
�吳�P�T�N
�V���T�� |
�r������̑�����ĐQ�o�m���ɒ����B |
| |
|
|
�ؑ]�Ó��i�M�Z�H���R�����j
���R�������������ȑO�����ʘH�Ƃ��ė��p���ꂽ�Ñ�̃o�C�p�X�B�ؑ]��P�x�R�[���k�ɉ��юR�Ԃ̏W����H��B |
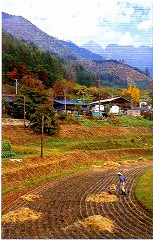 |
���숢��ɓ�
�ؑ]�J�ōł��Â��������Ƃ����Ă���B |
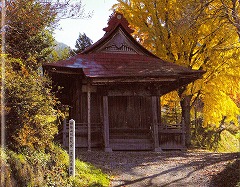 |
���숢��ɓ��̓V��
�R���㊯���������̊G�t�r��T�삪�`�����Ԓ��̊G������B |
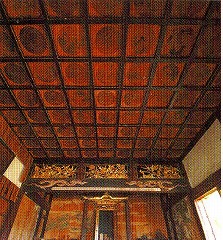 |
| |
|
| |
|
|
| |
4���ڂ�5 |
�@
����̑� |

�ؑ]�C���Z�\�㎟�V���E��P��
�L�d�ƒr�c�p��̕`��
���R���V���[�Y�̂R�X�Ԗ�
|
����̑�
�����A���v�X�ؑ]��P�x�Ɍ��������\�㍆�̂����e�ɗ��ꗎ�����
������P�T��
�u�u�낽���Ɂ@�ݗނЂƂ����͎�s�����
����Ƃ܂��ӂ��̂̑���v
�㗌�r���ɖؑ]��������y���ΎO�̘a��
�r��T�앃�q�̔ʼn���c���Ă���B |

�n�m�n�|�m�n�|�s�`�j�h�@�e�`�k�k�r

�ؑ]���i�@������e�z
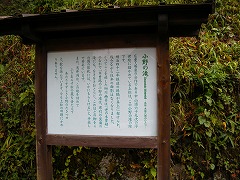 |
| �����_�� |
|
�A
�����ꗢ�� |

 ���֘Z�\�l�� ���֘Z�\�l��
�]�˃������\�O�� |
| ����ݍ� |
|
| �_���_�� |
|
| �ؑ]�Ó� |
 |
�����V�c
��x�e�� |
 |
| �Q�o���d�� |
 |
| �B�� |
|
�q�{�w
�Q�F�P�O |
|
|
| |
|
| 5���� (�����Q�T�N�P�P���P�R���@���j��) |
�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�R����) |
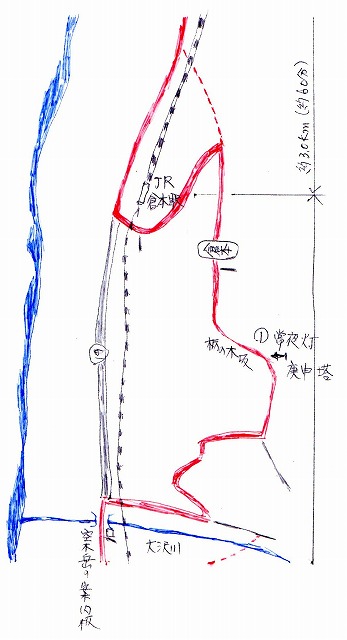
|
| |
5���ڂ�1 |
�q�{�w
�W�F�O�O |
|
| �Ȃ̖؍� |
|
�@
�q�{�̌Â��M�\�� |

 |
| ��铔 |
 |
���R����
������� |
 |
| ���R�� |
 |
| ��؊x�̈ē��� |
|
|
| |
|
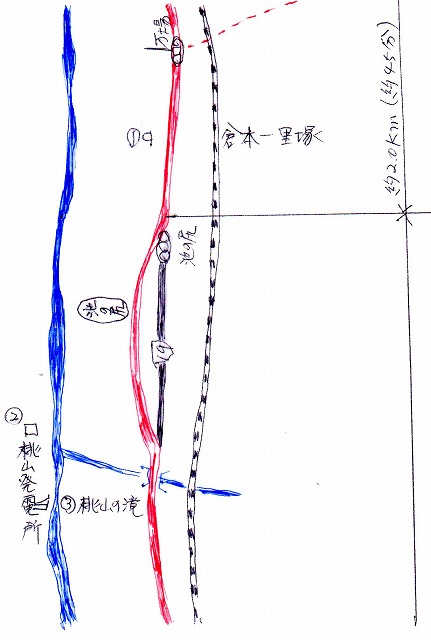 |
| |
5���ڂ�2 |
�@
�q�{�ꗢ�� |
|
�A
���R���d��
���{�ŏ��̓��E���T�C�N�����˂̒n |

�����V�X�C�T�T�� |
| �㏼���d�� |
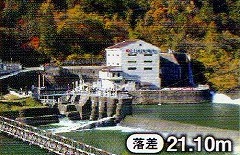 |
|
| |
|
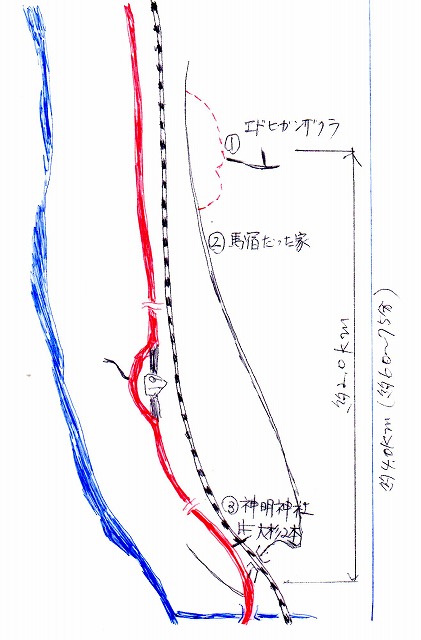 |
| |
5���ڂ�3 |
�@
�G�h�q�K���U�N�� |
|
�A
�n�h�������� |
|
| �̂����Ǎ����̈ē��� |
|
�B
�_���_�� |

 |
| �v�w�吙 |
 |
| �����R�o�R���̈ē��� |
|
|
| |
|

| ���R�@�̓��L���� |
|
|
| �菟�� |
�吳�P�T�N
�V���S�� |
�菟���Ƃ������h�Ȏ�������B�����̂ǂ����ɓV���𐰂炵�Ăق����Ɨ����f����B�����͗R�����鎛�Ŗ����V�c�̍s�ݏ��ł������������B |
| |
�Ɂ@�߁@�� |
| �ɓސ��d�� |
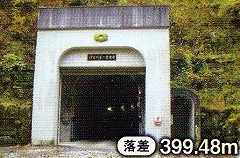 |
| ���V�d�� |
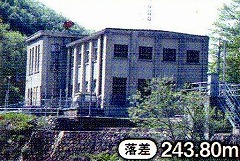 |
| �c�����d�� |
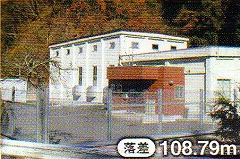 |
| ���ꔭ�d�� |

|
|
| |
5���ڂ�4 |
�@
�K�c�I�����w��
�{���h�͍K�c�I���̕������̕���ƂȂ����B |
 |
���M�Ɖ̔�
�{���͐̂��琴�����N���Ă����B
���M�͐{���h�̐����ɂ����i��ɃT�����j�����蔲���č���Ă���B |
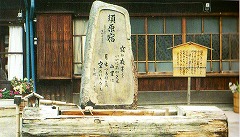
 |
�����q�K��
�̔�
�Q�ʖ锼��
�����ɂ�������
�R����
���o�Â�قǂ�
�ɂ��Ȃ� |
 |
�A
�{���h�ꗢ�� |
 |
��R�X��
�{���h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�Q�S�� |
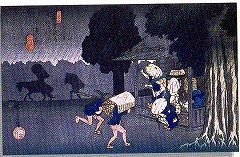 |
| ���O�_�� |
|
| �����_�� |
|
�S�C����
�����钷�������� |
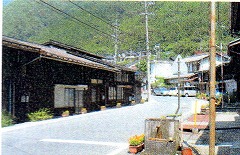 |
�B
�����̍� |
�{���h�̖��` |
| �{���h���D�� |
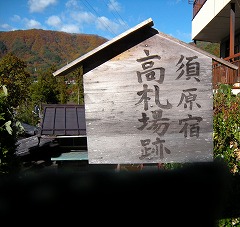 |
| �������_�� |
|
�C
�菟��
�ՍϏ@���S���h�̎��@�B
�菟���͖ؑ]�H�̒��̍ŌÙ��B�Ìc�N�ԁi�P�R�W�V�N���j�ɖؑ]�������������Ɠ`������B��̖{���E�O�畘�̎R��E�ɗ��͓��R�������Ƃ��č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B
�ؑ]�H�����_
�z�ܑ� |

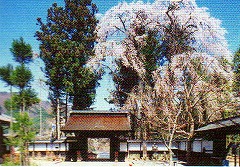
 |
�菟���B��
������̐��� |
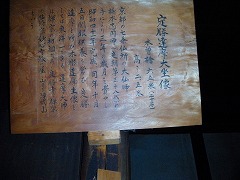 |
�菟��
�B������ |
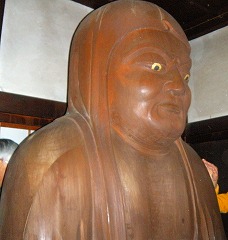 |
| �d�͎����� |
|
| ��K�����j���������� |
 |
|
| |
|
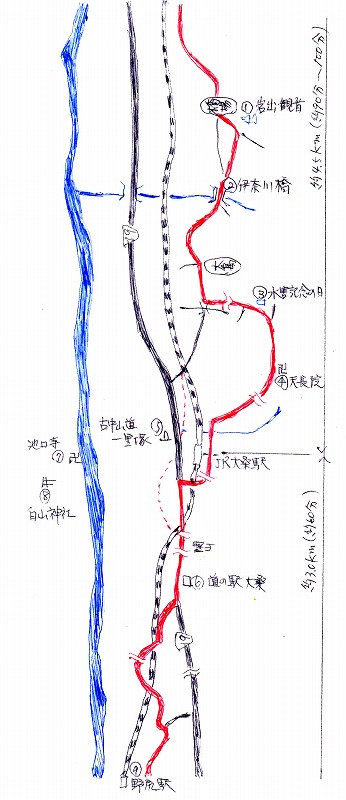
�E
�ڗ��R�r����
��t��
�P�R�O�O�N�㏉���Ɍ������ꂽ���q���z�l����������ؑ���������B�Ԍ��O�ԉ��s�l�Ԃœ����ɖ�t�@�������A����������F���������u����Ă���B |
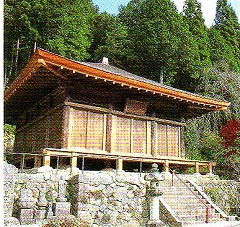 |
�F
���R�_��
���q�����ɑn������Гa���z�Ƃ��Ă͒��쌧�ŌÂ̂��̂Ƃ��č��w��̏d�v�������ƂȂ��Ă���B��ԎЗ��O�畘�B���R�_�Ђ𐳖ʂɍ��E�ɑ����E�ɓ��E�F��̎l�Гa������ł���B |
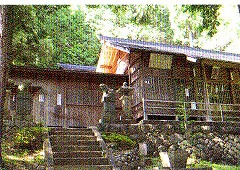

��ԎЗ����O�畘���̒��쌧�ŌÂ̊��q���z |
| �̂����ǐX�ь��� |
 |
|
| |
5���ڂ�5 |
�@
��o�ω���
�ʖ����ɓߐ�ω��܂��͋���ω��Ƃ����B
���`�ɂ��ƎO�S�]�N�O�{���̈�V�����n�̌B����鏤�������Ă����B�������l�̈Ќ�����n��̎����n�̌B�����߂����܈������Б��������Ȃ������̂ł��̎|��`���s���������ォ��ǂ������Č��݂̋���̓����t�߂œn�����B���͊��ő����n�����Ƃ������V���͎��̑��e�ɑł���đ�������ނ����Ƃ���T��ɂ������ؕЂ��Ƃ点�n��Łu�n���ϐ����v�Ə����ēn���u�K�������M����B�䗘�v������ł��낤�v�ƌ����ė����������Ƃ����B���ɂ���������ϊω��Ƃ������B�V���͂�����ƂɎ����A��_�I�Ɉ��u�����Ƃ��������������̂ŋ��������ċ���̊�o�R�̊�Ԃ��J�����Ƃ����w�q�X�ƌ�����������B���ߋ��ߍ݂̕]���ƂȂ藈�q������̂������Ȃ����̂ŁA�ߗׂ̏��͂Ă��̖ؕЂɊϐ�����F�ƍ����s�܂ŏo�����Ė��S���̖��m���t�̊J����Ď����A���F���������ĕ�������Ƃ���M������̑����ꌎ�\�����A�̏��߂̉����ɂ͉�������吨���Q��ɗ�����悤�ɂȂ����B |

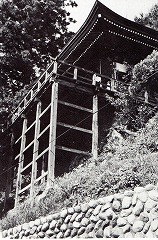
�ؑ]�̐������Ƃ�����B
�p��u�ؑ]�X���E�ɓߐ싴���i�}�v�ɕ`���ꂽ�R������


�]�˒����Ɍ������ꂽ���R����̊ω����B�����̊G�n����[����Ă���B
|
| �����k�����R�����̈ē��� |
|
�A
�ɓސ싴 |
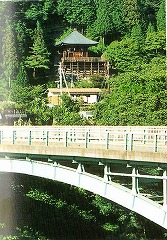

|
�ɓߐ�k�J
���P�x�E��؊x�E�z�S�R�̓o�R��������k�J�B�f�R�̒�����ѓ��������Ă���B |
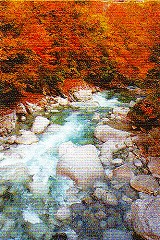
 |
| �����_�� |
 |
| �P���� |
|
�B
���Q�L�O�� |
 |
�C
�V���@
�V���@�͎�������ؑ]�ƋF�菊�Ƃ��Đ^���@�ɑ����ؑ]���Ó������̈ɓސ���̒n�ɋe���R�L�����Ƃ��Ă��������V���N��(�P�T�S�O�N�`�j���c�R���邢�͎R���̏Ă��ł��ɂ��p�₵�Ă��܂����Ƃ����Ă���B���̌㕶�\�N��(�P�T�X�S�N�`�j�菟������V�S�a�����J�R�Ƃ��đT�@�n���@�V���@�Ƃ��ċ��n�ɊJ����X���̕ϑJ�ɂ�芰���N�ԁi�P�U�U�Q�N�`�j�n�����̂��������̏h����̌��ݒn�ֈړ]�����݂Ɏ���B |



|
| �V���@�̃}���A�n�� |

 |
| ���a���� |
|
���ߓ��
�|�������
���̂�����̉Ƃ͌��ւɈ�N�����ߓ�������Ă���Ƃ����B��̐^�ɂ͉��N�̂����Ƃ������Y���n�̎}����������ł���B |
 |
��K����
�}���z�[����
�}�� |
 |
| �n�� |
 |
| �o���̂���� |
 |
| �f��Ђ���V���[�Y�̃��P���s��ꂽ�� |
 |
���R��
�ꗢ�� |
 |
| �֎R |
|
�E
���̉w��K
�P�Q�F�O�O
���H |
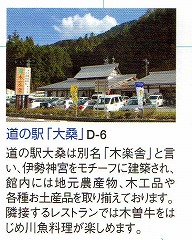
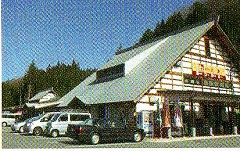 |
| �ɓސ씭�d�� |
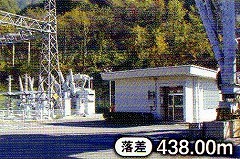 |
| �{�����d�� |
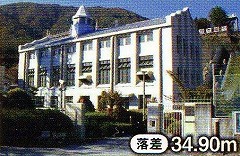 |
| �ؑ]���d�� |
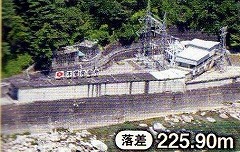 |
��K���d��
����͑哯�d�͎В��ɏA���Ă����K�A�{���A���R�A�Ǐ��̊e���d�������X�Ɍ��݂����B |
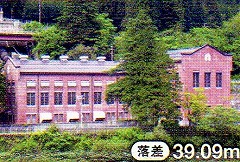 |
��K��K
���d��
�����Q�R�N�U��
���d�J�n
�S�X�O�j�v |
 |
| ��K����� |
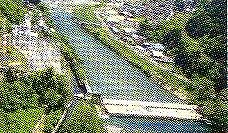 |
| �q�� |
|
| ���D��� |
|
| �{�w�� |
|
�H
�i�q��K�w
�Q�F�P�O |
 |
|
| |
|
| 6���� (�����Q�T�N�P�P���Q�O���@���j���j |
�ؑ]�J�{�s�@���R����(��P�Q����) |
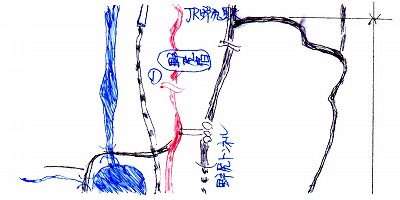 |
|
6���ڂ�1 |
��K�w
�W�F�R�O |
|
��S�O��
��K�h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�P�X�� |
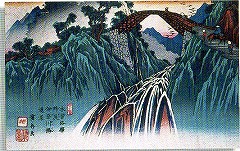 |
�@
��K�h |
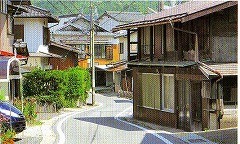
�O�G��h�����߂̋Ȃ��肭�˂��������݂������Łu���Ȃ���v�ƌĂ�Ă���B |
| �u�͂���v�Ƃ��������̉� |
|
| �^��`�O�ǖ�h�u���j�̓��v |
|
|
| |
|
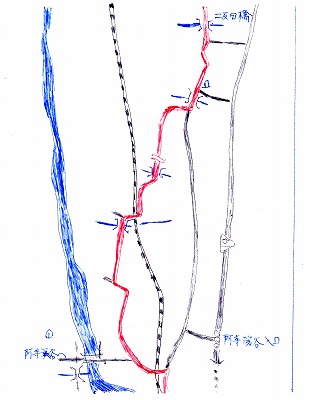
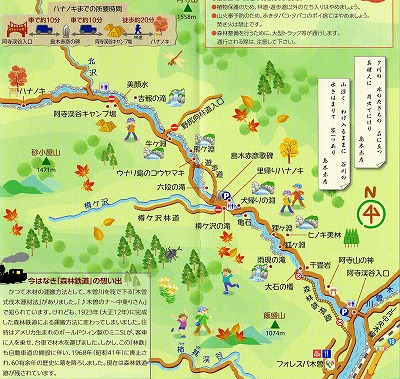
�@
�����k�J |
��K�w����k���Q�O���ň����k�J������֒���

 |
| �t�H���X�p�ؑ] |
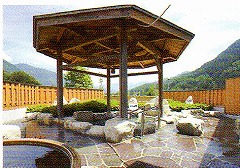 |
����
���̊�̉��ɗ����Ď��܂��ƒJ��̐�����������������������Ɍk�����قƂ����Ă���悤�ȍ��o����B�ꖼ�u������v�Ƃ������B |
 |
| �݂苴 |
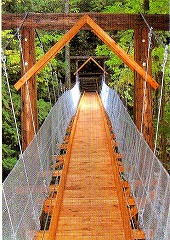 |
| ���A��̕� |
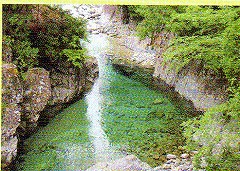 |
�K����
��
�ς�K���u���g�v�̏o���f�������̑���ɉf���Č����ƌ���ꖼ�Â���ꂽ�B |
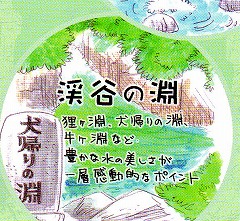 |
| |
|
| ���P��(��K����K) |
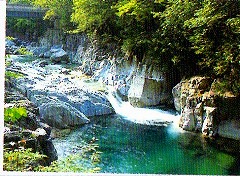 |
�J���̑�
�M����̑�
�Z�i�̑�
�g��̑� |
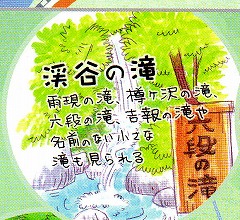 |
| �g��̑� |
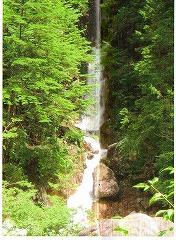 |
| �q�m�L���� |
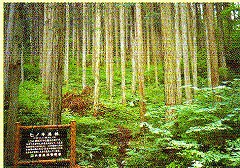 |
| ���ؐԕF�̔� |

�R�[���킯����܂܂ɒJ���
�����͂܂�ĉƈ�c����
�[��̐��̂������̐ɗ���
�^���l�Ɍ��o�łɂ���
|
| ���琅 |

 |
| �������L�т̃n�i�m�L |
 |
| �Ǐ��_�� |
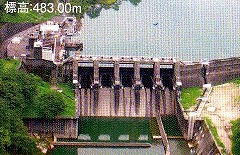 |
| |
|
|
|
�U���ڂ̂Q |
����
�ꗢ�� |
|
| �֔��� |
|
| �n���ω� |
|
| �Ȑ_�� |
|
�����_��
�����_���� |
 |
�@��R���o��
�ؑ]�H�����_
�单�V
�ՍϏ@���S���h�̌Ù��B�P�R�O�O�N���ɑn���B�P�U�Q�S�N�ɍČ��B |
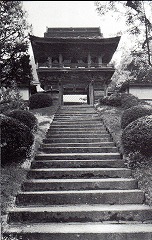 |
���o����
�}���A�ω� |
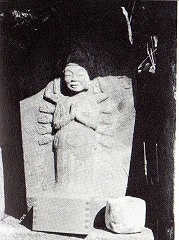 |
| ��̒n���� |
 |
�{���j�_��
�{���j�_���� |
 |
| ���l�� |
|
���O���
�L���K���������낤�Ɠ��O��̌��̏o��q�Ɠ`�����Ă���B |
|
�\�j��
|
|
| ���ꂠ�� |
|
|
| |
|
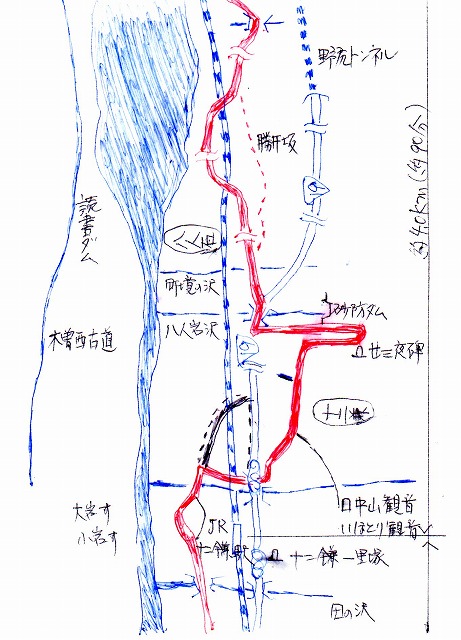 |
|
�U���ڂ̂R |
| �ؑ]�F��_�� |
|
���ڂƂ�ω�
���̊ω����ɂ���̌C�ł�������n���Ƃ��Ƃ�����B |
|
| �\�j���ꗢ�� |
|
| ��Q�o |
|
| �����_�� |
|
|
| |
|
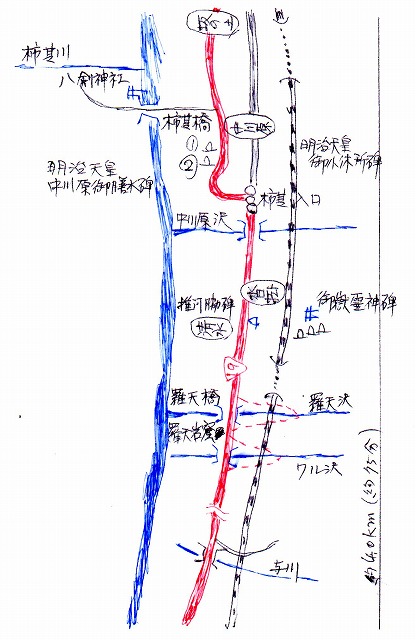
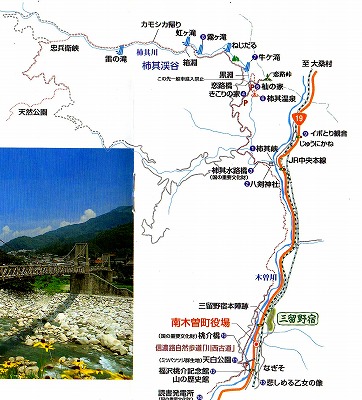
�����_��
�����̑吙�͖ؑ]�ł͒������F�쐙�Ŏ�����Z�N�]��B�l�{�̐����ꊔ�ɂȂ��Ă��āu�悷���v�Ƃ�������B���̓V�R�L�O���B |
|
�@
�`�����H��
�S���P�S�Q�C�T����d�A�[�`���Ƃ����S�R���N���[�g����B���̏d�v�������i���w��ߑ㉻������Y�j �Ǐ����d���ɑ������鐅�H���B���������O�̐��H���̒��ł͍ő勉�̂��́B |

 |
������̉�
�]�˖����̕��v�l�N�i�P�W�U�S�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ���Ƃ���̕����B |
|
�`����
�u��Q�o�v�Ƃ�������u�Q�o�̏��v�̃~�j�`���A�ŁB�ؑ]���̍L���͌����o�b�N�ɉԛ���̒���ߗ����Z�H����Ĕ������p�������Ă���B�ʖ����͌����Ƃ��Ă��B |
|
| �[�̉� |
|
���P�� (��ؑ]���Ǐ�)
�ԛ��������ʂ��Ċ`����{������������B |
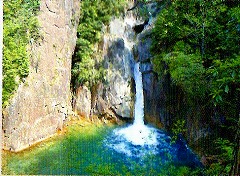 |
| �˂����� |
|
| ���P�� |
|
| ���P�� |
|
| �J���V�J�A�� |
|
| ���̑� |
|
| �����q�� |
|
�Ǐ����d��
�吳�P�Q�N�ő�o�͂S�O�V�O�OkW�̐��H�����d���B
���̏d�v�������i�ߑ㉻��Y�j�Ɏw�肳��Ă���B�i�����U�N�P�Q���Q�V���j
�@���d���{��
�i�S�R���N���[�g����A�����K�ǁA�������\���j���~�`�̑��▾���葋�Ȃǂ̋ߑ㐼�m�l���ӏ��������B
�A�����E�����S��
�B�`�����H��
�C����i��ؑ]�����L�j |
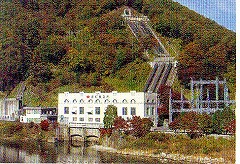 |
�`���k�J
�����ɂ킽���đꂠ�萣����̕ω��ɕx�k�J |
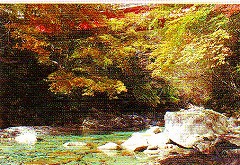
 |
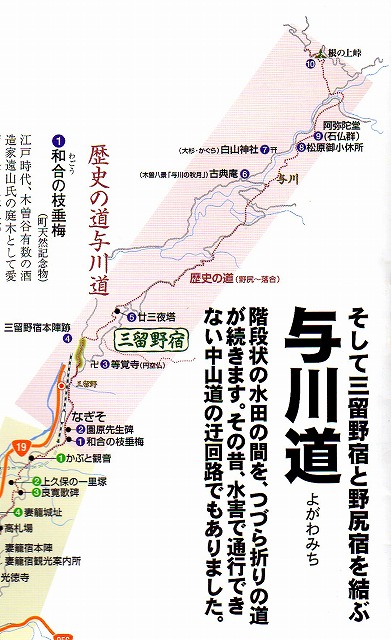
|
|
6���ڂ�4 |
�M�Z�H
���R����
�쐼�Ó� |
|
| �����V�c�䏬�x���� |
|
| �����V�c���͌���V���� |
|
| �B�| |
|
| ��ԗ�_�� |
|
| ���͘e�� |
|
| ���V�̎V�� |
|
| ���V |
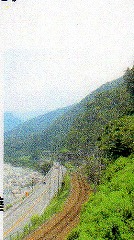 |
| �֔����̒n�� |
|
���̏㓻
�^��Ɩ�K�̍�̓��B���Ă͂����ɂ��䏬�x�����݂����Ă����B |
|
�^��
���̉��Ɍ��̖����u�^��̗��v������B |
|
| ���m���ꗢ�� |
|
����ɓ�
�����ɂ͍M�\��E����Q�q��E������Ȃǂ̐Δ肪����B �Â����̂͌��\�ܔN�i�P�U�X�Q�N�j�̂��̂�����B |
|
����
�䏬�x��
�䏬�x���͍��M�ȕ����ʍs����ۋx�e���Ƃ��Č����炵�̗ǂ��ꏊ�Ȃǂɐ݂����Ă����B |
|
| ���R�_�� |
|
���R�_�Ђ̑吙
���̓V�R�L�O��
�吙�͓�{����P�{�͖ڒʂ���͂W�C�Q�����̂P�{�͂U�C�V������B |
 |
| ���R�_�Ѝ� |
 |
�ÓT��
�]�ˎ��㏉���ɑm�V�ÓT���̂������Ƃ��� |
|
�ؑ]���i
�^��̏H��
�^��n��̌ÓT�����璭�߂�B |

 |
| �^��̏H���ό��� |
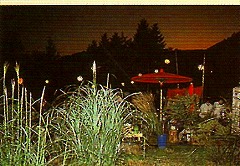 |
���O�铃
��\�O��̒x�����̏o��q�ݖL��Ȃǂ��F�閯���M�̓� |
|
|
| |
|
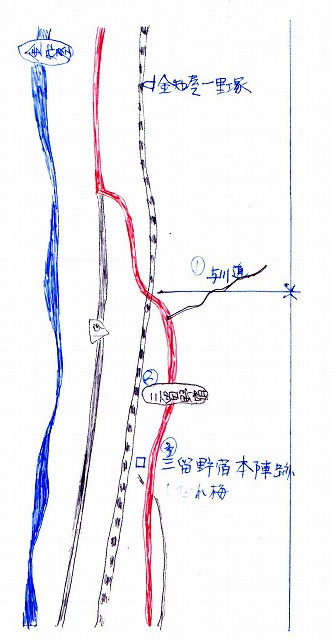
 |
|
6���ڂ�5 |
��S�P��
�O����h
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�R�Q��
���Ă������͖̂�K�E�O����h�Ԃɒ��R���ő�̓�u���V�̎V���v������������ł���B
�����P�S�N�i�P�W�W�P�N�j�̑�łقƂ�ǂ��Ď������B |
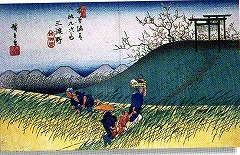 |
�@
���V�̓�������^�쓹.�B���̐̐��Q�Œʍs�ł��Ȃ����R���̉I��H�ł��������B |
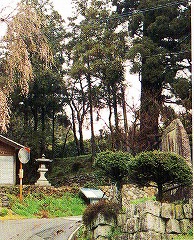 |
�A
�O����h
�ЂŏĂ��킸���ɖʉe���c���Ă���B |
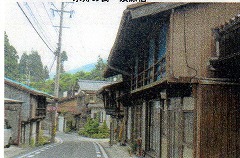 |
�O����
�e�{�w�� |
 |
| �^�쓹����_ |
|
�B
�{�w�Ղ�
�}���~
�}����~�͒��̓V�R�L�O�� |
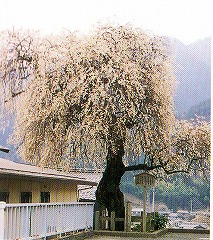
 |
| �����V�c��V�� |
|
| �^�씭�d�� |
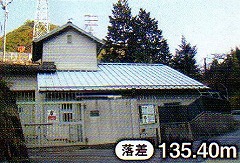 |
�ɐ��R�i�P�R�V�R���j
�吳�P�Q�N�܂ňɐ��_�{���N�J�{�̌�p�ނ́E���o |
|
| �֔����̔� |
|
|
|
|
| |
|
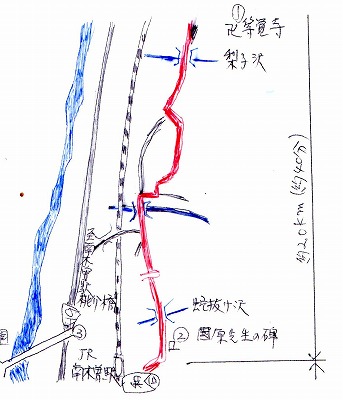
|
| |
6���ڂ�6 |
�@
���o����
�~��
�~�͓�ؑ]���ɂU�̂��蓙�o���ɂ���ʓV���ȉ��R�̂�����B |
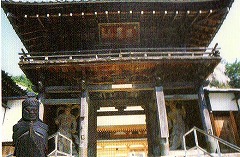

 |
�A
�����搶�̔�
�O���쓌�R�_�А_���̉Ƃɐ��܂ꂽ�������x�͍]�˒����̐_�w�҂Ŕ����E���Z�E�M�Z�ɖ�l������i���Ă����B |
 |
�P�Q�F�O�O
���H |
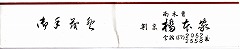 |
�B
���
�d�͉�����ؑ]�J�̓d���J�����ɉ˂����S��247
�������Q�C�V���̖̂ؐ�����������ő�ŌÂ̖ؐ����B�Ǐ����d�����z�̎��މ^���H�Ƃ��đ��点�����B�吳�P�P�N�X���Ɋ����B
���̏d�v�������i�ߑ㉻��Y�j
�^��{�̔F�̈Ⴄ���͐X�ѓS�����ʂ����O���̐Ղ��c���Ă���B |

 |
�C
�V������ |
 |
�߂��߂鉳���̑�
���a�Q�W�N�V���̈ɐ�������̎֔����i�R�Ôg�j�]���҂𓉂�ł���ꂽ�B |
|
����
�L�O��
����吳����Ɍ��Ă��ʑ��B�����K����̌����ɂ͓���Ə��D����z�̈�i���W������Ă���B |
 |
�R�̗��j��
���ďh�̖{�w�Ւn�ɂ�������������̌䗿�Ǎ��ďo�����̌����B |
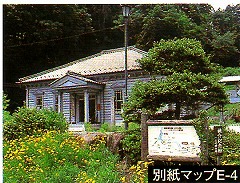 |
|
| |
|
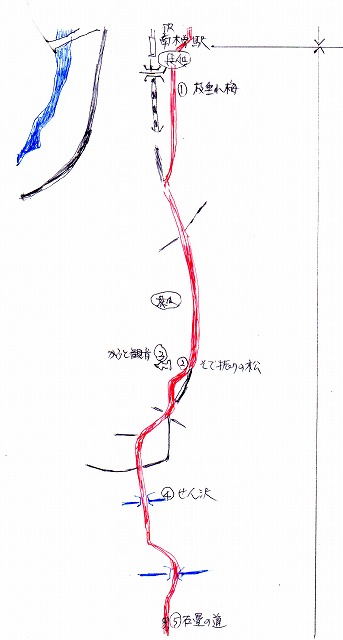 |
| |
�U���ڂ̂V |
�@
�a���}����~
���V�R�L�O���B�]�ˎ���ؑ]�J�L���̎Ɖ��R���̒�B |
 |
�_��
���ꂠ�� |
|
�A
�`���b���U��̏� |



|
�B
�ؑ]�`���̊��ω�
�ؑ]�`�����k���H�ɏo������Ƃ��鎞���ԂƂ̔������̊ω������J�����̂��͂��܂�Ƃ����`�����Ă���B |

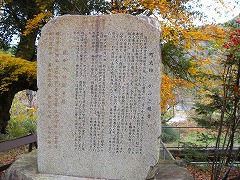 |
| �ό`�T���H |
|
�C
����� |
 |
�D
�Ώ�̓� |
 |
| �啽�� |
 |
�啽���̖ؑ]������
�M�B�̃T���Z�b�g�|�C���g�S�I |
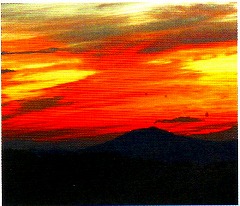 |
|
| |
|
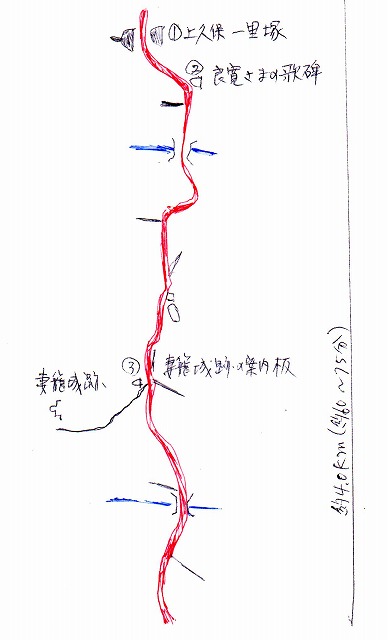 |
| |
�U���ڂ̂W |
�@
��v�ۈꗢ��
�]�˂��琔���ĂV�W���ڂ̒ˁB���`���Ƃǂ߂Ă���B���j�� |
 |
�A
�NJ����܂�
�̔�
�]�ˌ���̉̐l�NJ������̕��߂�ʂ����Ƃ��ɉr�܂ꂽ�a�̂̉̔� |

���̕��̂��̔߂����Ɏᑐ��
�ȌĂт��Ăď��������� |
| �� |
|
�B
������
�ē��� |
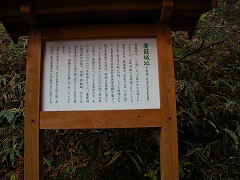
 |
����
���쌧�j�ՁB�퍑������ؑ]�̓�̉������Ƃ��ďd�v�ł������B���ď�͎�s�E�j�̊s�E��x�E�ыȗւ����Ȃ����K�͂̑傫�ȎR��Ŏ�s����͍��ďh�E�O����h����]�ł���B���q�E���v��̐킢�̐ܓ���R�ɑ��ē�U�s�����ւ����Ƃ����Ă���B |
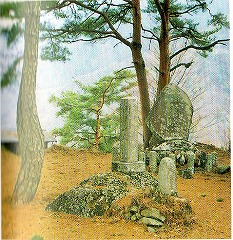 |
| ���ď�Ղ���̓W�] |
 |
|
| |
|
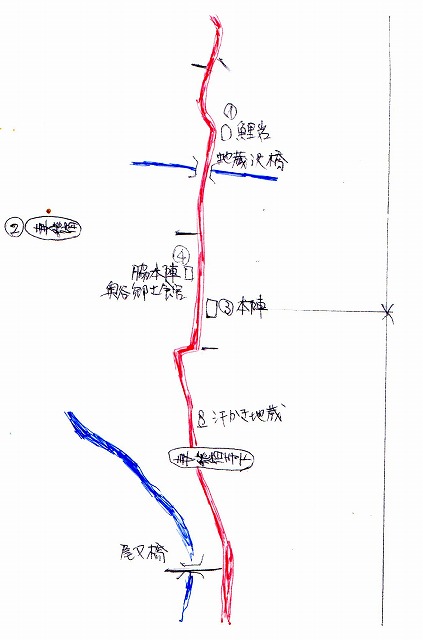
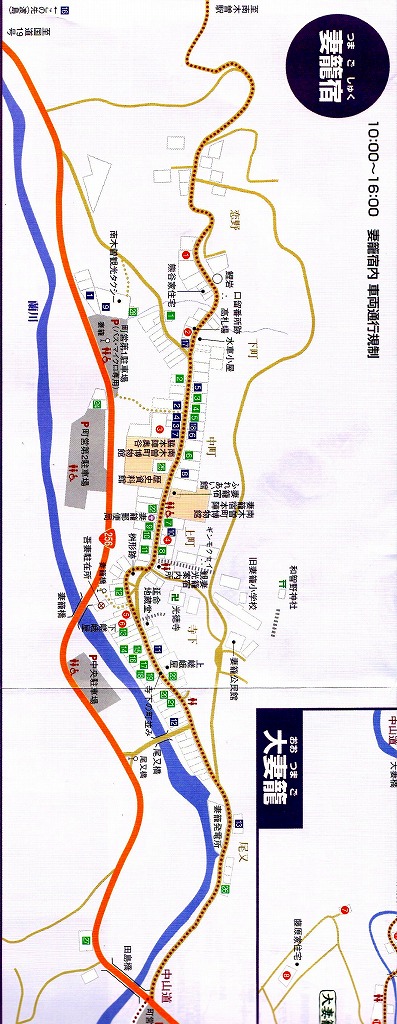 |
| |
�U���ڂ̂X |
�@
���
�傫�Ȍ�̌`��������Œ��R���O���̈�ł������������Q�S�N�̔Z����n�k�Ō`���ς���Ă��܂����B
�u�ؑ]�H�����}��v�ɂ͌��Ɍ������ĉj���p���`����Ă���B |


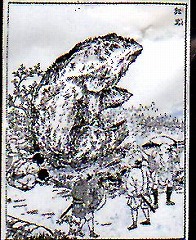 |
��S�Q�����ďh
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�R�P��
�c���U�N�i�P�U�O�P�N�j����ƍN�ɂ���ďh�w����߂��]�˂���S�Q�Ԗڂ̏h��Ƃ��Đ������ꂽ�B�����ȍ~�h��Ƃ��Ă̋@�\���������ނ̈�r�����ǂ��������a�S�R�N����n�܂��������ݕۑ����Ƃɂ��]�ˎ���̖ʉe����݂��������B���a�T�P�N�ɍ��̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳�ꂽ�B |
 |
�A
���a�T�P�N�ɍ��̏d�v�`���I�������ۑ��n��ɑI�肳�ꂽ�A�B���{�ōŏ��ɍ]�ˎ��㖖���̏h�꒬�����ƕۑ����s�����ꏊ�ł���B�u�o�����v�Ɓu�G�Ɋi�q�v����
�h�ꕗ�i���c���Ă���B
���ďh�͓`���I�������Q�Q�R���c������؊�ȂNJ������P�R�������݂����w��̓��蕨���Ƃ��Ă��ׂĂ����j����镶�����ƂȂ��Ă���B |
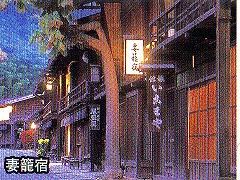 �W���S�R�Om �W���S�R�Om |
| ���ďh�̒��� |
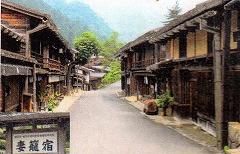 |
| ���ďh�܂� |
 |
�F�J�ƏZ��
�P�X���I�����Ɍ��Ă�ꂽ�����̈ꕔ�B���E�̔����Â��ꌬ�̉ƂƂ��Ďg�p���ꂽ�B |
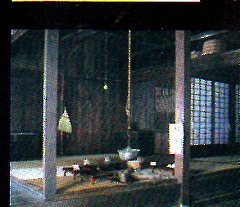 |
���Č����ԏ��̐�
�퍑���ォ��\�����I������܂Ŋ֏��������ꒆ�R�����s���l�X���Ď����Ă����B
|
 |
���D��
���ł����u����f���v�ō]�˖��{�������ɑ�����@�x�������������́B |

 |
| ���ԏ��� |
|
| ���ďh�ӂꂠ���� |
|
�C
�e�{�w���J
�ؑ]�ܖ̋���������Ė����P�O�N�i�P�W�V�V�N�j�ɑ��w����Ō��đւ���ꂽ�̂����݂̌����ł���B�����P�R�N�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B
���蓡���̗c�Ȃ��݁u����ӂ���v�̉ł��� |

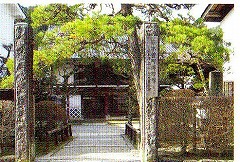
 |
| �Ȃ܂��ǂ̑� |
 |
| ���J����̊� |
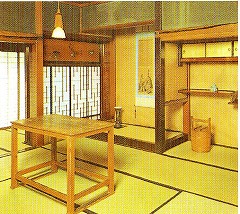 |
���J
�͘F���̊� |
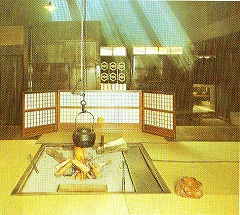 |
�����V�c
�䏬�x�� |
 |
����S����
�F�� |
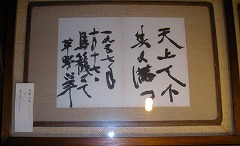 |
�����t�v��
�F�� |
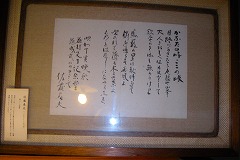 |
�O�c��終�
�F�� |
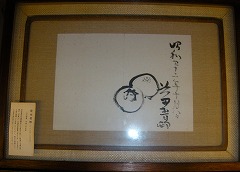 |
�Έ�ߎO��
�F�� |
 |
��ؑ]��
������ |
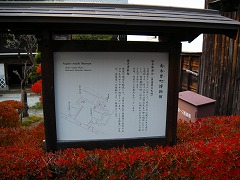 |
��ؑ]��
���j������ |
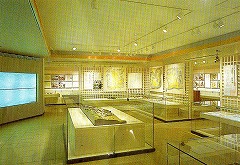
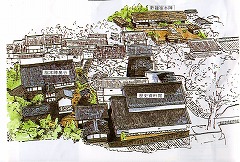 |
��ؑ]�w
�Q�F�Q�O
���J�����w��^�N�V�[�Ŗ߂� |
|
|
| |
|
| �V���� (�����Q�T�N�P�P���Q�V���@���j��) |
�ؑ]�J�{�s�@�@���R���@��(��P�R����)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�W������R�V�P�� �j |
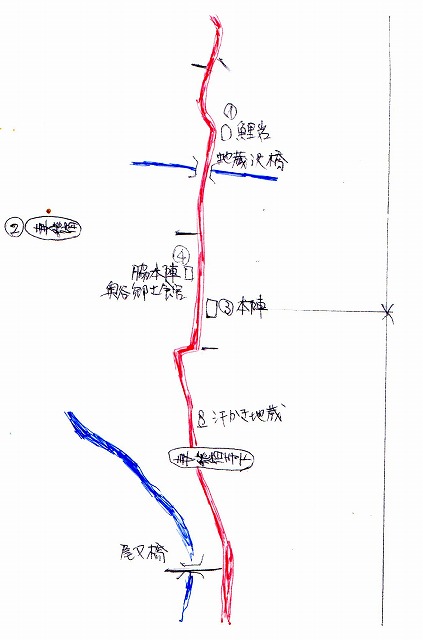

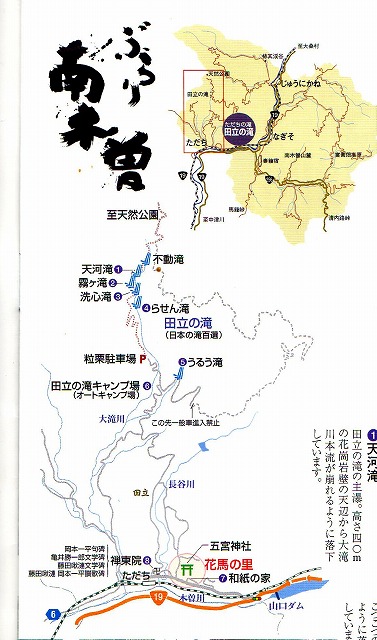
| ���̉w�˕� |
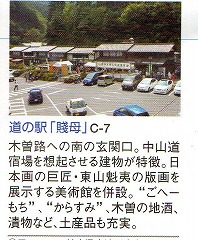 |
�T���@
���̏Z�E���c�a���͉̐l���{���̎q�̈���q�B���̉��ʼn��{�ꕽ�A�T�䏟��Y�A���{���Y�A���˓��⒮���K�ꋫ���ɂ͑����̕��w�肪����B |
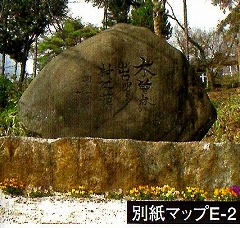 |
| �܋{�_�� |
|
�Ԕn�Ղ�
(���w�薳�`����������)
����͂����ܐF�̎��ŏ���ꂽ�ؑ]�n���J���ۂ��]���܋{�_�Ђ̋����܂ŗ��������������̉Ԃ���肠���B
|
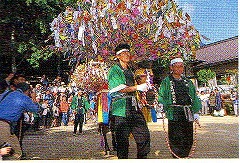 |
�c���a���̉�
������
��ؑ]���̓c���n��͂R�O�O�N�O����u�a���̗��v�Ƃ��Ēm���Ă���B�u�c���a���̉Ɓv�ł͂��̓`���Z�p��`���Ă���B |
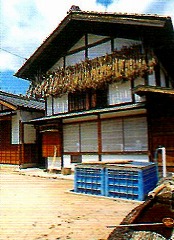

|
| |
|
| �c���̑�L�����v�� |
 |
| ���邤�� |
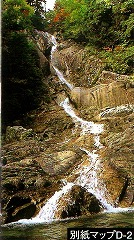 |
| �点��� |
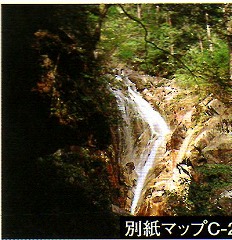 |
| ������ |
 |
�c���̑�(�V�͑�)
��ؑ]���c��
�c���̑�͍����S�O���̓V�͑�����e�ɂ��邤��A�点���A������ȂǑ���̌k�J�ɂ����閳�����e�z�̑��́B |
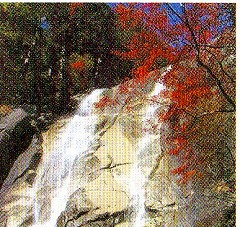
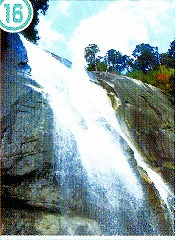 |
| �V�R���� |
|
|
| |
7���ڂ̂P |
��ؑ]�w
�W�F�R�O
�^�N�V�[�ō��ďh�܂ōs�� |
|
�B
���ďh�{�w
���蓡���̕�̐��ƁB
�{�w�͑�X���莁���߂Ă������n�Ă̓��莁�Ƃ͓����Ŗ����ɍ��Ă���ʂ����n�Ă̓��萳���i�閾���O�̎�l���R�����j�̂��Ƃɉł����B ���l�̎q�������������q���t���i�ߑ�̕������蓡���j�ł���B�����̎��Z�L���͍��ďh�{�w�̗{�q�ƂȂ�Ō�̓���ƂȂ����B |

 |
���ďh�{�w
�����Q�O�N�ɍŌ�̓��哇��L���i�����̎��Z�j�������֏o���������ꂽ�B�{�w�Ւn�͂��̌�䗿�ǂ�c�я� �Ɏg�p����Ă��������ɕ���������ꂽ�̂��@�ɕ����V�N�S���ɍ]�ˎ������̊Ԏ��}�����Ƃɒ����ɕ��������̂����̌����ł���B |
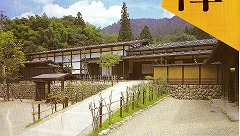
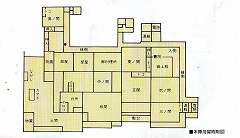 |
| �K�� |
 |
| �X�֎����� |
|
��ؑ]����
�}���z�[����
�}�� |
 |
��S�U��
��������
�����G��
�V�s�� |
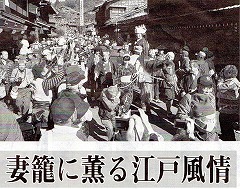
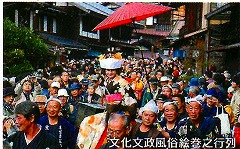 |
���R�@��
�S�̗��H�� |
 |
| ���Ă̒��� |
 |
�X�֎�����
���ėX�ǂɕ��݁B���蓡���̖閾���O�ɂ��J�ݓ����̗l�q���`����Ă���B |
 |
�M�����N�Z�C
���V�R�L�O��
�a�q��_�Ж��߂����Ƃ̒�� |
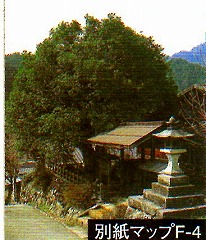 |
������
�₶��������̂��b���c�� |
|
���`
����ƍN���c���U�N�i�P�U�O�P�j�ɏh��𐧒肵���ې����喼�̖d���ɔ����]�˂ւ̐N�U�������ł��x�点�邽�ߏh��͈��̏�ǂ̖�������������Đ�������h��̏o������ɂ͕K�����`���݂���ꂽ�B
�X�����x���p�ɋȂ��O�G���N�����ɂ����悤�ɂ����̂ł���B���ďh�̖��`�͖����R�Q�N����̑啽�X�����C�H���ɂ�肻�̏㕔�Ζʂ��@�芄���Ă��邪�悭�����̎p��`���Ă���B |

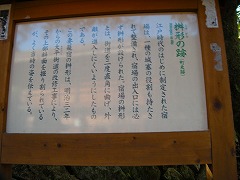
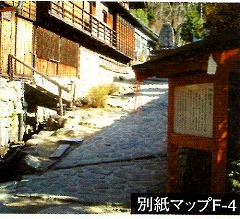 |
������
�����X�N(�P�T�O�O�N)�ɊJ�R���ꂽ�Ƃ����Ă���B
�ؑ]�H�����_
�b���
�ɗ��ɂ͖��������ɐ����a�����l�Ă����ԕt���āi���L�`�������j���W������Ă���B |
 |
��������
�}���� |
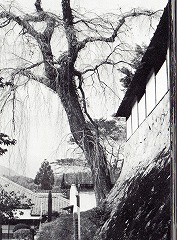 |
�����n��
�i�������n���j
�����P�O�N(�P�W�P�R�N)�������Z�E���O�a�����n�������̕����яオ���Ă����𗖃M�삩��^��ł��Ĉ��u�������́B |
 |
�Ε�
�u���R�E���v��
�����B��Ƃ����Ε��u���R�E���v���B�o�̑��͑��ɗޗႪ�Ȃ��B |
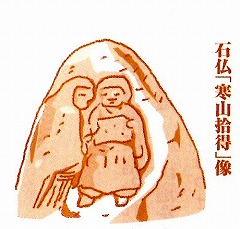 |
| �܂˂� |
 |
| �����㉮ |
 |
| �����㉮�͓��������ł��������̂̈ꕔ�����a�S�R�N�ɉ�̕��������B�����̏Z�����\����Гy�Ԃɕ����Ԏ��̌`�����悭�Ƃǂ߂Ă���B |
 |
| |
 |
�����̒�����
�����n��͍ŏ��ɕۑ����Ƃ��s��ꂽ�B |
|
�㍵�㉮
���a�S�S�N�̉�̕����ɂ���ĂP�W���I�����̖ؒ��h�ł��邱�Ƃ����������B |
|
| �a�q��_�Ѝ� |
 |
�X�։�����
���ėX�ǂƗX�֎�����
���ėX�ǂ͖����U�N�R�����ėX��p�戵���Ƃ��ĊJ�݂��ꂽ�B�����̎戵�����͖{�w�ɂ����������̌㖼�̂�ꏊ���ς�菺�a�T�S�N�P���Ɍ��ݒn�Ɉڂ����B�����͏d�v�`���I�������Q�ۑ��n�撬���݂̌i�ςɍ����悤�ɏo�����̌`����p���đ����Ă���B�X�֎����ق͂��̗X�ǂ̒��ɂ��菺�a�U�O�N�V���ɊJ�ق����B�����S�N�V���X���x�n�Ǝ��̕������͂��ߎ���̈ڂ�ς��ɔ����X�֊W�̋M�d�Ȏ������W������Ă���B |
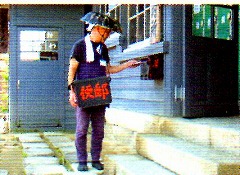
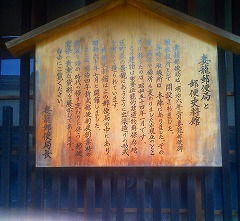
|
����W��
���݂̃|�X�g�͏��߂͏���W����W�M���ƌĂ�]�ˎ���̖ڈ���(�i��)�������ǂ��Ă���B���ďh�̒��̃|�X�g�͒����݂̌i�ςɍ��킹�n�Ǝ��̏���W���Ɠ����`�ɑ���ꂽ�B�S���ŗB��̍����|�X�g�Ƃ��ĕ������ꂽ�ŏ��̕��Ō����̃|�X�g�ł���B |
 |
| |
 |
|
| |
|
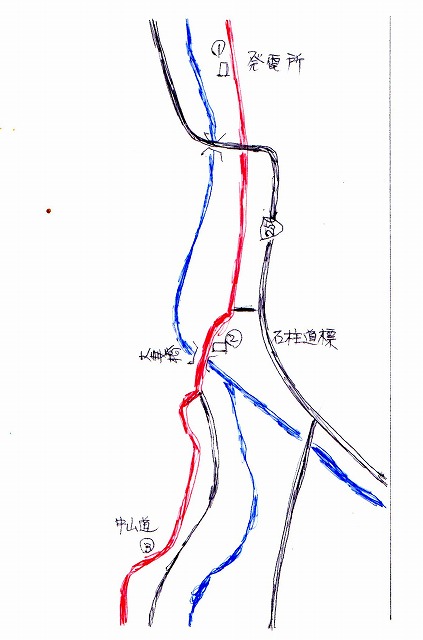
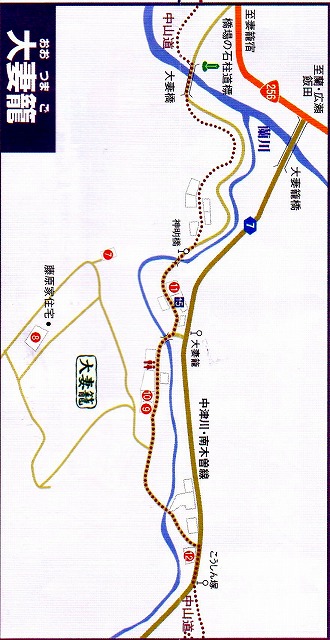
| |
���@�@�@�� |
| ���Ĕ��d�� |
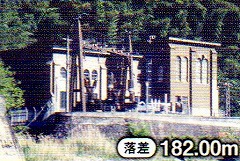 |
| ���씭�d�� |
 |
| |
|
|
| |
7���ڂ̂Q |
�@
���Ĕ��d��
���ďh�ŗB��̓S�R���N���[�g�̌��� |
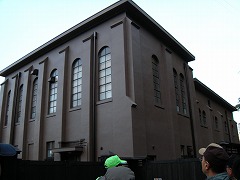 |
�A
���R���̓��W
�����R���[�g�����܂�̑�Β� |
 |
�����W
�̐���
�����Q�T�N���˕�V�����J�ʂ���܂Ŕn�ā`���ā`�O�����ʂ钆�R���͌Â����犲�����H�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B���Ƃɍ��Ă̋���͒Ǖ��Ƃ��Ăꒆ�R���Ɣѓc�X���̕���_�Ƃ��ĉh�����Ƃ���ł���B
�����P�S�N�U���ɔѓc�̊F�씼�l�Y�����N�l�ƂȂ��ē����̏��䋻�Z�E����s���q�E�����F��̐��b�l�ƂƂ��ɔѓc�E�]�B�E�n���̏��l�ɂ���ĐΒ����W�����Ă�ꂽ�B |


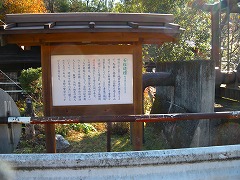 |
| ��ȋ� |
|
�B
���R�� |
 |
|
| |
|
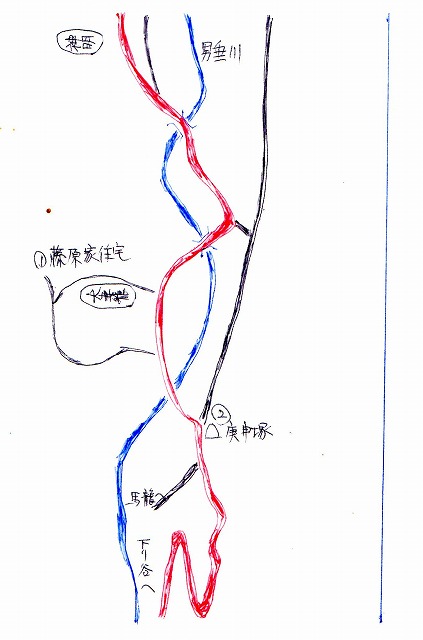


| ��ؑ]���� |
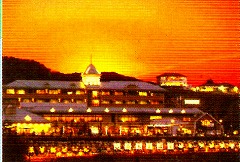 |
| �ؑ]�H�� |
|
��ؑ]�x
�W���P�U�V�U��
�ؑ]�R�x�̈�B�ʖ������R�ƌĂ�Â��͎R�x�C����ƂȂ��Ă����B |
|
| ��ؑ]�x����ԎR��]�� |
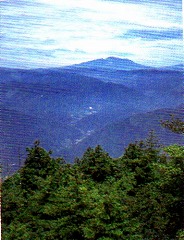 |
���i����炬�j����
����R�O�O�N�ȏ�̖ؑ]�ܖi�w�E�����E�����Ȃ�E�˂����E����ꠁj�̌Q�����鎩�R�T���� |
 |
| ��ؑ]�R�[���L�����v�� |
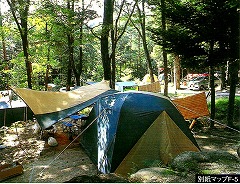 |
�낭��H�|
(���w��`���I�H�|�i)
�P���L�E�g�`�E�Z�����ǎ��Ȗ؍ނ����肾�����o��~�B������ƕ������͗y����N����ؒn�t�����̎�Z�B |
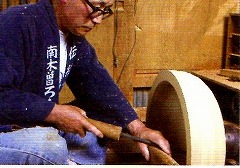 |
| ���L�����v�� |
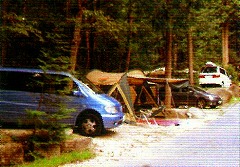 |
| ���O�} |
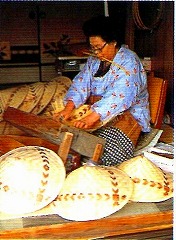 |
| �H�|�X���Ղ� |
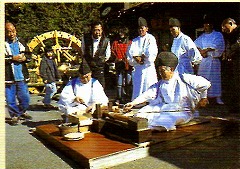 |
| �x�M�������ԓ��Ղ� |
 |
|
|
|
|
7���ڂ̂R |
�@
����
�����ƏZ��
�P�V���I���̌Â����z�B���a�U�R�N�ɕ����C�����ꂽ�B |

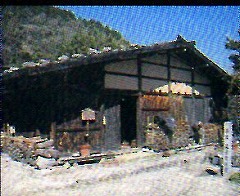 |
| ���� |
|
�A
���R���M�\�� |


|
�����ω�
�̑����}�ȍ⓹���v���ו����^�Ԃ��߂ɍ������g��ꂽ�B���̍����̋��{���B���R���ŗB��̋����ω��B |


 |
| ����J�ꗢ�� |
|
| ����J |
|
|
| |
|
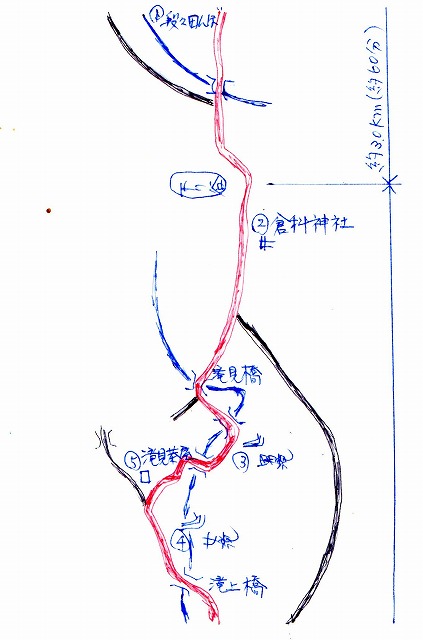 |
| |
7���ڂ̂S |
�@
�i�X�c��� |
 |
�A
�q�ȑc���
���{��召�}����c�̏d�b
�q�Ȏ��Y���q��͎�l���}����c�̖����đ��̖L�b�G�g�̂��ƂɎg���ɂ������̋A��ɔn�ē��ł��̒n�̓y�������̏P���ɉ���킵�������ɉ���J�ŏ]�҂R�O�]���ƂƂ��ɓ������ɂ��Ă��܂����B�Ƃ��ɓV���P�S�N�i�P�T�W�U�N�j�R���S���̎��ł������B�����͖ؑ]���Ə��}�����͉��x�������������Ă��肻�������������炱�̑������N�����Ǝv����B���̑q�Ȏ��Y���q��̗삪�J���Ă���B |

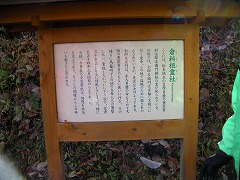
 |
��K�P���h����
�����V�c���H�������@���ꂽ�Ƃ��������ōŏ��̐ΐς݂̍��h����B�y���ɖ�����Ă������̂��������ꂻ�̈ꕔ���݂邱�Ƃ��ł���B |
|
�B
�j��
�j�ꏗ��͖ؑ]�ɊX�����J����Ĉȗ������Ƃ��Đe���܂�e���̏�ł������B��y�ё��͍^����֔����Ȃǂō�����[���������Ă��邪�Ȃ������̎p���Ƃǂ߂Ă���B����ӂ͌��j�Ȃ��ߓ��͂����Εt���ւ���ꖋ�����܂ł̒��R���͑�̉���ʂ��Ă������̂Ǝv����B���ݑ���ʂ��Ă��铹�����j�̓��ł���B
�g��p���̏����u�{�{�����v�̕���ƂȂ�����B���ɋ��̌{���������Ƃ����q�ȗl�`�����`�����Ă���B |

�{�{���������̏C�Ƃ�
�����Ƃ���Ƃ��ėL��
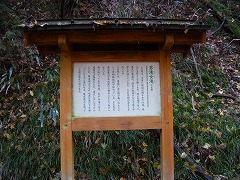

 |
�C
���� |
 |
�D
�ꌩ����
�Βu������
�̉�
�̖L���Ȗؑ]�ł͂X�X�C�X�p�[�Z���g�������ł������B�̓T�������g�������ɐ��ڂ��Ă����B
�c��̂O�C�P�p�[�Z���g�͓�쑺�̕��Ƃ̗��l���ς�ł��������ł����͖��������犝�����ł������B |


|
| |
|
|
| |
|
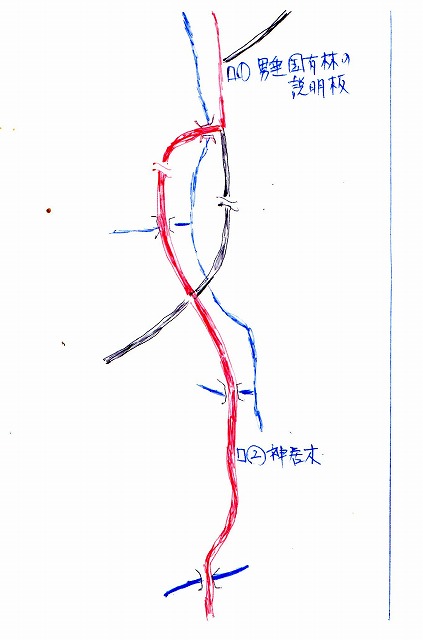 |
| |
7���ڂ̂T |
�@
�j�����
���L��
���R���̓�����т͖ؑ]�X�ъǗ�����ؑ]�x���Ǔ��̓엖�L�тł���B���̒��R�������̒j?�i������j�R��т͕��v�ی�тɎw�肳��w�E�����E�����ЁE����ꠁE�˂����̂�����ؑ]�̌ܖ��T���Ɛ������Ă���B�����̑�͍]�ˎ���͒�~�Ƃ��Ė����ɂȂ��Ă��犯�т���ɖ����Q�Q�N�ȍ~�͌䗿�тƂ��ĕی삳��Ă����B�܂����̈�т͍��̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳��Ă���B |


|
���R��
��ΓȌ� |

 |
�F�悯��
�e�[�v |

 |
�A
��������
���̞��i�����j�̉��}�������オ���ē��قȎ}�Ԃ�ɂȂ��Ă��邪���̂悤�Ȍ`�̎}���������j�t����_���i���������j�Ƃ����B�V��̍��|�Ƃ������B�̂���R�̐_�i�܂��͓V��j�����������ċx�ޏꏊ�ł���ƐM����ꂽ�B������������肷��Ƃ����܂��M��Ƃ����`�����[�l�i���܂тƁj�͂��̖̉���ʂ邱�Ƃ����������B���̖̂悤�ɗ����ɉ��}�������オ�����𗼐_���Ƃ����B |

 |
|
| |
|
 |
| |
7���ڂ̂U |
�@
���
���؉��ԏ�
���؉��ԏ��͖ؑ]����ڏo�����؍ނ������܂邽�ߐ݂���ꂽ�B�w�̏��}�Ɏ���܂ŋ�������������Ă��Ă��邩�ǂ����ׂ�قnj��d�ł������Ƃ����Ă���B�ԏ��͍ŏ�����J�ɐݒu����Ă������ؑ]������o���ɂ��Ɗ����Q�N�i�P�V�S�X�N�j�̎֔����ɂ���Ă�����ΓȂɈړ]�����B |
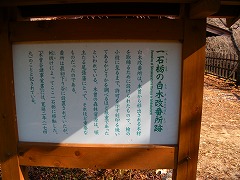
 |
�A
��ΓȊω����Ǝ}����
�}������͒��̓V�R�L�O�� |
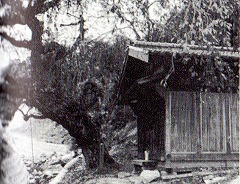
 |
���
���ꒃ��
���ꒃ���͏h�Əh�̒��Ԃɂ����ė��l�ɋx���Ɨ��ւ�^�����B��Γȗ��ꒃ���͍��ďh�Ɣn�ďh�̒��ԂɈʒu�������͂V���قǂ̉Ƃ������ĉh���Ă��������͖q��ƏZ��ꌬ�����ɂȂ��Ă���B�q��ƏZ��͍]�ˎ������̌����œ����͊Ԍ����\�Ԕ��������������݂͓쑤������ꔪ�Ԃɏk������Ă���B |
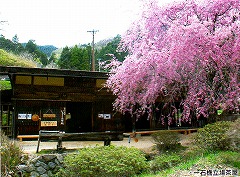

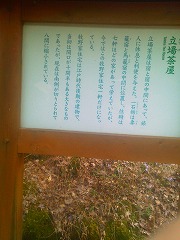 |
�B
�n�ē�
�C���W�O�P�� |

 |
| �{���̂W�O�P���͂��̎R�̏ゾ�Ƃ����B |
 |
�C
�n�ē�
���̒���
�W���V�X�O�� |
 |
�D
�����q�K�̋��
���_��
�t��t�̎O�\��
���̒����̂����e�ɐ����q�K�̋�肪����B |

 |
| �V���E�W���E�o�J�} |
 |
�E
�F��_�� |

 |
|
| |
|
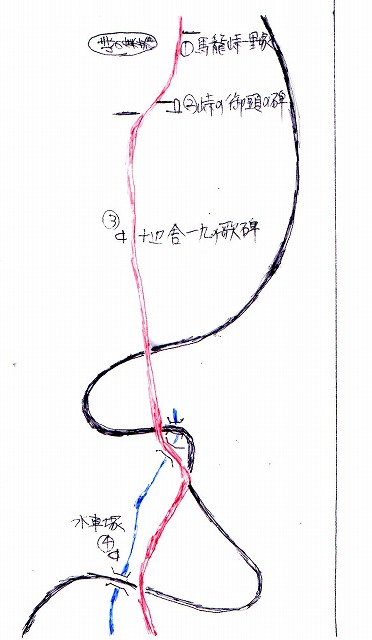
| �I�J���k��n�Ĕ��i�v |
 |
| �I�J���k���`�����n�ďh�̖������i�ɔ��Z�h�̔o�����������쎩�M�̋�ĕ\�������ꕝ�̊|�����B�V�ۂV�N�i�P�W�R�U�j�쐬�B�o�~���Z�h�͏Ԗ�\�N(�����m�Ԃ̖剺�̂����D�ꂽ�҂P�O��)�̂ЂƂ�ł���e���x�l�i�P�U�U�T����P�V�R�P�j�ɂ���č]�ˎ���L�����y�������h�B |
| ���a�R�N�A�u�閾���O�v���M�̑O�������W�̂��ߔn�Ă�K�ꂽ�����͂͂��߂āu�n�Ĕ��i�v�������B |
| ���z��J |
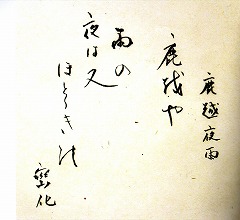 |
| |
���z���� �J�̖�͖� �قƂƂ��� �ۉ� |
| �����H�� |
 |
| |
�͂͂���
�@�@���˂Ă݂͂₯�ӂ̌��@���� |
| �Ԋ_�ː� |
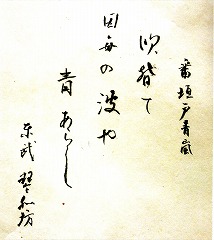 |
| |
���ւēc���̔g����炵�@
�����a�V |
| �h��A�� |
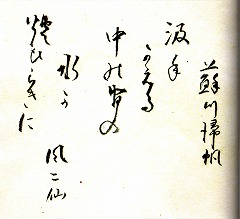 |
| |
���݂Ă�����
�@�@���̊Ԃ̐����F�Ђ炫���@����� |
| �w�˓c���� |
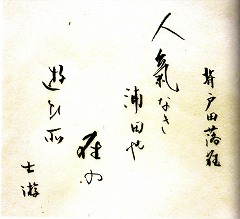 |
| |
�l�C�Ȃ��Y�c���̗V�Џ��@
�y�� |
| �b�ߕ�� |
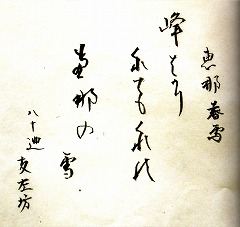 |
| |
��͂����Ă����ꂸ�b�߂̐�
�@���\�g�F���V |
| �{��[�� |
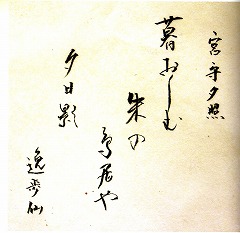 |
| |
�邨���ގ�̒�����[���e
����� |
| �i�����ӏ� |
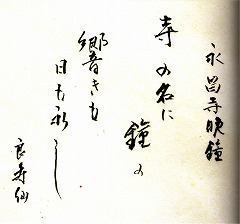 |
| |
���̖��ɏ��̋����������i��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǎ��� |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| �����V�u�n�Ĕ��i�v�o�� |
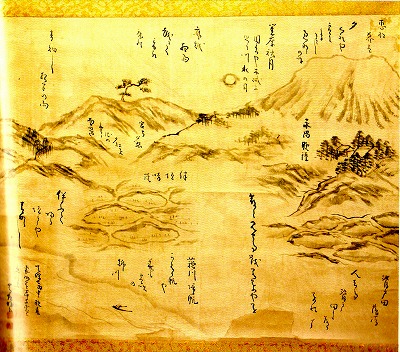 |
| �V�ۂV�N�i�P�W�R�U�j�쐬�B |
|
| |
�V���ڂ̂V |
���̏W��
���P�Q�N�i�P�V�U�Q�j�̑�̌�Ђ��Ȃ����߉Ɖ��͍]�˒����Ȍ�̎p�����ɂƂǂ߂Ă���B�]�˒n�ケ�̓��̏W���̐l�X�͖��Ԃ̉ו����^������u�����v���ƋƂƂ��Ă��葭�Ɂu���D�v�ƌĂ���Z�̍��n���牓���͒���̑P�����ӂ�܂ʼnו����^�B�����O�N�i�P�W�T�U�j�����̂��́u�����v�ƒ��Ð�̖≮�̊ԂɋN�����X�g���C�L�͓����́u�閾���O�v�ɂ��o�ꂷ��B |
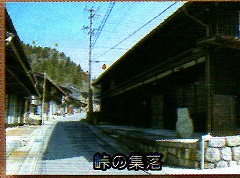

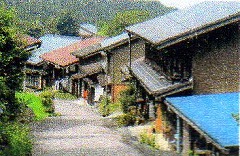
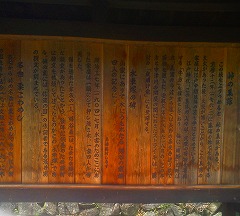
|
| ���Ȃ��� |
 |
�@
�n�ē��ꗢ�ː� |
|
�A���̌䓪��
�����O�N���W���̋����i�����g���ĉו����^�Ԑl�j�����Ð�̖≮�i�ו��̎�莟��������Ƃ���j�Ƃ̊Ԃʼn^���̔z���̑��������苍�����������B���s���i���j�̍�����]������ |

 |
�B
�\�ӎɈ���
�̔�
�a���
�ނ������͌����˂ǂ�
�I�̂��͂߂�
�����T���� |

 |
�C
���Ԓ�
�����R�V�N�R�Ôg�ŖS���Ȃ����I�J�ƈ�Ƃ̋��{�̒ˁB�����͓��蓡���̕M�B |


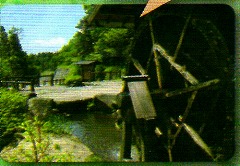 |
���Ԓ˂̔�
�����͓��蓡���̕M |
 |
| �n�ē� |
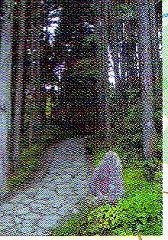 |
| |
|
|
| |
|
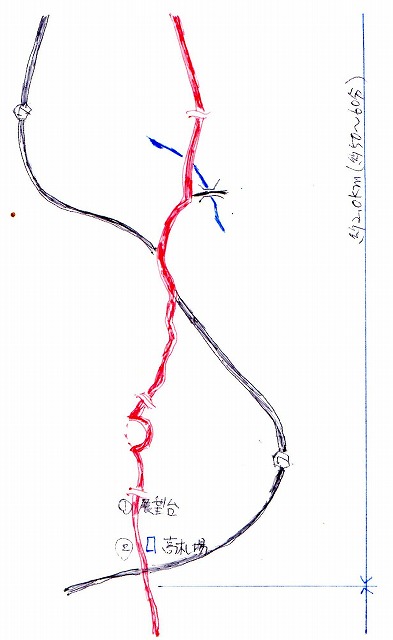 |
| |
7���ڂ̂W |
�b�ߎR
�@
�W�]�䂩��݂�b�ߎR
�Q�P�X�P�� |
 |
���萳���̊����Δ�
���蓡���̕������������܂�̋��̖ؑ]�J�̐_����ق߂����������̂ł���B |
 |
�z������
�L�O�� |
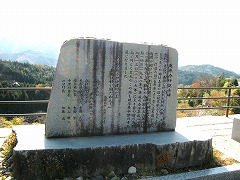 |
�����̔�
�j�C�`�G�̌��t��������Ă���B |

 |
�A
���D��
���D��͏h��̏o������ɂ���ؑ]�P�P�h�ł͂Q�Q�������̂������݂͔n�āA���āA�����A�ޗLj�̂S�J���ɂ̂ݎc���Ă���B�����̍��D��͎��ۂ̑傫���̂S���̂R�̑傫���ɕ������Ă���B |

 |
|
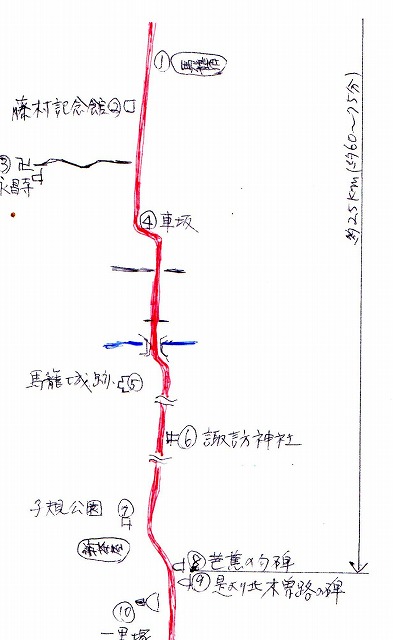
| �R���_�� |
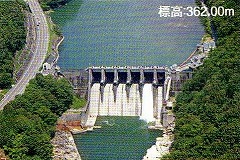 |
�˕ꔭ�d��
�吳�W�N
����ŏ��Ɍ��݂����B |
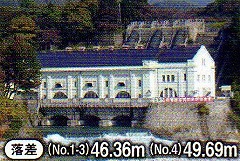 |
| �R�����d�� |
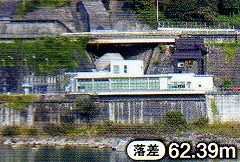 |
| �����_�� |
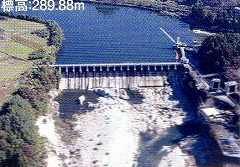 |
| �V�������d�� |
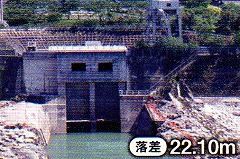 |
�������d��
����͖ؑ]��łV�̔��d������|���吳�P�T�N�ɍŌ�̗������d�������������B
���͔��d�Ɉꐶ�����������{�̋ߑ㉻�Ɣ��W�ɍv����������́u�d�͉��v�ƌĂꂽ�B
�j�ɒB�Ȃ炠�̖ؑ]���
�@�@�@�@���ꂭ�鐅�~�߂Ă݂� |

|
| |
|
| ���̉w�u�˕�v |
 |
| �N���A���]�[�g���M�� |
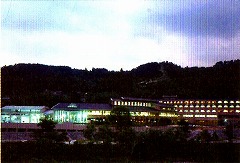 |
| |
|
| �����L�O�ُ�ݓW�����i��O���Ɂj |
| ���W |
|
 |
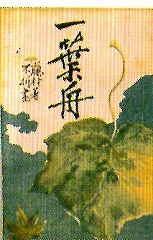 |
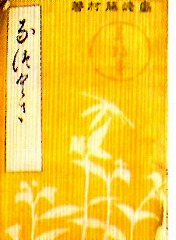 |
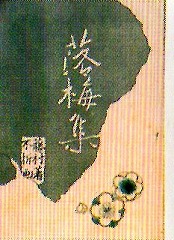 |
| ���� |
|
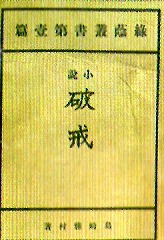 |
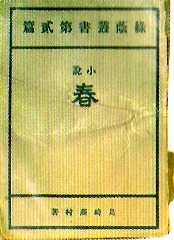 |
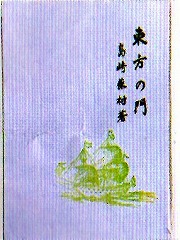 |
��
�閾���O
���̎��̏n���鎞
�V��
�� |
| ���b |
|
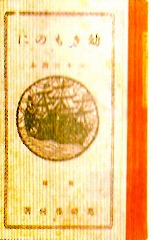 |
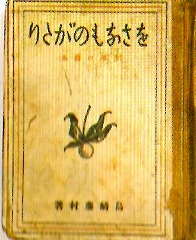 |
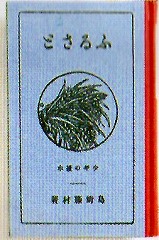 |
|
| �I�s���W |
�����������
�C�� |
|
| |
7���ڂ̂X |
��S�R��
�n�ďh
�{�w�@�P
�e�{�w�@�P
���ā@�P�W�� |

|
�@
�n�ďh
�n�ďh�͔�����ԖڂƂ���Ǝl�\�O�Ԗڂ̏h��ɂȂ�]�˂���̋����͔��\�O���Z���]��ƂȂ��Ă����B�X�����R�̔����ɉ������}�Ζʂ�ʂ��Ă���̂ŗ����ɐ�ς�ʼn��~��u��̂���h��v�������ł���h��̒����ɂ͍��M�Ȑl�̏h���ɔ������u�{�w�v��u�e�{�w�v�ו��^���̍��z������u�≮�v���u���ꗷ�l�̗��p����u���āv���\�������̂ق��u�щ��v��u�n�h�v�������čs���������l�œ�������B������\�ܔN�i�P�W�X�Q�j�ɖؑ]�쉈���ɍ������J�݂��ꖾ���l�\�ܔN�i�P�X�P�Q�j�ɂ͍��S���������J�ʂ������Ƃɂ��h��Ƃ��Ă̎g�����I�����B������\���N�i�P�W�X�T�j�Ƒ吳�l�N�i�P�X�P�T�j�̓�x�̑�ɂ��]�ˎ���̈�\�̂قƂ�ǂ��Ď������B |

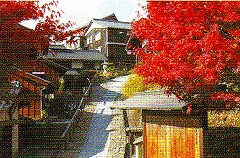 �W���U�O�Om �W���U�O�Om
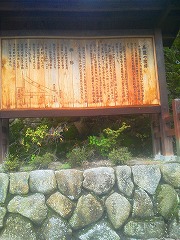 |
| ���q���v�荇��̐w��� |
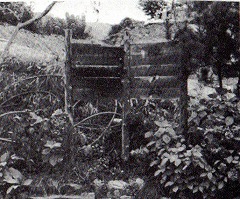 |
�n�Ęe�{�w�����وē�
�h��ő喼��g���̍����l�̏h���ɔ������Ƃ�{�w�e�{�w�Ƃ����˂̕ی���Ă����B�n�ďh��e�{�w�͖����Q�W�N�̑�Ō����͏Ď������B�n�Ęe�{�w�����ق͘e�{�w�̍ō��ʂ̕����ł����i�̊Ԃ��̏ꏊ�ɕ������Ă��� |
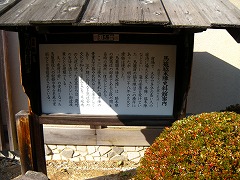
 |
| �R�����q�̋�� |
 |
| �P�Q�F�O�O |
���H
�����̏����̉̂ɏo�Ă��邨�䂤����̐��Ƃ̑单���Œ��H���Ƃ�B
 |
�A
�����L�O��
���蓡���̐���
��U��_�̍�i�������W�����Ă���B |

|
�B����
�����Q�W�N�̑�ŏĂ��c�����c����̉B�����B�c�������̕������ł��������B�����͏��N���ケ�̃j�K�̕����ŕ��c�h�̍��w�҂ł�����������l���܌o�̑f�ǂ����B |
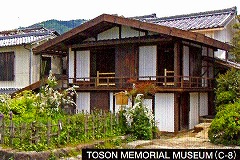

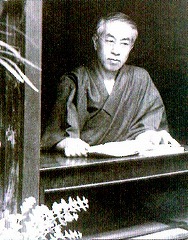 |
���蓡��
�Q���h���l�Ƃ��āu��؏W�v�Ȃǂ����s�B�X�ɏ����ƂƂ��āu�j���v�u�t�v�Ȃǂő�\�I�Ȏ��R��`��ƂƂȂ����B���ɓ��{���R��`���w�̓��B�_�Ƃ����u�Ɓv�������f���ɂ������j�����u�閾���O�v�Ȃǂ��������B |
|
�B
�i����
���蓡���̕��
�u�閾���O�v�ɂ͖������Ƃ��ēo��B |
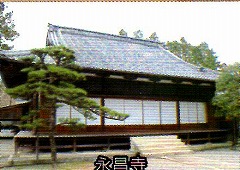
�n�Ĕ��i�@�i�����ӏ�
���̖��ɏ��̋����������i��
�@�@�@�@�@�@�ǎ���

�i�����֓��铹 |
�i�����ɂ��铇��Ƃ̕� |
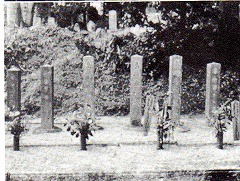 |
�ؑ]�`�����e�P�̕�
�ܗ֓� |
|
������
������
���蓡���̍�i�u���v�ɏo�Ă���u�X����v�i���ꕽ�j�̉� |
 |
�C
�ԍ�
�n�ďh�̖��`
�n�ďh�̊X���̓�[�͒��p�ɓ�x�܂�Ȃ��Ă��肱�̕����̎R�葤�͐�y�ɂȂ��Ă���B����͏�s���z�́u���`�v��͂������̂ł������u���`�v�Ƃ������B�{���h�ꂪ�R���I�ȖړI�������đ���ꂽ���Ƃ������Ă���B�����O�\���N�i�P�X�O�T�j�̓��H���C�ɂ�蓖���̌��`���Ď����������̌�Z�\�N��ɕ������ꂽ�B
|


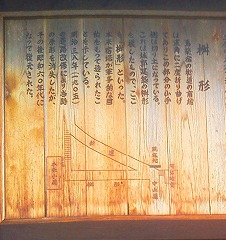 |
���`�ɂ��鐅�ԏ���
���݂͏����͔��d�����Ă���B |
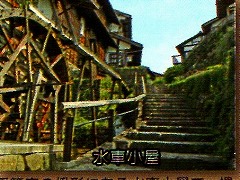

|
| ����ɓ� |
|
���̉w
�����≺ |
|
���P��
�ؑ]��̗��ꂪ�Z�H���Ăł������̉��P����͂��ߒn���ł͂��̈�т𗳋{�ƌĂ�ł���B |
 |
�܂���
���R�A���� |
|
| ���R�����̉��� |
 |
�D
�n��
������T�O�O�N�قǑO�̎������ォ��n�ď邪���������Ƃ��L����Ă���B�퍑����n�Ă͕��c�M���̗̒n�ƂȂ邪���c�M���ŖS��D�c�M���̎�����o�ĖL�b�G�g�P���̖ؑ]�`�������߂��B�V���P�Q�N�i�P�T�W�S�j�R���L�b�G�g����ƍN�̗��R�͏��q�R�ɑΛ������B�G�g�͓���R���U�ߏオ�邱�Ƃ�h�����ߖؑ]�`���ɖؑ]�H�h�q�𖽂����B�ؑ]�`���͕��R�S�𑗂��ĎR���Ǐ��ɍ��ď���ł߂������B�n�ď�͓��蓡���̑c�ł��铇��d�ʂ��x�������B�V���P�Q�N�X������ƍN�͔ѓc�̐����藘�����̕ۉȐ����z�K�̐z�K������ɖؑ]�U���𖽂����B�O�R�͍��ď���U�߂��̈ꕔ�͔n�ĂɍU�ߓ���n�Ă̖k�ɐw�n���\�����B�����̕ӂ��w��Ƃ����B�n�Ă�����Ă�������d�ʂ͂��܂�̑�R�ɋ�����Ȃ���A�ɂ܂���Ėؑ]�쉈���ɍ��ď�֓��ꂽ�B���̂��ߔn�Ă̏W���͐����Ƃꂽ�B�c���T�N�i�P�U�O�O�j�փ����̐킢�œV���𐧂����ƍN�͖ؑ]���̂Ƃ��Ă��������a���N���B����`���̗̒n�ƂȂ�Ȍ��̂Ȃ��܂ܔn�ď�͎p���������B |
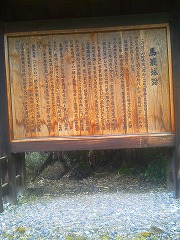 |
�E
�z�K�_�� |
 |
| �����̔� |
 |
�~�c�o
�c�c�W
�t���O���ł���B |
 |
�F
�q�K���� |
|
�����q�K��
���
�K�̎���
�ؑ]�H�o�Â��
�䔞���� |
 |
�G
�m�Ԃ̋��
������
����ʂĂ�
�ؑ]�̏H |
|
�V����
���̕ӂ�̒n����V�����Ƃ����B�]�˂̍��h��Əh��̊Ԃɂ��钃���𗧂ďꒃ���Ƃ������B���Ă̒����͂�����������ɐ��S���[�g���قǓ������ꏊ�ɂ��������]�˂̏I��荠���ݒn�Ɉڂ����B���̂��߂�����V�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�n�݂����̒����̖����ł������Ƃ����B |
�W���S�X�Tm
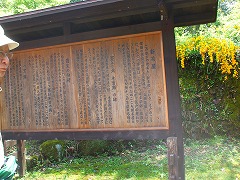
 |
�H
������k
�ؑ]�H
�����͌����쌧�Ɗ��̍�B�ؑ]�H�̓�����ɓ�����B
���a�P�T�N(�P�X�S�O�N)�V�������U�W�������������n���̗v���ɂ���Ċ��|�����B�����͂U�O�����玩����u�V�l�v�ƋL���悤�ɂȂ������̓��͓����L�O�ق̗����P�O���N���L�O���ď��a�R�Q�N(�P�X�T�V�N)�P�P���ɓ����L�O�ٌ��݂̎��s��̂ł���ӂ邳�ƗF�̉�ɂ���Č������ꂽ�B�B |
 |
�V������
�ꗢ�� |



|
�Ȃ����̓m
�{�����u�ЂƂ����v�Ƃ����Ð���̈ˑ��ł���B�T�����{���̊J���Ŗ��J���͎��オ�^�����ɂȂ�Ⴊ�ς������悤�Ȍi�ς������Ƃ����B���a�T�P�N�����V�l�N���u���A�������B |

 |
| �o�H�O�R�_�� |
 |
������
�Ώ�
�W�S�O���ɂ킽��Ώ�������̎j�գ
�����̂��̂͂V�O�������c���Ă��Ȃ�������������W�S�O���܂ŐL�����̂ł���B�����̂��̂ɂ͑傫�Ȏ��R�̂܂܂̐��g���Ă���B
���̐Ώ�͒��R���̏h�ꗎ���Ɣn�ĂƂ̊Ԃɂ���\�ȓ��̍⓹������₷���悤�ɐ�~���Ȃ�ׂ����̂ł���B�]�ˎ���̎�ȊX���ɂ͈ꗢ�˂�A���𑽂��A�����x�������̕ی�ɂ͐₦�����ӂ������Ώ�ɂ��Ă͉����l�����l�q���Ȃ��Ƃ����B���̂��ߏ��܂ܕ��u����邱�Ƃ����������̐Ώ���ꎞ�͍r���܂܂ɂȂ��Ă����B�n���̐l�����̋ΘJ��d�Ō��`�ɕ��������B
�������̎p���Ƃǂ߂Ă���̂͂����Ɠ��C���̔����̂Q�ӏ��������Ƃ����B���R�����ł����̂͊��i�N�Ԃł��邪�Ώł����̂͂����s���ł���B���v���N�̍c���a�{�̒ʍs�Ɩ����V�c�̍s�K�̎��C���������Ώ�ɍ����܂��Ĕn������Ȃ��悤�ɂ������Ƃ��L�^�Ɏc���Ă���Ƃ����B |



�����̕����͑傫�����R�̐����鏊�B
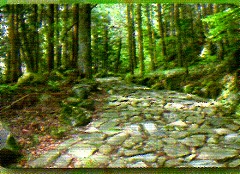
 |
| �Ώ����� |
 |
| �\�ȓ� |
|
�㉤��
�㉤���̎}�����
�o�~�̏@�������V���u���̓����̓����ɐ������������
�Ɖr��������Ƃ���ꂽ���ł������B�ɐ��p�䕗�œ|�ꍡ�͂Q��ځB |





�m�Ԃ̋��
|
�����h�Ώ��
�W�� |
 |
| �Q�O�O����Ώ�ƕW�����Ă��钌 |
 |
| ���R���̕���_ |
 |
| ���R�� |
 |
| ���R���͂��̂悤�ɓ���̂�����̂悤�Ȃ��̂�~���l�߂Ă���B |
 |
�����h��
���D��� |
 |
| �]�˕����̓�����ɂ͓������p�ɋȂ���ꂽ���`������� |

 |
���҂̐^�ɏ�铔���������B
�����h�ɂ̖͐h�Ƃ����ˊe�ˏ����̓����Ԃɂ��̍Г��~���悤�ƋF�肵�Ȃ���ق̂��Ȗ����肪�Ƃ�����Ă����S��̏�铔���������B
���̊����l�N
�i�P�V�X�Q�N�j�Ɍ������ꂽ�㒬�̏�铔�͂����O�̓��̒����ɂ��������P�W�W�O�N�̓��H�����̍ۓ��̕Ћ��Ɋ�ꉝ���̎p�𗯂߂Ă���B
���ƎO��̂������͑P�����̋����ɓ��͂����������̈����ЂɈڂ��ꂽ�B |
 |
| �������N�P�W�O�S�N�\��N�P�W�P�T�N�̓�x�̑�͏h�ɑ傫�ȑŌ���^�����B���������݂������A�i�q�̂��閯�Ƃ� |


 |
| �]�˕��̏\�ȓ��ƐΏ��̗^��t�߂ɂ͍]�ˎ���̖ʉe�������Ɏc���Ă���B |
|
| �������� |
 |
| �����h�e�{�w�� |
 |
| �����h�{�w�� |
 |
�������������劘
���v���N�i�P�W�U�P�N�j�c���a�{�̑�ʍs���ɂ͂S���Ԃʼn��ז�Q���U��l�]�肪�����h��ʂ����B�����g���������ĂȂ������邽�ߊe�Ƃ̂��܂ǂ͈������炸����������ꂽ�Ƃ����Ă����B�����ɓW�����Ă���劘�͓V�����ς鎞�Ɏg�p���ꂽ���̂ł���B |

 |
�����h
���̒����ɂ͗p�������꒬�̒��قǂɖ{�w�Ƙe�{�w�i�Ƃ��ɖ≮�����j������{�w����Ƃ͔�������Ƌ��l�̐瑺���i�v�v�����j�e�{�w�˓c�Ƃ͓����l�̎R�����i�ؑ]���j�̏��������˂Ă����B |
 |
�����h
�����h�͍]�˂ց@�A�W�Q��
�P�Q���i��R�Q�R�����j���ւT�Q���X���i��Q�O�T�����j�̈ʒu�ɂ���A���R���U�X���̂����]�˂��琔���ĂS�S�Ԗڂ̏h�ł���B�������́u���R���h����T���v�̋L�^�ł͏h�̒����͂R���R�T�ԁi��R�X�O���[�g���j�h���̉Ɛ��͂V�T���ł���
�B���������ɂ��鑂���@�̑P�����͌c���T�N�i�P�U�O�O�N�j�̑n���Ƃ���ꕐ�V�S�֑��i�֎s�j�ɂ��间���̖����ł���B�����Q�S�N�̓��H���C�H���Ŏ��̈ꕔ�����H�ƂȂ莛�͓����Ɉڐ݂��ꂽ�B�����ɂ��������͂��̂܂c���ꌻ�݁u�H��̏��v�Ə̂���Ă���B�q�̏��͎��n�����̎R����Ă������Ƃ���u�劥�̏��v�ƌĂ�Ă���B���H�̐V�݁A�g���A���̈ړ]���ō����ɂ߂����Ă����̂��}���S�T�O�N�̔N���o���Ă���Ƃ����Ă��邪���قǑ傫���Ȃ��h��̓�����Ɋi�D�̕��т�Y���Ă���B |


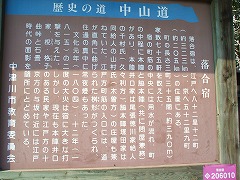 |
| ����h |
 |
����w
�P�T�F�R�O
�����h����^�N�V�[ |
|
|